突然届いた手紙
地方のとある産婦人科病院で働いている看護婦・今田彩子は先日勤続12年の節目を迎え、病院の中堅的な立場として関係者や利用者と友好的な関係を築いている。現在35歳の彩子にとって、この病院で働くことは生きがいとも言え、定年まで勤め上げることを心から望むほど肌に合った職場であった。
この産婦人科医院は個人病院であり、施設としてはあまり大きなものではないが、個人病院であるからこそ可能になる細やかなサービスや配慮、利用者との触れ合いが好評であり、別の地域から診察に訪れる人も少なくない。
彩子の仕事は診察に訪れた人の対応や、入院している妊婦の世話、週に何度かの夜間当直など、好きで続けている仕事ではあるものの、時には肉体的にも精神的にも疲労を感じてしまうことも事実だ。
10代の女子学生が来院し、妊娠が発覚したが、本人は一切悩むこと無く中絶を選択するという出来事が起こったり、せっかく授かった命が不幸にも失われてしまったり、婦人科系の難病が発覚したりと、やるせない気持ちになることも多い。
そんな激動な日々の中で、彩子が仕事の活力としているのは利用者から寄せられる感謝の言葉だった。病院で直接言われることがほとんどだが、病院宛に手紙が送られることもある。
『この病院を選んでよかった』
『悩んでいた病気を治すことが出来てよかった』
そんな言葉を掛けられると、彩子の心は暖かくなり、自己肯定感が高まって仕事にも精が出た。
ある日、彩子は病院に配達された郵便物の仕分けを行っていた。請求書や領収書、営業のダイレクトメール、協会からの案内など配達された大量の郵便物を各担当者に渡すために振り分けるのも彩子の仕事の一つだった。個人から届いた手紙は個別に宛先がなければ彩子が中身を確認することになっているのだが、その日届いた手紙の一つに気になるものを見つけた。
そちらの病院で出産し、子供が成長するに連れ私にも夫にも似ていません。もしや取り違えをされたのではないかと不安です。近いうちに直接ご相談に参ります。私としてもできるだけ事を荒立てたくありません。私の子を返してくれさえすれば何も言いません。そちらが事実を認めないのであれば法的措置も検討しております。何卒、社会的な判断をお願い致します。
端的に書かれたその手紙は酷く不気味で、彩子は全身の血液が冷えるような感覚に陥った。
『絆のリボン』
彩子の看護婦人生の中でこのような手紙が届いたのは初めてだった。封筒の裏面に書かれている差出人の西野は確かに半年ほど前この病院で出産した女性で、担当したのは彩子自身である。
西野は安産で、産まれた赤ん坊を幸せそうに抱いて退院した時には彩子と笑って挨拶を交わして別れた。だからこそ、まさかこんな手紙を送られるとは夢にも思っていなかった。手紙の最後に書かれている『法的措置』とは、裁判を起こす覚悟があると示唆しているのだろう。
この病院では医療ミスはもちろん、裁判に発展するほどのトラブルは起こったことがない。
手紙を持った彩子の手は大きく震え出し、思考は悪い方へと広がっていく。彩子の脳裏には数年前に発生した事件が浮かんだ。
都会にある大きな産婦人科医院で何年も前に取り違えが起こっていた事が発覚し、取り違えられていた子供たちはすでに成人していたというニュースが大々的に報道された。一時期は毎日のように報道されていたため、彩子の病院利用者からも取り違えは本当に起こらないのかと毎日のように尋ねられていたのである。
母親にしてみれば、自分がお腹を痛めて産んだ子が知らないうちに取り違えられ、それを何十年経過して初めて知るという恐怖や不安が襲ってくるのも不思議ではない。産まれたばかりの赤ん坊は性別がどうであれ、顔つきは似ているため、取り違えられていたとしてもはっきりとそれを指摘することは実の親でも難しいだろう。
産婦人科医院では当然ながら取り違えを行わないような工夫を行っている。彩子の勤める病院では、赤ん坊が産まれると、産湯につけてすぐ結束バンドのように簡単に取り外しが出来ない個人識別のためのタグを取り付けている。
他にも、取り違えを犯さないような対策をいくつか取っていたが、より不安を解消させる義務があると考えた彩子が発案し、誕生したのが『絆のリボン』だった。これは病院側が用意した綿生地でできた特製のリボンに、母親や家族が思い思いにメッセージを書き、それを新生児の足に巻き、赤ん坊はそのリボンを着けたまま退院するのが普通の事になっていた。
おまじないみたいなものではあるが、母親たちには喜ばれていることから現在でも続けられている『絆のリボン』は子供が誕生した時の記念品として、へその緒と一緒に大切に保管している家庭が多いようだ。時折届く手紙にも『絆のリボン』のことが書かれていることが多く、考案者の彩子も嬉しい気持ちでいっぱいになるのだった。
心強い味方
これほどまでに取り違えに対して細心の注意を払っていた彩子だったために、西野から届いた手紙の内容には愕然とするばかりであった。冷や汗をかき、頭の中が真っ白になるのを感じながら彩子は手紙を何度も何度も読み返していたのだが、直筆で書かれたその文面には筆跡から戸惑いや不安、そして怒りが滲み出ている。
もし彩子がこの場で手紙のことを騒ぎ立てれば病院関係者の間に流れる不穏な雰囲気が利用者にも伝わってしまい、結果的にあらぬ誤解を生む可能性もあるだろう。どう対処すべきか困り果てた彩子は、少し離れた場所で仕事をしていた婦長を見つめた。
婦長の高橋は産婦人科に勤めて40年という大ベテランである。この病院以外でも勤務した経験があり、彩子の何十倍も現場に立ち、多くの出来事を体験した実績があるため、トラブルが起こる度に相談を持ちかけられるほど病院にとって心強い存在だった。
彩子の視線に気付いた婦長は即座に彩子の異変を察知して何気なく立ち上がり、それとなく他の看護婦がいない部屋へと誘導する。別室で周囲に誰もいないことを確認した婦長は彩子の顔を心配そうに覗き込み、ゆっくり尋ねた。
「彩子ちゃん、どうしたの? そのお手紙が原因?」
彩子は震える手で持っていた手紙を差し出すと、婦長はそれを読んで静かに驚いた顔をしたが、何度か読み直し不意に遠い目をしたと思ったが、封筒に書かれている差出人の名前を改めると真剣な顔で頷いた。
「まずはこの方のカルテや、入院期間中の日報を確認して、出産後から退院までのことを調べてみましょう」
婦長の言葉に対して曖昧に頷くことしか出来なかった彩子の冷たく震える手を、婦長は両手でしっかりと握って、安心させようとした。
「大丈夫。きちんと調査をして、事実を確かめましょう。もしも本当に取り違えがあったら真摯に謝罪をすればこの方だって許してくれるわ。お手紙にもそう書いてあったでしょう?」
彩子は握られた手が暖かくなるのを感じると同時に、緊張が少しずつ解けていくのがわかった。そして、ここで震えてばかりでは何の解決にもならない、しっかりと事実を追求しなければ、という使命感を覚え、婦長に向き直った。
「そうですね、まずはきちんと調べてみます」
今度ははっきりと返事をして婦長の手を握り返すと、婦長も安心した表情で頷き返した。
「他の人の耳に入れると騒ぎになってしまうから、医院長先生のお耳にだけこっそり入れておくわ。今ちょうど書類を届けるところだったの」
「医院長先生はどう思われるでしょうか? 私達の責任だとお怒りになったり……」
「医院長先生も長く勤めてる方だから、まずは調査をするように言うと思うわ。だからあなたはこっそり調べてみて」
「わかりました。よろしくお願いします」
医院長は普段は穏やかな先生として通っているが、医師と看護婦の間に明確な線引きをしており、働いている側からすればプライドが高く気難しい人物として認識していた。そんな医院長にこんな不祥事を報告するとなれば、どのような反応をされるかわかったものではないと彩子は怯えたが、婦長は心配いらないというように心強い笑顔を見せた。
あの日の真実とは
話し合いが終了すると、先に婦長が詰所に戻り、少し遅れて彩子も戻った。彩子が詰所に入ろうとした時、詰所を出ていく婦長とすれ違ったが、婦長は動じず『これから医院長先生のお部屋に行ってくるわ』と声を掛けて行った。
手紙の送り主である西野涼子のことは彩子もよく覚えており、西野が入院していた時の記録はすぐに発見することが出来たのだが、内容は至って普通のことばかりである。出産時には医院長と婦長、そして同僚の看護婦と彩子の4人で立ち会っており、予定日ちょうどに3200gの女の子が産まれていると記録されていた。西野は産後の肥立ちも良好で、母子ともに健康という理想的な状態で退院していったというところで記録は終わっている。
彩子はそれを読みながらふと、一度も西野の夫が病院に来なかったことを思い出した。仕事が多忙であったり、家庭の事情で父親がいないという利用者は多数いるが、西野の夫は入院の手続き時に一度来たきりで、それ以来退院するまで一度も顔を見せたことはなかった。
家庭にはそれぞれ事情があり看護婦がそれを話題にするのはご法度であることから、彩子が自分から西野の夫について尋ねることはなかったのだが、西野自身は時折寂しそうな表情でぼんやりしていることが度々あったことを思い出した。彩子はそんなことを思い出しながらカルテと日報を一通り読み終えたが、別段変わったことは起きていなかった。
産婦人科での取り違えが起こるのは大抵新生児室であるが、彩子の病院では個人識別タグだけでなく、『絆のリボン』もある上、ベビー服は各家庭で用意したものに名札を付けた状態で新生児室に寝かせている。
新生児室は施錠されておらず、入ろうと思えば誰でも入ることが可能であり、外部の人間が『絆のリボン』や名札付きの服を別の子と取り替えてしまうのは難しいことではないだろう。
しかし、新生児室は看護婦の詰所前を通らなければ入ることはできず、夜間は消灯しているため明かりが少しでも点けば、当直の者がすぐに気付くはずである。
しかしながら、一つの可能性としては、病院関係者が取り違えてしまったとしか考えようがないのだが、出産から退院までの一週間で当直を行ったのは彩子と、西野の出産に立ち会った同期の看護婦、婦長、彩子の後輩看護婦だが、いつも通り見回りを行い、いつも通り注意しながら世話をしていただけで、取り違えが起こる要素はひとつも思いつかなかった。
医院長の判断
婦長が詰所に戻り、医院長室にある植木鉢の移動を頼まれたから手伝ってほしいと彩子に話し掛けた。彩子はすぐに自分が医院長に呼ばれていることを察して立ち上がった。二人で廊下を歩いている最中、婦長が小声で彩子に尋ねた。
「カルテと日報は調べられた?」
「はい。西野さんのことは私もよく覚えていたのですぐに見つかりました。でも、やっぱり特に問題は見られないんです……」
「そう……医院長先生もそんなはずはないって言って、あなたを呼ぶようにおっしゃったの」
彩子は生きた心地がしないまま婦長と共に医院長室に入ると、牛皮張りの椅子に腰掛けた医院長が西野からの手紙に目を通していた。
「ああ、今田君。……早速だがこの手紙は君と婦長以外誰にも見せていないね?」
「はい……、その通りです」
「それで、この患者の担当者は君だったね。本当に取り違えは起こっていないと断言できるかね?」
「断言できます」
彩子がそう話すのにはあらぬ疑いから逃れたいという気持ちも当然あったが、それ以上に、これまで彩子が強く責任感を持って仕事に当たっていたという自負もあった。小さなミスはあるものの、大切な赤ん坊を取り違えてしまうというような過ちは起こしていないと自分で信じたかった。彩子がはっきりとそう答えると、医院長は婦長を見て目配せをした。
「彼女の言葉は信用できるのか?」
「ええ。私は彼女と長年働いていますが、そのような失敗をするような子ではありません」
婦長もきっぱりと断言してくれたことが今の彩子にはとても嬉しく、心強いものとなった。
それを聞いた医院長は納得したように数度頷いた。
「そうか……しかしこうして手紙を寄越されては困ったものだ。時折こんなこともあるものだが……」
「と、言いますと?」
医院長の言葉に理解が追い付かなかった彩子は、ゆっくりと尋ねた。
「医者をやっていると思い込みの激しい患者に出会うことがよくあるんだよ。特に産婦人科はデリケートな事情が多いからね……。ほら、前に都会の方で赤ん坊が取り違えられたという事があったじゃないか。あの時も自分の子供も違うのではないかと言ってきた患者が何人かいたよ」
「その時はどうされたのですか?」
「知り合いの科学研究所で遺伝子検査を依頼してもらったが、結果として誰も取り違えてはいなかった。だから今更こんな事が起こるとは私も思っていなかったものでね」
医院長は持っていた手紙を机に置くと深い溜め息を吐いて彩子と婦長を見比べるように眺めた。
「今回もきっと育児に不安があってそういう考えになってしまったのかもしれない。もしも直接病院に来ることがあったら遺伝子検査をしてもらうように伝えてくれ」
「わかりました」
彩子の代わりに婦長が返事をすると、医院長はさっさと部屋を後にした。残された二人も医院長室を出て、誰もいない廊下をゆっくり歩きながら、もしも西野が病院へ訪れた場合には遺伝子検査を勧めるということで落ち着いた。
突然の来訪
医院長に例の件を相談してからしばらくは何事もなく日々が過ぎていったが、事件は手紙が届いて一ヶ月ほど経過した頃に起こった。勤務中の彩子が診察受付の方が騒がしい事に気付いて見に行くと、受付にはあの西野が居た。
「早く医院長を出しなさいよ!でなければこの病院の悪事を全部ここで話すわよ!」
西野は看護婦が宥めるのも、ヒステリックに叫んでいる。そして呆然と立ち尽くす彩子の姿を見つけると、食いつくような勢いで近寄り、血走った眼で睨みつけた。
「アンタ!担当だったのはアンタでしょう!手紙を無視して!アンタのせいで夫もいなくなったのよ!」
話すというよりも叫ぶに近い言葉は支離滅裂で、他の病院利用者はその場から離れたり、遠巻きに見ていたりするだけで、その内容までは入ってこないようだった。
彩子は騒ぐ西野をどうにか別室へ連れて行き、落ち着かせるためにお茶を淹れようとしたのだが、彩子がその場から逃げると思ったのか西野は服を強く掴んで離さない。彩子は西野の隣に座り、西野は服にシワが出来るほど掴んだまま一方的に捲し立てた。
「産まれた時に女の子だと言われた時におかしいと思ったのよ!お腹にいる頃の検査では男の子だと言われていたんだから取り違えたに決まってる!性別が変わる注射をこっそり打ったの?それとも薬?私が男の子を産めなかったから夫は私を捨てていったのよ!私の赤ちゃんを返してよ!」
最後の方は泣き叫ぶような声で、彩子はただ唖然とするばかりだった。
取り違えは可能性としてゼロではないにしても、子供の性別を変える薬というのは常識的に考えても有り得ない。薬や注射を患者に気付かれず投与するということも無理な話であろうことは誰が聞いても分かるはずだ。その上、西野の夫が家を出ていったということまでも病院側の責任されるのは、彩子は返事を考えることもできなくなっていた。そんな彩子の態度に、西野は激昂し、散々罵倒して部屋を出ようとした。
「あんたじゃ話にならないから医者か婦長を出しなさいよ!」
「西野さん止めて下さい!そこまでおっしゃるのであれば遺伝子検査を行いましょう!」
彩子の言葉に西野は勝ち誇ったような顔で笑った。
「本当にいいのね? 検査をすれば私はこのことを世間発表するわよ?」
「ええ、それであなたの気が済むなら……」
思わず言ってしまった挑戦的な言葉に、西のは彩子の手を払ってこう続けた。
「母親は自分の子かどうかなんてすぐに分かるのよ!あの子は私の子じゃない!入院中に優しくしてくれたから穏便に済まそうと思ってたのに、そっちがそういう態度ならせいぜいニュースになるのを待っていなさい!」
すっかり取り違えは事実であるということが決まっているような口調の西野は捨て台詞を吐き、喚き散らしながらそのまま病院を出ていった。
部屋に残された彩子はしばらく放心したのちに立ち上がったが、酷い目眩がしたため、同僚に断って仮眠室で休むことにした。薄暗く、静かな場所で横になるとようやく安心できたのか、彩子は1時間ほど眠ってしまった。起き上がって詰所に戻ってみると、外出で不在だった婦長が彩子に気付いて心配そうな顔で駆け寄って来た。
「彩子ちゃん、大丈夫だった?話は聞いたわ。私が居たらよかったのにタイミングが悪かったわね」
「ええ……でも西野さんは遺伝子検査を受けると言ってお帰りになりました」
「そう。それと、他の子たちから聞いたのだけど、西野さんの様子がおかしかったって本当?」
「そうですね、とても取り乱していて。どうやら旦那様が家を出てしまったそうで、それはお子さんが女の子だったからだと言っていました」
「そういうことね。まぁ、絶対にこの性別がいいって言う方はたまにいるわ。でも、そればっかりは私達にはどうしようもないものね……」
婦長はこれまで多くの患者や妊婦を見てきた人物であるため、こういったケースにも立ち会ったことがあるのだろう。
「ひとまず、西野さんが検査をして、結果が本当の親子だって出るのを待つだけね」
「本当の親子だと証明されたら西野さんは納得してくれるでしょうか?」
「してもらわなければ……別の病院を紹介するしかないわね」
別の病院というのが精神の治療を行う病院であることを彩子は察した。出産や育児には大きなストレスが生じる上、西野は旦那にも見放されたようで、心が不安定になってしまったのかと思うと、彩子はやるせない気持ちになった。
遺伝子検査が決まってからしばらくしたある日、西野が子供を抱いて病院に現れた。受付の看護婦は西野の顔を見て驚いたが、今回は落ち着いた態度で彩子に会いたいと申し出たため、看護婦は言われた通り彩子に伝えた。
それを聞いた彩子は婦長にも報告し、二人で西野の待つ部屋に向かったが、西野の姿に彩子は息を呑んで驚いた。
体は細く、化粧をしていない顔はやつれて頬がこけており、パサパサになった髪には白髪も増え、先日会った時よりかなり老け込んでしまっている。部屋に入った彩子と婦長を生気のない眼で一瞥した西野は、鞄から書類を取り出して見せた。
それは遺伝子検査の結果で、西野とその子供は100%親子関係にあると書かれていた。それを見た彩子は取り違えの事実が無いことが分かりホッとしたが、西野は黙ったままだった。
彩子の記憶にある西野は元々優しい人物で、入院中は産まれてくる子供に希望を持ちながら、どんなことをして遊ぶだとか、小学生になったらどんな習い事をさせたいだとか楽しそうに話してくれていた姿だ。彩子は呆然と俯いた西野に何と声をかければ良いのか迷っていたが、婦長は西野にしっかり向き合って優しい声で話し始めた。
「あなたの気持ちは痛い程わかるわ……けれど、この子はせっかくあなたの元へ来てくれたのだから、きちんと向き合いましょう?」
その言葉を無表情で聞いていた西野は連れてきた子供を椅子に寝かせたまま立ち上がり、ふらふらと婦長の前に立ち感情のない眼を向けた。
「あなたに何が分かるのよ……」
吐き捨てるように呟いた西野はそのまま部屋を出てしまった。彩子が急いで子供を抱き上げて追いかけたが、西野はそのままフラフラと歩き続けた。
「その子は差し上げます。私には必要ありませんから……」
「何を言ってるんですか!」
彩子は無理矢理にでも子供を渡そうとしたが、西野の手はその子を抱こうとはしなかった。
「どうしてもと仰るのなら、その子を男の子にしてくれたら取りに来ますから……」
そう言い残すと、西野はまたフラフラと歩きながら病院の扉をゆっくりと開けて、西日中に消えていった。
婦長は彩子に帰宅するよう促したが、その日は当直だったので無理を言って仕事を続けさせてもらうことにした。家に帰って一人で居ると色々なことを考えてしまいそうなので仕事をしていた方がいいという理由と、できれば今日は一人ではいたくなかった。
不穏な夜
婦長の指示で当直の仕事だけ行うことになった彩子だったが、一緒に当直になるはずの同僚がいつまでも現れなかった。無断欠勤するような人ではないため、何かトラブルが起こったのかと心配していると詰所の電話が鳴り響いた。
驚きながらも電話を取ると、到着を待っていた同僚の声がして、出勤中事故に遭ったことを知らされた。幸い命に別状はないようだが、必然的に彩子一人の宿直となった。応援を呼ぼうかとも考えたが、今日に限っては色々なことがあったので、疲れているであろう婦長や別の看護婦を呼びつけるのは気が引けてしまった。
当直は原則二人で行わなければならないのは彩子も重々承知していたが、今日出産予定の妊婦は居ないし、何か問題が発生すれば近所に医院長や婦長が住んでいるため、対応が遅れることもないだろうと思った。
仕事に慣れている彩子にとって、一人で当直を行うことに大きな問題は無かった。日付が変わる時間になり定時巡回を始めたが、入院している患者はもちろん、新生児室にいる赤ん坊たちもぐっすり眠っており、昼間の出来事が嘘だったかの様な静寂が広がっていた。
巡回が終わって詰所に戻った彩子は、昼間の疲れが取り切れていなかったのか、机に突っ伏してうたた寝をしてしまった。どのくらい時間が経ったのか、何か気配がした気がして目を開けた。
ぼやけた彩子の視界に飛び込んできたのは、誰かが新生児室に入っていく様子だった。
時々夜中に目が覚めてしまった母親が、病室を抜け出して新生児室に来ることがあるが、今見えた影に対して彩子は直感的に西野だと思った。西野が別の赤ちゃんを自分の子供だと言って連れて行こうとしているのかもしれない。そんな不気味な考えが浮かんだ彩子は物音を立てないようにそっと新生児室に向かい、入り口付近で様子を窺ってみた。
もし、入院中の母親だった場合、自分の子供が寝ている場所を知っているので真っ直ぐにそこへ向かうため、他の子供を選別するようにゆっくりと見回ることもしないはずだ。それが、新生児室にいる人影は、ふらふらと歩き回っている。その姿にゾッとした彩子は一人で立ち向かっては危険が伴うかもしれないと思い立ち、まずは警察に通報することにした。
詰所に戻った彩子は電話の子機を持って看護婦用の更衣室へと入り、最寄りの警察署へ掛ける。不審者に声が聞こえないよう小声で通報し、警察の到着を待った。彩子は警察が来るまで更衣室でやり過ごそうとしたのだが、もし不審者が新生児室で何かしていたらと思い立ち上がった。
新生児室や入院フロアは病院の2階にあるため、まずは不審者を2階から降ろさないよう、階段の前で待ち伏せることにしようと考えたのだが、相手が分からない恐怖があったのも事実だ。ただ、彩子が不審者のを刺激しなければ、相手も油断して向かってくることはないだろう。
そう踏んだ彩子は、早速巡回確認用の書類を挟んでいるボードと懐中電灯を持ち、階段前に向かい、書類を明かりで照らしながらその場で何かを書き込んでいるふりをした。遠くから見れば誰かが立っているというだけで十分効果はあるだろう。
外でパトカーが到着したのを確認した際に時計を見ると数分しか経過していなかった。彩子は助けを求めるように急ぎ1階に降りて正面玄関の鍵を開け、病院前に停まったパトカーへ駆け寄ると警察官が2名立っていた。手短に状況を伝えて、新生児室に向かうため早足で玄関を通り抜けようとしたのだが、警察官のひとりがふと立ち止まって尋ねた。
「不審者はこの玄関を開けて侵入したのですか?」
「いえ……鍵がかかっていましたから違うと思います」
「他に侵入が可能な場所はどこですか?」
「関係者入り口が病院の裏手にあります……まさか……」
彩子が言葉を詰まらせると質問した警察官は急いで関係者入り口に向かった。侵入経路が関係者入り口であった場合、逃げ道も同じだろうと思われた。彩子と共に残った警察官に促され、2人は新生児室に向かったのだが、案の定不審者はその場に居なかった。
赤ん坊の数に問題はなく、彩子は一旦安心するが、警察は別の可能性を探っていた。
後編に続く
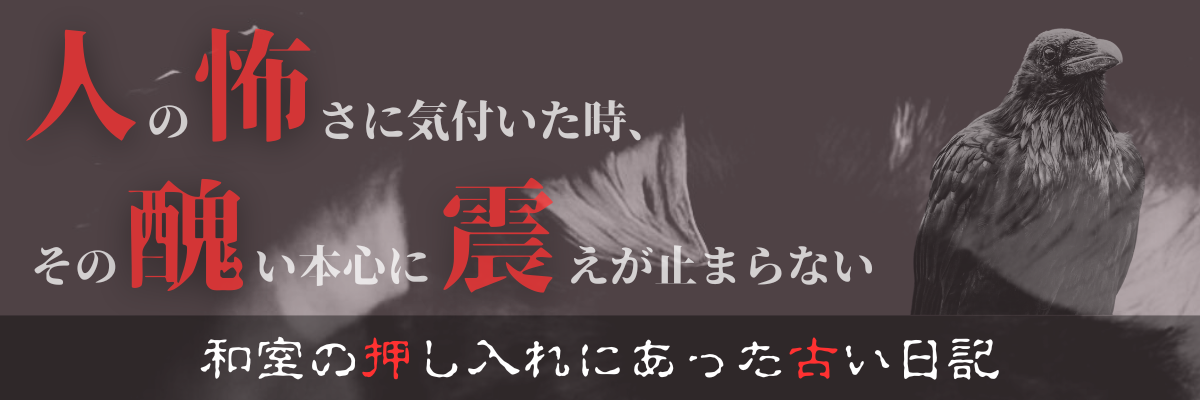




コメント