反抗期の雄太は、せっかくの家族旅行にも関わらず、帰り道の車中で『家族なんていらない』と暴言を吐き捨てた。次の日朝目覚めると、雄太の望み通り自分の目の前から家族が消えていた。1週間すると家族は家に戻ったが、自分の事を無視するつもりのようだ。
ところが、郵便受けの新聞の日付が1週間前のものであることに雄太は気づく。毎日新聞は来ていたはずなので、取り忘れたわけではない。では、いったい自分が過ごしてきた1週間は何だったのか。その真相が明らかになる時、雄太は言い知れぬ恐怖に襲われることとなる。
新聞の記事
雄太は混乱した。今日が旅行から帰った次の日だったとしたら、自分が自由を満喫していたあの1週間は過去の事だったのか?それとも未来を見ていたというのか?でも、確かに自分は1週間の時間を過ごしていたはずだ。
得体の知れない状況に自分を失いそうになりながらも、雄太は必死で考えた。そこで、雄太はとりあえず今日の新聞を見てみようと思った。旅行から帰った日とその次の日のタイミングで何か起きているとしたら、新聞には何か書いてあるかもしれない。そう思ったからだ。
公園のすぐそばまで来ていたが、自宅へと引き返して郵便受けから新聞を抜き取って自室に入った。寝ているらしい家族はまだ誰も起きていなかった。

新聞には芸能人の結婚記事を始め、政治家の汚職事件や夏祭りの様子など、全国的な出来事が多く掲載されており、雄太が知りたい情報とは思えなかったが、地方独自の情報が載っているページに目をやると、雄太は自分の目を疑った。そこには次のように書かれていた。
高速道路から車転落 家族3名が死亡、1名が行方不明
お盆の連休最終日に、一家が車ごと崖から転落するという事故が起きた。事件現場は温泉街に通じる高速道路で、山の斜面を走る国道。それほど細い道路でもなく曲がりくねった道でもなかったが、高速道路から落ちたとみられる車が、山中で煙を上げているところを近隣の住民が発見し、車の中から3名の遺体が見つかった。
警察が身元を調べると、亡くなったのは新藤三郎さん、真紀子さん、小春ちゃんの3名。温泉街のホテルに宿泊したとみられるレシートから、長男の男の子も同乗していたとみられるが、現場からは発見されず、警察は転落した際に車外へ投げ出されたとみられ、捜索を急いでいる。
雄太は目の前が真っ暗になった。帰ってきたと思っていた家族は死んでいるということなのか。もしそうだとしたら、自分はどうやって自宅まで帰ってきたのか。すべてが雄太には理解できずに新聞から目を離すことに躊躇していた。
様々な思いを巡らせて考えていると、新聞の記事には続きがあった。
なお、現場には不審な点がいくつか残っている。ひとつは、高速道路に設置されたガードレールには車が衝突した跡や突き破ったような跡がないこと。その場合に、車は発見された場所へ高速道路から転落したわけではない可能性も否定できない。
二つ目は、車の向きから考えて、温泉街から帰る方向とは逆方向から走っていたとみられ、ホテルのチェックアウトのレシートとつじつまが合わない。警察はこれらの状況を踏まえて、事件と事故の両面から捜査を続けている。
中学生の雄太にも想像できるのは次の結論だった。
あの日、ホテルから出た後自分たちは確かに自宅に帰ってきた。ただ、自分を置いて3人は改めて温泉街へ向かった。その途中で事故に遭って死んだ・・・。なぜ・・・。
不穏な想像が雄太の胸を強く締め付けた。それは、自分が一言だ。
『お前らなんていなくなっちまえばいいんだ!こんな家族なんかいらないんだ!』
自分で言ったはずの何気ない一言が、今は大きな責任となって雄太の上にのしかかってきた。もしかしたら、自分が散々好き勝手暴れていたことに疲れて、3人は集団自殺を図ったのではないか。だとしたら、間接的にも自分が家族を殺したという事にならないか。3人はすでに死んでいるから自分の問いかけにも答えないんじゃないか。だとしたら、今寝室で寝ている3人は・・・。
考えるだけでゾッとするようなことが、実際に今、目の前で起こっているとは雄太には信じられなかったが、誰もいない昼下がりに見た心霊写真特集で司会者が口にしていた言葉が雄太の頭の中を駆け巡った。
家族の突然の死など、大きな衝撃やストレスを受けると、残された人はある種の幻覚を見るようになります。そこにいないはずの人たちが見えたり、聞こえないはずの物音が聞こえるようになったり。だからこそ、遺族の方の心のケアが重要なんです。
まさか、そういうことだったのか。
3人は死んだ。どこかでそれを否定していたけれども、寂しさから3人の事を思い出して、自分で幻覚を作り出していたのだろうか。だから夕食も3人分を3人で食べていたし、自分がどれだけ話しかけても返事をしなかったのか。昨日帰った時にテレビを観ていた小春が自分の姿に見向きもしなかったのは、小春がすでに死んでいたから・・・?
雄太は、自分でも知らない間に涙が頬を伝っていた。あれだけ居なくなってしまえばいいと思っていた家族も、いざ本当に居なくなった途端に寂しさと悲しさが込み上げてきた。雄太は久しぶりに声をあげて泣いた。
『母さん・・・ごめん、万引きした俺の代わりにスーパーの人にあんなに頭を下げてくれたのに、俺は不貞腐れて詫びの一言も言えなかった。父さん・・・毎日父さんが必死に働いてきた金を盗んだ俺の事を必死に諭してくれていたのに。小春・・・大切にしていた人形のおもちゃを滅茶苦茶に壊して、すごく悲しそうな顔をしていた・・・』
雄太にはこれまでの後悔が走馬灯のように思い出されて、心の中で3人に詫びた。
4人掛けのベンチ
どのくらい時間が経ったのか分からないが、手にしていた新聞は涙でもうグチャグチャになっていた。少し落ち着いた雄太は、寝起きで見た寝室の家族の姿が気になっていた。
『もしこの新聞の内容が本当だとして、自分の想像が本当だとしたら、さっき寝室で見た3人は・・・まさか、幽霊なのか?』
リビングに行ってみると、いつも通り朝の支度をする父と母の姿があった。小春は洗面所で歯を磨いていた。テレビからは昨日のニュースが細切れに聞こえた気がした。台所で卵焼きを作っている母に恐る恐る声をかけた。
『母さん・・・』
震えるようなか細い声で雄太は言ったが、母はやはり反応がなかった。もう一度意を決して母に問いかけた。『母さん!ねぇ?聞こえる?』雄太はさっきよりも大きな声でそう言ったが、やはり台所の母はガスコンロのほうを向いたままだった。
父がネクタイを締めて鞄を持つと、『じゃあ、行ってくるからな』と母に声をかけた。母は『行ってらっしゃい』と応答した。雄太が父に向って『父さん!』と叫ぶが、母と同様、雄太の呼びかけには応じずに玄関のドアをバタンと閉めた。
雄太の中の不安は確信に変わりつつあった。
やはり、新聞記事は事実で、3人は死んだのだ。恐らく自分には幻覚が見えていて、過去の記憶から想像した姿なのだろう。これまで自分から『おはよう』なんて声をかけたことがなかったから、そんな記憶がないばっかりに幻覚の3人は自分に反応してくれないんだろう。
雄太は、母と小春が朝食を食べているテーブルの隅で、一人また涙をこぼした。居ても立ってもいられなくなった雄太は、何も持たずに中央公園へと走った。これ以上3人の幻覚を前に、自宅に居るのが耐えられなかったのだ。
中央公園はいつも通り木漏れ日に揺れていた。いつもはゆったりとしたベッドに感じていたベンチが、4人掛けという広さにますます孤独感を助長していた。向かいに座っている家族は、両親が子供二人を挟む形で座っており、自分との対比にさらに寂しさが込み上げた。
残暑が残る昼下がりの公園で、雄太は一人温泉旅行の事を思い出していた。
父が提案した旅行だったが、自分の万引きの件があってから母も心労が絶えなかったし、自分も落ち込んでいるだろうと父なりの気遣いだったことは、雄太も心のどこかで理解していた。それなのに、自分は塞ぎ込んでホテルで一人マンガを読み、3人が行きたがった鍾乳洞にも行かなかった。
母が記念にと手にしていたビデオカメラにも映りたくなかった。どんな顔をすればいいか分からなかったからだ。正直な話、家族旅行を楽しむ自分にムズ痒い気がしていただけだった。小春もあんなに楽しそうにしていただけなのに、うるさいと怒鳴ってしまっていた。
考えれば考えるほど、雄太の頭の中には後悔だけが渦巻いて、これからどうすればいいのか全く見当がつかなかった。行き帰りの車の運転は疲れただろうに、そのあと再度温泉街に向かった時の父の気持ちはどんなだっただろう。自分が身勝手な行動をしていたばっかりに、3人にそんなことを・・・自殺なんて事をさせてしまったのかと考えると、悔やんでも悔やみきれなかった。
向かいに座っていた家族がふと立ち上がると、父親が子供に向けてビデオカメラを向けた。レンズをのぞき込んで子供に手を振り微笑む姿が、なぜかとても愛おしく感じた。

『そうだ。ビデオカメラだ。』
雄太は閃いた。新聞の記事ではホテルのレシートについて触れてはいたが、ビデオカメラについては触れていなかったはずだ。車内になかったとしたら・・・10万分の1の確立に賭けるため、雄太はそのまま自宅へと走った。
母のビデオカメラ
自宅へ戻るとやはり誰も居なかった。雄太は改めて新聞を見返したが、母が持参したビデオカメラについては言及されていなかったのだ。だとするならば、一度自宅へ戻った時に母がどこかに置いて出たという事はないだろうか。
死の間際わざわざそんな事をするとは思えなかったが、あのビデオカメラは母が昔から大切に使っていたものだ。自分たち子供の成長をビデオに収めたい、いつか時が来たらそれを懐かしく家族で鑑賞したいと言っていたのを覚えていた。
すぐさま雄太はリビングを見回してみた。母はリビングのカウンターにものを置く癖があったから、おおよそリビングのどこかにあるのではないかと思ったからだ。キッチンの戸棚や玄関の下駄箱も開いていみたが、それらしいものは見つからなかった。そのたびに、雄太の心にあった僅かな希望の蝋燭が今にも消えようとしていた。
次に思いつく場所としては両親の寝室だ。両親の寝室はベッド以外には母の鏡台があるくらいで、他には探せる場所はクローゼットくらいしかなかった。ベッドの下やクローゼットの奥も確かめてみたが、どこにも見当たらなかった。
最後は小春の寝室だ。ここは可能性は低いと感じていた。小春はまだ小さいので、戸棚やクローゼットがあると、物をどこにしまったのか分からなくなってしまうということで、ベッド以外には人形をしまう箱だけが置いてある。それ以外には、物が置ける場所がなかったからだ。
小春の部屋にも母のビデオカメラは見当たらず、トイレや風呂場もダメもとで探してみたが、やはり見つからなかった。愕然とした雄太は自室に戻りベッドの上で泣いた。
あのビデオカメラも持って行ってしまったのか。
もしビデオカメラがあれば、幻覚ではなく現実に存在した家族の姿をもう一度見られるのではないかと思っていた。今は、それすらも叶わないのかという虚無感から、雄太は押しつぶされそうになった。
天井を仰いで、もう何もする気力も無くなった雄太は、ほとんど視点があっていない目で部屋の中を見つめていた。ふと目に入ったマンガ本の戸棚に雄太はくぎ付けになった。黒いケースに青いリボンのついたビデオカメラが視界に入ったからだ。母のビデオカメラだ。雄太はすぐさまベッドから飛び起きて戸棚へ駆け寄った。
手に取ったそれは、確かに母のビデオカメラだった。真っ暗な洞窟に閉じ込められて掘り続けた穴から、ようやく陽の光が差し込んできたような、何か救われたような感覚に雄太は囚われていた。
ケースに入っていた本体と、母が使っていた接続ケーブルを取り出すと、リビングのテレビへと繋いだ。本体のスイッチを押して確かめると、中に入っているテープは旅行に行った時のままのようだ。テレビの電源を入れて入力を切り替えた。ビデオカメラの再生ボタンを押すと、懐かしい家族の声に雄太は涙を堪えきれなかった。
母は、旅行の前日からカメラを回していた。そこには、自分と小春が寝静まった後に、旅行についての話をしているところだった。大人げなく久々の旅行にはしゃぐ母の姿が眩しかった。父が母をなだめたが、それでも小さな声で母は楽し気にどこに行きたいとか、何を食べたいとか喋っていた。
『鍾乳洞は一度行ってみたかったのよね。夏の鍾乳洞って暑いのかしら?』母が父に尋ねた。『いや、夏でも涼しいって聞いたけどな。そんなことより・・・』『そんなことって何よ?楽しみでしょ?』『確かにそうだが、今回の目的の一つは雄太の事もあるんだからな・・・』
やはり、両親は自分の事を考えていてくれたのだ。雄太はまた声を上げて泣いたので、しばらく両親が何をしゃべっているのか分からなかった。
画面にホテルのバイキングの様子が映し出された。小春はデザートばかりをよそっていた。大きな口を開けてケーキを頬張る姿は今では懐かしくどこか寂しい気がした。父は魚が苦手だったから、肉料理ばかりを取り皿に入れて、母に注意されていた。自分の両親ながら、何となく笑いが込み上げた。
自分が行かなかった鍾乳洞のシーンだ。真っ暗でほとんど何も映っていないが、時折懐中電灯の明かりが3人を照らしていた。雄太が想像していた鍾乳洞よりも画面に映る鍾乳洞は大きく、広い洞窟になっていた。鍾乳洞を出た先には滝が流れていて、父は滝の前でポーズをとった。
とうとうホテルを後にする日の朝が画面に映った。不貞腐れた自分の姿に少し嫌気がさした。
ホテルから出た後に見えた山々に母が何か言っていた。小春は窓を開けて吹き込む風に窓から手を出して父に叱られていた。
その後、例の口論の場面で、自分が3人に怒鳴っている声が流れた。こんなところまで回していたのかと考えると、少しだけ母の考えを疑いたくもなったが、よくよく考えれば、これが最後の家族の会話になってしまったなんて・・・。そう考えると、雄太はまた込み上げる涙を堪えるので必死だった。自分が罵った声が聞こえ、母がビデオカメラのスイッチを切ったところで映像が途切れた。
つい先日の出来事にも拘わらず、雄太は遠い日の思い出に浸っているような気分になった。必死で家中を探し回って疲れてはいたが、懐かしい声と懐かしい顔に、雄太は疲れた甲斐があったと一人で微笑んでいた。
しかし、そのあとに映し出された映像に雄太は戦慄を覚えることになる。
空蝉の泣き声
車の中で雄太が家族を罵った後は映像はプツッと切れたが、そのあと映し出された映像には母の顔があった。どこかにカメラを固定して録画ボタンを押したとみられ、母はしばらくすると後ずさりしていった。そして、そのあとカメラの向こうに見えた映像に雄太は背筋が凍るような感覚を覚えた。

暗い森のようなところで、車のヘッドライトを照らした先にスコップをもって一心不乱に穴を掘る父の姿が見えた。何をしているのか分からなかったが、次第に母と小春の話し声が聞こえた。
『帰ったら何を食べたい?小春の好きなシチューにしようか?』母が小春に夕飯について尋ねていた。見たこともないような形相で穴を掘る父と、いつもと変わらない口調で夕飯について語る母と小春の対比が、不気味なほどの温度差を醸し出していた。
『これで十分だろう。』
父が不意につぶやくと、車の方へ歩いていく姿が見えた。そのあと、父は何か引きずっていた。雄太はギョッとした。父が引きずっているのは間違いなく自分だった。顔にビニール袋を被せられていたが、着ている服や体格などは間違いなく自分だった事と、父が『雄太も大きくなったな』と吐き捨てたことからそう思った。
手足はロープで縛られていた。顔は見えなかったが、何かを叫んでいる自分の声がくぐもっていたので、恐らくガムテープなどで口を塞がれているのではないかと思った。『この映像はどっきりか?どういうことなんだ?』先ほどまで家族の姿に懐かしさや愛おしさを感じていた雄太は、今テレビに映し出された映像に現実味を感じることが出来なかった。
穴の近くまで自分と思われる体を引きずってきた父は、穴の中を改めて確認して、その中にまるでゴミを捨てるように自分を放り投げた。ドサッとという音と、何か呻いている自分の声のようなものが微かに聞こえた。
雄太を戦慄で包んだのはそのあとに続いた家族の会話だった。
『ははははははははっ!!!やっと捨てられた!本当に嫌だったわ!』母の声だった。
『散々迷惑かけといて自分の気分で暴れて、こっちの気持ちを考えたことあるのかしら?もうその格好だと、自由も糞もないかもね!ははははははっ!!!』キチガイじみた母の高笑いが静かな山の中に響いていた。
『いっつもお兄ちゃんは物を投げてきて、小春に当たった時もごめんなさいしてくれなかったよね!?』小春はそう言いながら、近くにあった石や木の枝を、穴の中に捨てられた自分目掛けて投げつけていた。
『自分の財布の金額くらい覚えてるもんだがな。お前が盗んでるのを気づいてないとでも思ったのか?万引きも気づかなければいいだって?笑わせるなよ!お望み通り、お前も気づかないうちに縛り上げてやったよ!』父はそう言いながら穴の中に土を戻し始めた。
『ははははははは!ははは!はははははははっ!・・・』
3人が穴の中に捨てられた自分に対して蔑んだ表情でケラケラと笑っている声が響いた。
『ははははははは!ははは!はははははははっ!・・・』
まだ3人はケラケラと笑っている。
ただ、先ほどと違ってその声は雄太の後ろから聞こえる気がした。もう雄太には何が何だか分からなかったが、恐る恐るテレビの電源を切ると、真っ暗になったテレビの画面に自分の後ろに立つ家族の姿が見えた。
振り返った雄太の目に映ったのは、目を剝いてケラケラと嗤う3人の姿だった。母が最初に口を開いた。
『やっと気づいたの?ずいぶん時間がかかったわね。だから言ったでしょ?言葉は現実になるのよって。だから暴れるあなたに何度も忠告したのに。だからね、車で寝ちゃったあなたに、自由に生活ができるように、家族の事を大切に思うようにって何度も何度も言い聞かせてたのよ。』
母の言い分はこうだ。旅行から帰った次の日から1週間の自由な日々を過ごしたのは、母が自分に言い聞かせた妄想であり、それは幻想だったのだ。新聞に書いてあった事故の件も、あくまでも雄太が家族を大切に思うように母が言い聞かせた幻想であり、居なくなったのは家族ではなく、自分の方だった。
本当の自分は、家族に殺されていた。
『ずいぶん楽しそうな顔をしていたけど、何かおかしいと思わなかった?お腹空かなかったでしょ?誰とも話をしていないでしょ?それはね、あなたが死んでいるからよ!!はははははっ!!』
『ハァァァ、これで疎ましいあんたも居なくなって家族3人で楽しく暮らしていけるわね!ははははは!はははははは!』
家族が居なくなって泣いていた雄太は、まさに空蝉だった。空蝉の泣き声は電源を切ったテレビのようにプツっと途切れてなくなった。
雄太の家族は、反抗期の雄太の暴力や暴言、身勝手な行動に限界を超えて、旅行の帰りに山の中に穴を掘り、その中に雄太を生き埋めにしていたのだ。
心霊写真特集の司会者はこうも言っていた。
突然亡くなった人というのは、自分が死んだということに気付かずに、それまで生活していた所を彷徨ったりすることがあります。それが心霊現象の最たる例です。しかし、自分が死んだということを自覚すると、それまでの状況が嘘のようにフワッと消えていくことがほとんどだそうです。無論、人々に愛された人は天国へ、恨まれて死んだ人は地獄へ落ちると言われていますがね。
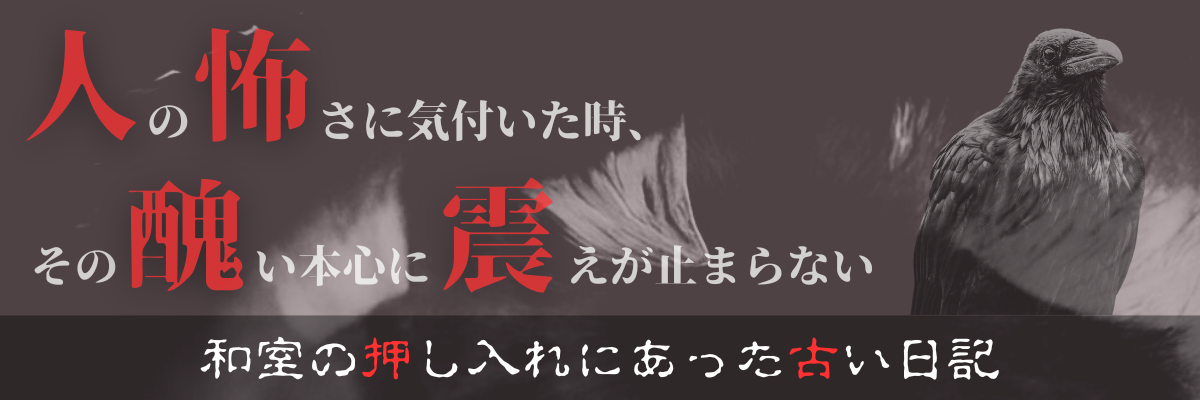




コメント