窓の外ではセミが鳴いている。ギラギラとした夏の日差しがカーテンの隙間から差し込んで、テレビゲームをしていた雄太には鬱陶しく思えた。ただ、冷房の効いた部屋で山積みの夏休みの宿題をなかったことにして、雄太は自由を手にした気分だった。
ありふれた反抗期の少年に訪れた小さな違和感。その真実を知った後、少年は後悔と得も言われぬ恐怖を体験することとなる。
理由のない破壊衝動
父の三郎は会社勤めで培った勤勉さと、長年のサラリーマン気質から雄太を強く𠮟る事は出来なかった。雄太が暴れて壊したテレビも、叱る前に新しいテレビを買うというような人だった。もちろん、子供の教育に関心がない訳ではなく、成長した雄太の暴力に対して、自分の腕力ではどうにもならないと感じていたからだ。
昔は『大きくなったらパパにお家を買ってあげるね』という雄太の言葉を嬉しく思っていたが、今ではただの金ずるとしか思われていないことを悲嘆していた。雄太が、度々三郎の財布から金を盗んでいた事は分かっていた。
最初は500円とか100円とか小銭がなくなる程度だったため大目に見ていたが、次第に札がなくなるようになってからは、財布を別に用意するようになった。もちろん小遣いも与えてはいたが、雄太の行動がエスカレートして、他所で窃盗をするよりはずっといいという甘い考えを持っていた。
一度だけ雄太に金を盗んだことを咎めたことがあったが、うまくいかなかった。
『雄太、お前父さんの財布から金を持って行ったか?必要なら言ってくれれば・・・』と言いかけたところで『うるせえよ!』と一蹴され話にならなかった。
妹の小春とは仲が良かったが、雄太が中学に上がる頃、小春はまだ小学生低学年だったため、母は小春の世話を焼くことが多くなり、雄太は自分が蔑ろにされていると感じていた。
冷静に考えれば小春の事を優先すべき状況が多い中で、雄太は自由を求める反面で自分の中の歪な感情から、母は自分の事をどうでもいいと思っていると感じていた。
小春に対しては暴力を振るう事はなかった。雄太の暴力の理由は自分の力を誇示することが目的であり、まだ小さな小春に力を示したところで意味がないと思っていた。しかし、母の愛情が小春だけに注がれていると思っていた雄太は、小春の持ち物を壊したり、小春の事を口汚く罵ったりしていた。
その度に、母の真紀子から注意を受けたが、『クソババァ!』と怒鳴っていた。
そんな雄太ではあったが、自室にいる時は随分と大人しかった。雄太は決して家族が嫌いではなかった。自分の中に込み上げてくる目に見えない破壊衝動に自分でもコントロールが効かなくなるのだ。ただ、自分が何か壊したとしても両親が元通りにしてくれるし、遊ぶ金がなければ父の財布から盗めば事足りた。
雄太は反抗期独特の揺らぎの中で、理性と堕落の狭間にいた。
バレなければいい
反抗期の雄太は、悪い友達ともつるむ様になった。
下級生から金を巻き上げたり、授業を抜け出してゲーセンに通ったりと、家庭内では収まらず外の世界でも雄太の行動はエスカレートしていった。始めこそ雄太は気が引ける部分があったが、そのうちにスリルを感じて、いつしかそれが快感になっていた。
ある日雄太は友達と万引きをした。近所の駄菓子屋でガムを1つ盗んだ。小さな個人経営の駄菓子屋で、お婆さんがレジにちょこんと座って、相撲中継を見ているような店だった。雄太は初めての万引きに大きな達成感を味わった。
『あの婆さん全然気づかなかったな!この調子なら、バレなきゃずっと続けられるぜ。』
雄太は友達とそんなことを話していた。次の日も雄太は万引きをした。今度は少し大きな板チョコを盗んだ。その日もお婆さんにはバレなかった。
2週間ほどその駄菓子屋で万引きを働いたが、雄太達は盗む事よりもそのスリルを求め始めていた。ターゲットの店を変えようという話が出るまで長い時間はかからなかった。自分たちならきっと他でも上手くやれると思っていたからだ。
『どうだろう?今度は学校の帰りにあるスーパーに行ってみようぜ。あそこなら死角がたくさんあるし、商品も多いからな。』

そんな話をしていると目的のスーパーにたどり着いた。事前に打ち合わせをして、友達がジュース2つ、雄太がお菓子の詰め合わせを盗むという予定だった。いづれも店員がいるレジからは死角になっているコーナーなので、雄太は絶対に成功すると確信していた。
雄太達はそれぞれ目的の品を自分のバッグに入れて足早に店の外に出た。雄太は心の中で『よし!』と叫んだ。しかし、次の瞬間誰かに肩をつかまれて背後から声がした。
『君、ちょっと待ってくれるかな。』
そこには警備員らしき男の人が立っていた。友達と目を合わせて一目散に走って逃げた。『待て!!!』と警備員の声が追ってきたが、全速力で走り近くの神社へと逃げ込んだ。成長期の雄太達の足は、警備員よりもずっと速かった。
『ハァ、ハァ・・・危なかったな・・・』
息を切らしながらつぶやく友達に『ああ・・・でも、うまく言ったな!・・・』と雄太は答えた。そのまま二人は盗んだお菓子とジュースで空腹を満たして、陽が落ちるころにそれぞれの家へと帰っていった。
雄太が家に戻ると母と小春がリビングでテレビを観ていた。『お帰り』と声をかけた母を無視して、雄太は自室へと閉じこもった。多少の罪悪感があったからか、雄太は母と目を合わせなかった。しばらくして自室のドアの向こうで電話が鳴った。
しばらくすると、母が自室のドアを開け叫んだ。『雄太!万引きしたって本当なの!?』
雄太は咎められた事よりも、なんでバレたのかという事の方が気になった。始めこそ抵抗したが、バレているなら仕方ないと開き直って、今日の出来事をいつものように『うるせぇな!クソババァ!』と母を罵りながら喋った。
1時間もしないうちに警察が来た。さすがに雄太も『まずい』と思った。
警察の話によると、防犯カメラに学校の鞄がしっかりと映っていたため、スーパーが学校に問い合わせたという。その後、カメラに映った二人が特定され、先に友達の家に警察が行った。友達がすべて白状したことで、雄太のところにも警察がやってきたというのだ。友達は観念したのか、駄菓子屋での万引きについても喋ってしまったようだ。
警察からは厳重注意を受け、母が品物の代金をスーパーまで持参し平謝りをした。もちろん雄太も連れていかれたが、一言も喋らずに不貞腐れていた。
父が帰宅し、何故こんな事をしたのかという事と、他には何をしたんだという事を両親から詰問された。
『駄菓子屋と今日の店だけだよ!駄菓子屋のばぁちゃんだって、友達が吐かなければ気づかなかっただろ?バレなきゃ問題なかっただろ!』と雄太は精いっぱいの虚勢で叫んだが、内心反省はしていた。ただ、今回はバレたから怒られただけで、スーパーに行かずに駄菓子屋だけでやっていたら、気づかれずに何事もなかったのではないかと、甘い考えも捨てきれなかった。
久々の家族旅行
夏休みも中盤に差し掛かりお盆を過ぎたころ、例の万引きの一件以来、自宅から出ることを禁じられた雄太は自室に閉じこもっていた。両親から言いつけられたというのもあるが、中学生の雄太には駄菓子屋とスーパーくらいが行動範囲だったため、外に出ても行く宛がないというのが正直なところだった。学校にも呼び出しをされてしまったので、ゲーセンに行く気にもなれなかった。
ある日、夕食の席で父がこう話し始めた。
『なぁ、今度の週末みんなで旅行に行かないか?』
母と小春は同調したが、雄太は黙ってテレビを観ていた。正直、今の雄太にはどっちでも良かったのだ。
家族はどこで何をしようかと話し合っていたが、雄太は興味がなかったので、食事を終えるとそのまま自室へ戻った。リビングでは家族の話し声や、時折笑い声が混じっていて、何がそんなに面白いんだと雄太には癪に障った。机にあった漫画本を力いっぱいドアに投げつけると『バンッ!』と大きな音を立てて落ちた。次の瞬間リビングの話し声は聞こえなくなった。
旅行は温泉街に行くことになった。父が運転する車で片道3時間。2泊3日のホテルを予約した。山奥にある温泉街ということで、道中は険しい山道もあったが、雄太にとっては全てがどうでもよかった。

雄太にとって一番鬱陶しかったのが、母が持参したビデオカメラだった。母は、何か行事があるとビデオカメラで撮影し、祖父母にそれを見せることが好きだったからだ。無論、雄太にカメラを向けても何も喋らないし話しかけても機嫌が悪くなるので、あまり積極的に雄太を撮ることはなかった。
唯一雄太が満足できたのは、旅行で泊まったホテルの食事だった。バイキング形式の食事だったので、好きなものを好きなだけ食べた。観光地を回るという家族の意見に雄太は興味がないと言って、ホテルで一人で居ることを選んだ。ホテルの部屋にはテレビがあったので、雄太には問題のない環境だった。
2日目の昼間、家族は近くの鍾乳洞を見に行くということで朝早くから出ていったが、相変わらず雄太はホテルの部屋でテレビを観ていた。地上波はそれほど映らなかったが、洋画特集で放映されていた『ホーム・アローン』を何となく見ていた。クリスマス休暇の設定の話は季節に合わないと思ったが、気づいたら家族が居なくなっていたという物語の設定に雄太は少し興味をそそられた。
『俺もあんな家族なんて居なくなったらいいのにな。そしたら自分の好きなように暮らせるのに。』
そんな風に妄想しながらテレビを眺めていると、その思いとは裏腹に鍾乳洞を満喫した3人が部屋に戻ってきた。夏でも鍾乳洞は涼しく、幻想的で本当に言ってよかったと口々に話す家族に、映画に対する妄想と現実の家族の鬱陶しさに苛立ちを感じていた。
最終日の朝、ホテルのチェックアウトを済ませると、父が運転する車に乗り帰路へついた。
午後の日差しにうなだれながら、高速を走る車の後部座席で雄太は自宅から持ってきたマンガ本を読んでいた。『せっかく旅行に来たのにマンガ本なんて』と母が言うと、『うるせえな!』と雄太は怒鳴った。楽しかった旅行の帰りにカリカリするなと宥める父の言葉に、雄太の中で何かが爆発した。
『もう本当に鬱陶しい!なんなんだよお前ら!旅行が楽しかったのはお前らだけだろ!?俺は何も楽しくなかった!お前らなんて居なくなっちまえばいいんだ!こんな家族なんか要らないんだ!』
怒鳴る雄太に、母が静かに咎めた。『そんなこと言わないで。言葉は現実になるんだから。そんなこと悲しいじゃない。』感情を感じない棒読みのような言い方に少し雄太は違和感を感じたが、それでも雄太は自分の感情を爆発させた。
両親も黙って、小春も後部座席で小さくなっていた。シーンとし車内では交通情報を知らせるラジオだけが流れていた。雄太はひとしきり叫んだので次第に眠くなってきて、2つ目のパーキングエリアを出たくらいで眠ってしまった。
手に入れたはずの自由
雄太が目が覚めたころにはすでに自宅にいた。窓の外にはセミが鳴いていて、真夏の夜の鬱陶しさが漂っていた。雄太はホテルから帰ったままの服装でベッドに寝ていたが、時計を見るともう夜中の2時を回っていたので、そのまま朝まで眠ることにした。
次に目覚めると、すでに時計は10時を回っていた。よく寝たなと思った雄太だが、少し違和感を感じた。それは、いつもならリビングから聞こえるテレビの音がなかったからだ。正直どうでもよかったが、腹が減っていたので自室から出てリビングへ向かった。

『あれ?おーい』
雄太がリビングに行くと、そこには家族の姿がなく、壁にかけた時計の秒針の音が聞こえるほどに静かだった。とりあえずテレビをつけて冷蔵庫を開けると、食パンを取り出して牛乳をコップに注いだ。テレビから流れる天気予報に耳を傾けると、確かに昨日ホテルから帰ったはずの日付だった。
『なんだ?夢なのか?現実なのか?なんで誰もいないんだ?』
雄太はボーっとしながら考えを巡らせたが、とりあえず昼過ぎまでリビングでテレビを観ることにした。いつもなら母がワイドショーを観ていて見られない心霊写真特集を雄太は堪能した。作りものなのか本当に怨念が込められているのか、嘘なのか本当なのか分からないが、そんなことよりも雄太は自分の興味が画面に引き込まれていく感覚のほうが大事だった。
午後になっても家の中はガランとしていた。父は仕事に行っているはずだから夜には帰るだろうが、母と小春はどこへ行ったのだろうか?祖父母の家に行ったのか、買い物にでも行っているのか。いづれにせよ、自分だけが家に残されている状況は初めてではなかったので、雄太としては久々に静かな一人の時間を楽しむことにした。
窓から見える信号機の影が夕日で長く伸びたころ、雄太は昼寝から目覚めた。まだ家の中には自分しかいない。暇を持て余していたので両親の寝室や小春の部屋を覗いてみたが、やっぱり誰も居なかった。まぁいいか。どうせ夜になったら、またあの煩わしいやつらが帰ってきてしまう。その前に一人の時間を楽しもうじゃないか。雄太はそう思った。
時計の針はそろそろ20時を回るところだったが、それでも家族が誰も帰ってこなかった。
さすがの雄太も異変に気付いた。『今日はどこかへ行く予定だったかな?でも俺に何も言わずに出ていくなんてふざけた家族だな。』今まで散々好き勝手やってきておきながら、雄太は自分の事を蔑ろにしている家族に対しての不満を感じた。
22時を回るころ、いよいよ全く帰ってくる気配のない家族に対して、何が起きているのか考えた。雄太の記憶で最後の家族の姿は、喚き散らした高速道路での一件だ。そう考えてみると、2つの出来事が雄太の頭の中でつながった。
『そんなこと言わないで。言葉は現実になるんだから。そんなこと悲しいじゃない。』という感情のない母の言葉と、ホテルで観た『ホーム・アローン』だ。もしかしたら、俺が強く思ったから家族が消えたのか?半分バカげていると思いながらも、今日一日の状況を考えると、無くもないのかもなと思った。とりあえず、明日の朝起きて家族が居なかったら、それは自分の想いが現実になったんだということにしようと、雄太は自室のベッドに体を投げ出した。
次の日の朝、父が仕事に出る8時半よりも早く8時前にはリビングに行ってみた雄太だったが、やはりリビングには誰も居なかった。昨日の朝と同じように時計の秒針の音だけが響いて、家の中には誰もいないということを雄太に知らせていた。
雄太は、にわかには信じられない状況ではあるが、家族の存在を疎ましく思っていた自分にとっては好都合であるこの状況に、勝ち誇った様子で笑った。
『俺の想いが届いたんだ!俺は今日から誰にも縛られることなく生きていけるんだ!』
雄太は心の中で叫んだ。まだ朝の8時過ぎだ。これから好きなように1日を過ごそう。雄太はそう決めるとまずはシャワーを浴びて身支度を整えた。以前からやってみたかったのは、町の公園でマンガを読み耽ってみたいと思っていた。学校の遠足で持って行ったリュックサックに、詰められるだけのマンガ本を詰めて、雄太は颯爽と自宅を後にした。
中学生の雄太には、夏休みに自分の好きなだけ好きなように行動できることが、無限の自由を手に入れたように思えた。それは、目に見えるもの耳に聞こえる全ても、それまでとは違って自分に味方してくれているように感じた。
公園に行くまでの道すがら、例の万引きをした駄菓子屋が目に入った。店はいつも通り入り口が開いていたが、中には人の様子はなかった。あんなことがあってから行こうとも思えなかったが、今の雄太にとっては自分の自由と過去の成功体験を象徴するものに思えた。

目指していた中央公園は比較的大きな公園で、春になると桜のアーチができる地元でも有名な場所だった。公園の中央には噴水があり、夜はライトアップされるためカップルのデートスポットとしても好んで利用されていた。
雄太が気に入っていたのは公園内のベンチで、植えられた木々がちょうどよく日向と日陰を作るので、夏でも涼しく、春や秋は日差しが心地よい絶好の場所だった。今日は赤ん坊を連れた近所の奥さん連中がいるくらいで、人も少ないので雄太はさらに気分が良かった。
それにしても、夏でも早い時間だとこれほどまでに風が気持ちいいとは思わなかった。だいたいお昼前くらいに起きて食事を摂って、夕飯前まで自室に籠るような生活をしていた雄太にとっては、これから待ち受ける自分だけの自由な生活にとって、新たな発見だと思われた。
大きな4人掛けのベンチは、成長期の雄太でもゆったりと寝そべることが出来るだけの大きさはあった。ベンチの足の部分は鉄でできており、洋風の装飾が施されている。足と背中が当たる部分は木製になっており、程よく軋んでベッド代わりにはちょうどよかった。雄太はリュックサックからマンガ本を取り出すと、残った本をリュックサックの中に入れ、枕代わりにしてベンチへ寝ころんだ。
日が高くなり始めたころ、雄太は一冊マンガ本を読み終えていた。
少し昼寝をしようと決め込んだのは、マンガ本に飽きたからではない。心地よい風と暖かい太陽の光を存分に楽しみたいと思った雄太の新たな挑戦だった。
うつらうつらしている中で、木々の葉っぱが風に吹かれる音や、小鳥のさえずり、遠くで聞こえる大通りの車の音などが雄太の耳に入った。いつもは自室のテレビとたまに来る訪問販売の玄関の呼び鈴の音くらいしか意識していなかったから、新鮮な感覚を覚えていた。
気づいたころにはもう夕陽が噴水に反射していた。雄太はずいぶんと寝てしまったという後悔を強く感じた。残りのマンガ本は明日また読めばいいかと思い、雄太はリュックサックを背負うと自宅へと足を向けた。
違和感と家族の行方
それからというもの、気ままな生活を続けていた雄太だったが、さすがに1週間も経つとおかしいと思い始めた。家族が未だに帰ってこないのだ。どこかへ出かけているとしても、子供を自宅に残して1週間も戻らない親がいるだろうか。自分の両親については、反発こそしていたものの、比較的まともな親だと思っていたので今回のこの状況については信じがたいことだった。
自由を手に入れたと思っていた雄太だったが、まだ中学生ということもあり、さすがに不安のほうが大きくなってきたのは事実だった。もしもこのまま家族が帰らないとしたら。そう考えると、どれだけ反抗期と言えども落ち着いては居られなかった。
漠然とした不安を抱えながらいつものように眠りについたが、次の日の朝起きてみると、雄太の不安は苛立ちに代わっていた。そこには仕事の支度をする父、朝食を食べる母と小春の姿があったのだ。何も言わずに帰ってきたのかと腹が立った雄太は、『何も言えないのかよ!俺だけ残してどこに行ってたんだよ!』といつものように怒鳴った。一瞬3人の動きが止まったように思えたが、雄太の怒りに反応することなく、そのまま時間が過ぎていった。
むしゃくしゃした雄太は、最近のお気に入りだった中央公園に出かけるためリュックサックをもって家を飛び出した。
『何なんだあいつら。俺には声を掛けずに出ていったくせに!帰ってきたと思ったらそれでも一声かける事もしないなんて!やっぱりあんな家族いないほうがマシだった!俺は自由に生活するんだ!』
いつものわがままな反抗期の雄太に戻っていた。
苛立ちはあったが、公園に来てしまえば雄太だけの世界だった。リュックサックに詰め込んマンガを取り出して、時々吹き出しながら読み漁った。陽が落ちかけて自宅へ帰ろうとしたが、朝のことがあるので雄太は一芝居打ってやろうと思っていた。
『今日はここで一晩過ごして心配させてやろう。1週間も俺を放っておいたんだ。1日くらい俺の事を心配する時間が必要だろう。』

雄太は自分で自分に言い聞かせるように納得して、マンガの続きを読み始めた。3冊くらい読んだところで雄太は眠りに落ちた。
気づいたころには、公園の時計は10時を回っていた。今日はこのまま夕方まで過ごして、夕飯時に家に帰ればいい。そうすれば、心配した家族が自分に対して何か言ってくるだろうと思っていた。予定通り夕方まで好きなように過ごした雄太は、陽が落ちた18時くらいに帰路についた。
玄関を開けると母は台所で夕飯の準備をして、小春はリビングでテレビを観ていた。何も言わずに自室へと向かった雄太だったが、母と小春も自分に対して何も言ってこなかった。夕食の時間になると父が仕事から帰ってきた声がした。しばらくしてリビングに降りてみると、3人で夕食をしていた。
『なんで俺には声を掛けないんだよ!』
雄太は昨日の苛立ちに輪をかけて怒鳴った。それでも平然と食事を続ける3人に雄太はピンときた。
『そういうことか。我慢比べだな!?いいさ、そうやって無視してろよ!俺はお前らなんかいなくても、1週間も一人で生活してたからな!勝手にしろよ!』
そう言って雄太は自室へと戻った。
次の日の朝、雄太は珍しく6時ごとに目が覚めた。両親も小春もそれぞれの部屋でまだ寝ている様子だった。玄関の郵便受けに挟まっていた朝刊には、芸能人が結婚したという見出しが少しだけ顔を覗かせていた。『あれ、あの芸能人少し前に結婚しなかったかな?最近の話だったかな?』雄太は何となく疑問に思ったが、正直そんなことはどうでもよかった。
雄太の頭にあったのは、自分を無視するゲームを続ける家族に対して顔を合わせるのが面倒になっていたので、家族が起きる前に公園に行ってしまおうと考えていたのだ。いつものリュックサックをもって、雄太は足早に家を出た。
その日も夕方まで帰らなかった。というよりも、朝が早かったので公園についてお昼まではマンガを読んでいたが、そのあとは昼寝をしていたらすでに辺りが夕方になっていたのだ。家には帰ったが、一言も言葉を発さずに雄太は自室のドアを閉めた。
次の日も雄太は朝早く起きた。ふと昨日と同じように目に入ってきた朝刊が、雄太に大きな疑問を投げかけた。昨日観た芸能人の結婚と同じ紙面だ。さすがに何かおかしいと思った雄太は郵便受けから朝刊を引っ張り出し、両手で広げて眺めてみた。普段新聞なんて読まない雄太だったが、一つだけ明らかにおかしい点に気付いた。日付だ。
1週間前の日付なのだ。
それはちょうど、家族が居なくなって自由を満喫し始めた最初の日の日付だ。どういうことなんだ?と思った雄太はとりあえずテレビをつけてみた。いつもは見ることのないニュースの時間帯だが、雄太が気になったのは今日が何日なのかという点だった。やはり、ニュースで伝えられる日付も新聞と同じ1週間前の日付だった。
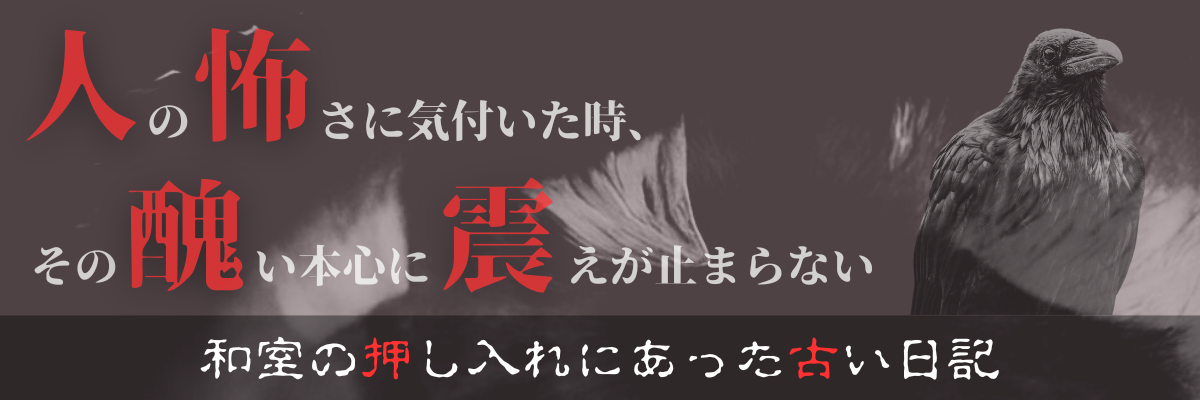




コメント