世の中にはたくさんの呪いが存在し、時には人の命さえ奪ってしまうことがある。しかし、呪いをかけられた人に一番大きな影響を与えるのが、『誰からなのか分からない』という点が、疑心暗鬼を起こして不幸を引き寄せてしまうという説があるようだ。
この話は、『誰からなのか分からない』という人の心理が引き起こした『手紙』による言葉の凶器の話である。
ルックアップレター
昭和天皇が崩御し、元号が『平成』と改称された1989年、新学期からは消費税が新たに導入されることとなった。バブル景気も終わりが見えてきたころであり、新たな税金制度の導入により、消費の冷え込みを懸念した企業は、様々な販促策を検討していた。
郵便局では、消費税の導入により、それまで30円だったハガキが41円に値上がりした。これを受けて、群馬県に本社を構える印刷会社が地元郵便局と連携し、『平成の幕開けに、誰かに感謝を伝えよう!』という謳い文句と共に『ルックアップレター』というキャンペーンを行った。

このキャンペーンは、専用のハガキを100円で購入し宛名を書かず、誰かに対して感謝や励ましのメッセージを送るというものだった。自分がいつもお世話になっている人を想像しても良いし、自分とは関りが無いような人に対してでもいい。印刷会社が用意した見本に習って、誰かに対してポジティブな手紙を出す。
その手紙は郵便局側でランダムに配送され、受け取った人は、誰からか分からないが日頃の感謝や激励を受け取ることが出来る。また、売り上げの内25円は地元群馬県に対して還元される仕組みになっており、社会貢献の意味も持つことから、郵便局では大々的に販売促進を行った。最初こそ群馬県内にとどまったが、評判が評判を呼び、瞬く間に全国規模のキャンペーンへと拡大していった。
キャンペーンの内容としては非常に評価が高かったが、商業的な観点でもよく考えられた内容だった。郵便局は正規の値段でハガキの販売が出来て、専用のポストさえ準備すれば良かった為、追加コストがない事、印刷会社は郵便局側で販売促進をしてもらえることから、純粋に100円の売上から41円のハガキ代と25円の地域還元を除いた34円が何もせずとも利益となるため、消費者に対して動機づけが出来れば極めて効率のいい商業策だった。
また、日本人に強くみられる『返報性の原理』を利用して受け取った人がまた別の誰かにルックアップレターを出すという行動予測もできたため、3年ほどルックアップレターキャンペーンは大きな盛り上がりを見せた。
【返報性の原理】
人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返しをしなければならないという感情を抱くが、こうした心理をいう。この「返報性の原理」を利用し、小さな貸しで大きな見返りを得る商業上の手法が広く利用されている。
身近な例では、試食がある。試食は本来、無料で食品を提供し、その味を客が確かめ、購買に値すると判断した場合に買ってもらうプロモーション戦略のひとつであるが、客は店員から直接食品を手渡されることによって、味が良いかに関わらず商品を買わなければいけないという気持ちになることが多い。
Wikipediaより抜粋
しかしながら、手紙の内容が一辺倒になりがちなことが欠点となり、3年もするとこのキャンペーンも徐々に衰退し、印刷会社の社長による郵便局との癒着問題も取りざたされ、消費者の前から姿を消すこととなった。
時を同じくして、滋賀県米原市で暮らす萩原 由香里(はぎわら ゆかり)は教員免許の試験に合格し、次の年から市内の公立小学校の教諭になることが決まっていた。合格が決まった年の10月から、事前の研修で数学の授業と音楽の授業に補助教員として勤めることになった。由香里は25歳で若かったが、大学を卒業してからは受験勉強とアルバイトに時間を費やしていた。生活は楽ではなかったが、なんとか食い繋いでようやく念願の教員免許を取得した。

補助教員としての業務が始まると、覚えることが多く目の回るような日々であったが、由香里は自身の希望だった教員になることが出来たため、必死で業務を覚え学校の中でも評価が高かった。特に教頭からの評価が高く、年配の女性教諭からは影口を叩かれていたほどだった。
由香里は平成2年の4月から、2年生のクラスの担任になることが決まっていた。教頭からの推薦だったが、一つだけ由香里には気になることがあった。それは、1年間の関係構築が終わった2年生の進級のタイミングでクラス替えがあった事だ。そもそも自分が新任であることに加え、生徒たちも新たな人間関係を構築する必要があるという状況は、担任としては大きな課題であると感じていた。
『どうしてこんな早いタイミングでクラス替えをするんですか?』
ある日の夕方、その日の業務を終えると由香里は教頭に尋ねた。教頭は白髪交じりではあるが短髪を綺麗にそろえた髪型をしており、年齢の割には剥げていなかった。陸上部の副顧問であることもあり、体格はがっちりとしていて、眼鏡をかけてスーツを着た姿は、高学年の生徒から『ヤクザ』と揶揄されていたくらいだった。
『元々は、3年生に進級するタイミングでクラス替えをするのが一般的なんですが、萩原先生にお願いする予定だったクラスの中でいじめの疑惑がありましてね。ある生徒が授業中に緊張してお漏らしをしたことから、それを馬鹿にした生徒がいたんです。そこから一部の生徒が面白がって茶化したことからいじめに繋がってしまって。まぁ、小学1年生の話ですから、実際に何か問題があるわけではないのですが、保護者会とも話をしてクラス替えを決定したんです。』
由香里はいじめという言葉を聞いて、少し狼狽えた。
生徒たちにとっては人生初となる集団生活。これからの人生を形成していくために非常に重要な成長段階だ。その中でいじめがあれば、学校生活はもちろん、一生のトラウマになりかねない。由香里は自身が中学生のころに苦い思い出があった。それは、自分がいじめの加害者側にいた経験があったのだ。
中学3年の夏休みが終わったころ、同じクラスの小林 智花(こばやし ともか)という生徒が、女子のリーダー的グループからいじめを受けていた。上履きを隠されたり、机に落書きをされたりというありがちないじめではあったが、智花は2か月ほど登校拒否を余儀なくされた。本来であれば一番楽しいはずの中学3年の2学期に登校拒否を選択せざるを得なかった智花の心情は計り知れない。
由香里はその時に中立的な立場ではあったものの、リーダーグループの支配力が強く、智花へのいじめを目撃しても何もできなかった。いじめている側のクラスメイトの一人が、放課後に智花の事をからかった際に、『クラス全員あんたの事なんか嫌いだから!』と言い放った。その時に由香里も教室にいたが、『好きな人なんかいる?』という問いかけに、由香里は自分が智花側に行くことが怖くて何も言うことが出来なかった。
智花とは中学2年のころから親しくしていたので、本当であれば庇ってあげたい気持ちもあったが、由香里の心の弱さと、リーダーグループからの報復が恐ろしくて見て見ぬふりをしていたのだ。
『好きな人なんかいる?』という問いかけの際に口をつぐんでしまった由香里は、一瞬智花と目が合ったような気がした。智花が登校拒否になってから、由香里は智花との親交は高校進学もあり途絶えてしまった。
高校に進学してから、由香里は智花に対して申し訳ないという思いから、一度だけ手紙を出したことがあった。いじめに対して何もできなかった自分の弱さを反省し、智花に対して申し訳ないと思っているということを、短い文章ではあるが、心を込めて書いた。卒業文集にあった自宅の住所に手紙を送ったところ、智花から返事が来た。
『ありがとう。多分言いにくかったよね?それだけで嬉しいよ!これからお互いに新しい人生を楽しもうね!』
智花からの返事も短い文章ではあったが、その文面に由香里は救われた気がしていた。手紙のやり取りだけではあったが、それを贖罪として今でも自宅の押し入れに智花の手紙をしまってあるのだ。
そんな経験から、新しいクラスを何とかしたいと思った由香里は、ルックアップレターの事を思い出した。もともとは自分のもとに届いたルックアップレターがきっかけだったが、そこにはこう書かれていた。
『今が大変でも、きっといつか実を結ぶはず。自分を信じて!』
当たり障りのない励ましの文章ではあるが、資格試験の勉強をしながらアルバイトに明け暮れていた由香里にとっては大きな励ましとなった。後にそれがルックアップレターであるということを知り、とてもいいものだと感じていた。由香里は、新年度でクラス替え後の生徒たちにルックアップレターを流用することで、クラス内の交流と生徒たちの雰囲気改善を図ろうと思い、教頭に相談していた。
キラキラの手紙
教頭からルックアップレターの応用策について承認をもらった由香里は、新学期のスタートに向けて着々と準備を進めていた。どのようにしたら生徒たちがお互いに良い関係性を築けるのか、どうしたらクラス内の雰囲気が良くなるのかを真剣に考えた。また、生徒たちが自発的に関係構築に取り組める環境づくりも重要だと考えていた。
新学期を迎えた春。由香里は少し緊張した面持ちで初めての教室のドアを開いた。『ガラガラッ』と音を立てる引き戸は、どこか懐かしかった。緊張した様子で自分を見つめる生徒たちに笑顔で登壇し、自己紹介をした。生徒たちからは『由香里先生』と呼ばれることとなった。
ある日の道徳の授業で、例のルックアップレターを実践することにした。
『今日は、皆さんに提案があります。みんなが嬉しくなるような、みんなが仲良くなれるような魔法を先生が考えてきました!』生徒たちは『魔法』という言葉に途端に色めき立ち、『なに!?なに!?先生教えて!』と口々に言った。掴みは上々だった。
『美点凝視』という言葉を黒板に書くと、由香里は次のように説明した。
『この言葉は、難しい漢字だけど、とても素晴らしい意味があります。それは、友達の良いところを探してみようという意味です。』生徒たちは由香里の『魔法』にかかったように、食い入るように説明を聞いていた。続けて由香里はこの取り組みについて具体的な内容を生徒たちに説明した。
『皆さんはお手紙を書いたことはありますか?お手紙を書くときは、最後に自分の名前を書きますよね?でも、この手紙は自分の名前は書かないで出す手紙です。』生徒たちからたくさんの質問が出たが、要はこういうことだ。
- 友達の良いところをみんなで探そう
- 特定の人だけではなく、たくさんの人の良いところを探そう
- 人の良いところを探すことが出来る人は、自分もいい人になれる
- いいところを手紙に書いて、先生が届けます
- 自分の名前を書かないので恥ずかしくない
- 仲良くなった人には手紙ではなく直接伝えられるように仲良くなりましょう
ということだった。生徒たちは由香里の提案に賛成し、この取り組みは毎週1通以上の手紙を書くということで落ち着いた。書いた手紙は由香里が回収し、対象の生徒の机に始業前に入れておくということになった。こうすることで、登校すること自体が楽しみになればいいと由香里は思っていた。
せめてもの過去の償いも兼ねて。
生徒たちの発案でこの取り組みは『キラキラの手紙』という名前が付けられた。友達のキラキラした部分を見つけて、受け取った人がキラキラした笑顔になることを目的に取り組もうというのがその意味合いだった。小学2年生にしてはなかなか気の利いたネーミングだと由香里は思っていた。
キラキラの手紙を導入してから1か月が経った頃、教頭からその後の経過報告を求められ、由香里は月報にまとめた。概ね取り組みは順調であり、生徒たちからも評判は良かった。ほかのクラスの生徒も噂を聞きつけるくらい順調で、先生たちの中でも評価が高かった。一部の生徒は、まだ手紙の内容が薄い事もしばしばあるが、それも次第に好転していくであろうというのが由香里の報告内容だった。
『保護者へのアンケートでも比較的好評のようですね。初めての担任にもかかわらず、非常に頑張っていると思います。これからも継続して生徒たちの教育活動をよろしくお願いします。』教頭は短く切りそろえた頭をなでながら、由香里の取り組みを評価した。保護者からの評価も良かったという点は由香里にとっては自信になった。『かしこまりました。』と一礼して、由香里は自分のデスクへ戻り、当日の業務を片付けて帰宅した。
新米教師としてのスタートは順調だった由香里だが、プライベートはあまりうまくいっていなかった。教師の仕事は持ち帰ることも多く、当日の残務だけではなく次の日の準備にも時間がかかった。
大学時代から付き合っていた彼氏がいたが、教員免許を取得したころから時間のすれ違いが多くなり自然消滅していた。先日飲み屋で知り合った男性とメールや電話のやり取りをしているが、彼には家庭があり子供もいるようで、それ以上の関係にはならない状態が続いていた。

由香里の住んでいるアパートには大家の趣味の花壇があり、最近ではアジサイが咲いていた。
由香里は自分の部屋でサボテンを育てており、忙しい毎日でもそれほど手がかからないことと、『枯れない愛』という花言葉が気に入ったため、玄関の下駄箱の上に置いていた。2Kのアパートはほとんど寝るだけのための場所になっており、玄関のサボテンとアパート前の花壇が数少ない心の癒しとなっていた。
恐れていた変化
由香里は梅雨の季節が嫌いだった。小さい頃から癖毛がコンプレックスだったからだ。母も同じで癖毛だったため、恐らく母からの遺伝だと考えていた。洗濯物の生乾きの匂いと、雨が降った後の独特の匂いは、由香里の心をどんよりとさせた。
ある日いつも通り出社し、生徒からキラキラの手紙を回収したところ、恐れていたことが起こった。全部で34名の生徒のうち、今回の回収されたキラキラの手紙は28通、そのうち2通に悪口が書かれていた。当然対象の生徒の名前が記されていた。いつかは起こると思っていたことだが、由香里は回収した手紙を一度検閲することにしておいて良かったと思った。
生徒が家庭科の時間に作ったテルテル坊主が教室の窓に並ぶ中、ホームルームの時間に例の悪口の手紙について注意喚起をすることにした。
『皆さん、おはようございます。今日は先生からお願いがあります。キラキラの手紙は書けていますか?クラスメイトの良いところを探すのは簡単なことではありません。たまに、良くないところが見えてしまうこともあると思います。そんなことがあったら、手紙にせずに先生に相談してください。友達の直してほしいところを、良いところとに変えるお手伝いをしましょう。』
生徒たちには検閲していることを伝えていないので、当たり障りなく全体周知をした。半数の生徒は、由香里の言葉が何を意味するのか分からなかったようで教室内は少しざわついたが、学級委員が連絡事項の呼びかけをしたことで、教室内は落ち着きを取り戻した。
実は、キラキラの手紙を始めてから今まで、一度も手紙をもらっていない生徒が一人だけいた。クラス替えのきっかけとなった、いじめの対象となってしまった原田 舞(はらだ まい)だ。舞は綺麗なロングヘアーに二重の目をした非常に可愛らしい生徒だ。1年生のころからクラスでも友達が多く人気者であったが、その舞が授業中にお漏らしをしてしまったことから、反動でクラス内での立場が窮屈なものになってしまった。
一旦は登校拒否になったが、クラス内でも一連の出来事が過去のことになり、それを口にする生徒も出なかった事から、2年生の進級と同時に登校を再開した。
例の一件があったからなのか、舞が自発的にコミュニケーションを取ろうとしないからなのか、舞にはキラキラの手紙が一度も届いていなかった。正確に言えば、舞を含めて、手紙の宛名に名前がなかった生徒には、由香里が手紙を作成してフォローしていた。悪口が書かれたのは、まぎれもなく舞に対してだった。
キラキラの手紙を提出する際には専用のボックスに入れるため、誰が悪口を書いたのか特定することは難しかったが、ある程度筆跡から目星はつけていた。特に、片方は句読点を大きく書く特徴がある筆跡のため、由香里の中ではある女子生徒が書いたのではないかと考えていた。そうなれば、おのずとその生徒と仲の良い女子生徒がもう一通を書いたと思われ、由香里はその二人の様子を注意深く見守ることにした。
その日の放課後、職員室で夏休みの準備について職員会議があった。特に議題に上がったのは、夏休み中に開放するプールの監視当番のシフトだった。8月の全校登校日の2日後、由香里の先輩教諭の金森 恭子(かなもり きょうこ)が次の日の由香里のシフトと交換してほしいと申し出た。由香里は友人と出かける予定を立てていたが、先輩からの申し出に断ることが出来ず渋々了承した。
職員会議の後、手帳を眺める由香里のところへ恭子が声をかけた。
『萩原先生、シフトの交換悪いわね。予定調整大丈夫?』マグカップに注いだコーヒーを手に持ちながら、仁王立ちで由香里に声をかけてきた。恭子は由香里と同い年ではあったが、1年先に教員免許を取得し、同じ学校に配属になっていた。気が強く、声も大きいことから、学校内でも一目置かれていた。
『あ、お気になさらないでください。私は問題ありませんから。』
由香里は手帳を閉じて椅子から立ち上がり恭子に答えた。『そう?断りにくかったでしょ?でも嬉しいわ。初めての夏休み楽しんでね。』笑顔で立ち去った恭子の背中に、由香里は何か妙な違和感を感じた。それが何か分からなかったが、梅雨空の不安定な天気のように、どことなくふわふわしたものを感じた。

梅雨も明けて、由香里は教師としての初めての夏を迎えようとしていた。生徒の服装もほとんどが半袖になったころ、キラキラの手紙に1通の手紙が入っていた。いつも通り検閲すると、由香里は自分の目を疑った。そこには次のように書かれていた。
『由香里先生 どうして助けてくれないの。役立たず。あんたなんか必要ない。』
生徒が書いたとは思えない文面ではあるが、その筆跡は明らかに子供のように思えた。もしかしたら自分に対して不満を持っている生徒が手紙として主張しているのではないか。それに、『助けてくれない』というのは、例の原田 舞からの手紙ではないのか?しかし、舞の筆跡とは似ても似つかないと由香里は思った。
結局、誰のものなのか分からなかったが、由香里はモヤモヤとした感覚を抱えたまま、夏休みに入ることとなった。夏休みと言っても教員自身の休みは生徒たちと全く違い、2学期の準備で大忙しだった。それに加えて、プールの監視当番や当直当番などもあるため、ゆっくりと休めたのは全校登校日も終わり、学校全体が休みになるお盆時期の4日間ほどだった。
ゆっくりくつろげる時間がようやく取れたので、休みの間、由香里はマッサージに行って、あとは自宅で過ごしていた。突然、玄関の方で物音が聞こえたので何気なくいってみると、郵便ポストに手紙が入っていた。それを見た時、由香里は違和感を覚えた。キラキラの手紙だったからだ。なぜ分かったかというと、生徒たちと決めた特定の手紙の折り方だったからだ。
郵便受けから手紙を手に取り開いてみると、そこには驚愕の内容が書かれていた。
『由香里先生 どうして助けてくれないの。役立たず。あんたなんか必要ない。』
あの時と同じ文面だ。筆跡も多分あの時のものと一緒で間違いない。由香里は急いで玄関を開けると、今しがた投函されたであろう手紙の差出人の姿を確かめた。照り付ける太陽と、遅咲きのアネモネが花壇に揺れているだけで、人の姿はなかった。恐ろしくなった由香里は玄関の扉を閉めて鍵をかけた。
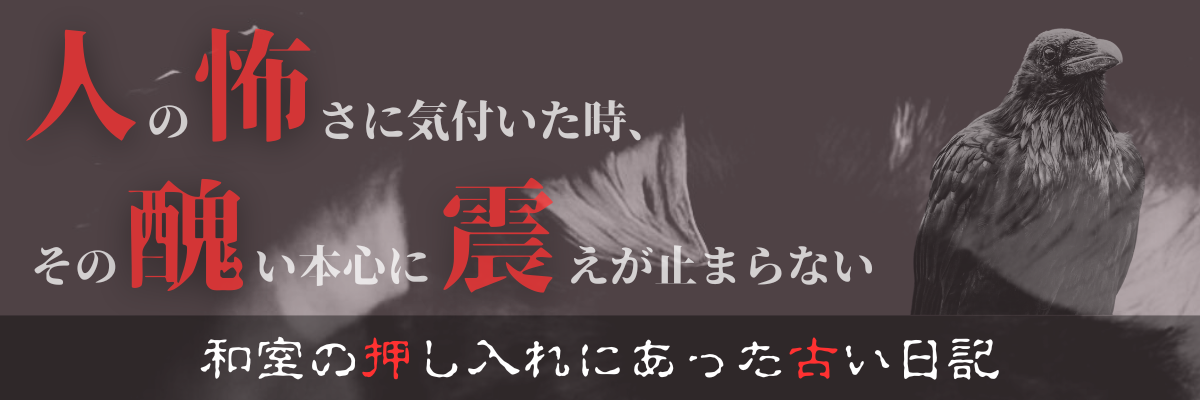




コメント