新任教師として小学2年生のクラスを担当することとなった由香里。いじめが原因でクラス替えがあったことから、『キラキラの手紙』という取り組みで、生徒同士の美点凝視とコミュニケーションの活発化を促進しようとした。始めはうまくいっていたが、ある日特定の生徒の悪口が書かれた手紙があった。
対応に苦慮している中、今度は由香里に向けた不満を書いた手紙が届くようになる。誰からの不満なのか、『どうして助けてくれないの?』とはどういう意味なのか。困惑する由香里はあることを思いつくが、物語は衝撃の展開を迎える。
差出人の行方
自分宛の奇妙な手紙に困惑したが、ついに自宅にまで届くようになったことで、由香里は教頭にこの事を相談することにした。
『実は、6月くらいから生徒からと思われる手紙が私のところに届きまして。これなんですが・・・』教頭は由香里が差し出した手紙を見ると、右手で眼鏡を押さえながらこう言った。『生徒からのもので間違いないんですか?』由香里はキラキラの手紙のボックスに入っていたことと、その後同じ筆跡の手紙で自宅にも届いた経緯を説明した。
『そうですか。であれば、新学期ということもありますので、個別面談を実施しましょう。萩原先生がこの手紙の差出人だと思う生徒をピックアップしてもらって、その生徒は私が面談します。それ以外の生徒は萩原先生が普通に面談してください。あとはこちらで理由をつけて体裁を整えますから。』
そういうと教頭は立ち上がり、由香里に手紙を返した。ふと、改めて由香里の方を振り返ると、『これ、本当に生徒からの手紙なんですね?それにしても、この筆跡どこかで見たことがある気がするな。まぁ、生徒の作文とか私も色々見ますからね。そのせいだと思うんですが。あ、どの生徒か分かっているわけではありません。ただ、印象的な筆跡だなと思いまして。』教頭は独り言のようにそう言うと、自分のデスクへ戻った。
教頭の提案した通り、2週間に渡って生徒の個別面談を実施した。由香里のクラスだけでは保護者への説明がつかないので、職員会議にて周知し、他のクラスでも面談は実施してもらうことにした。新任教師だからという理由で、由香里のクラスだけは教頭も補助で対応するという建前にした。
しかし、結果は意外なものだった。
由香里が面談した生徒も、教頭が面談した生徒も、事後の保護者アンケートも含めて、相変わらず由香里の教師としての評価は高かった。無論、由香里に対して不満を口にする生徒はなく、強いて言えば授業中に口にする言葉で四字熟語が多く、分からない時があるという小学生らしい注文はあったが、教頭と由香里が心配していた例の手紙につながるような意見は出てこなかった。もちろん、いじめられていた原田 舞も含めての話だ。
『特に問題はないようですね。きっと誰かのいたずらでしょう。あんまり気にする必要はないと思います。何かあるようなら、いつでも私に相談してくださって結構ですよ。萩原先生の評判は素晴らしいですから、これからも期待していますよ。』
教頭は力強くそう言ってくれたが、由香里はそう思えなかった。生徒からの手紙ではないとしたら、誰が自分に対して不満を持っているのだろう。教員の誰かのイタズラなのだろうか。ただ、総じて教員は字が綺麗な人が多く、あんな子供じみた筆跡はあり得ないと由香里は思った。疑心暗鬼に囚われそうになったが、ひとまず自分が一番関わる生徒たちからのものではないと自分に言い聞かせて、この件についてはそれ以上考えないことにした。
その瞬間、『ある考え』が由香里の脳裏をかすめた。
狂い始めた歯車
運動会の季節になり、由香里を含めた教員たちはその準備に追われた。空は澄み渡っていて、過ごしやすい日々が続いていた。校庭にはコスモスの花が風に吹かれて、生徒たちは砂場のどんぐり拾いに夢中になっていた。

例の一件以来、由香里のもとに不満を書いた手紙が届かなくなったが、ある日、キラキラの手紙で問題が起きた。それは、由香里が検閲をしていたにもかかわらず、生徒の一人に悪口を書いた手紙が届いてしまったのだ。ターゲットになったのは、坂口 加奈子(さかぐち かなこ)だった。
加奈子は活発な子で、人から恨まれるようなことはしない生徒だったが、親が金持ちで裕福であり、そのことを妬んだような内容の手紙が、加奈子の机の中に入れられていたのだった。由香里が検閲をした際にはなかったはずの手紙であり、特徴的だったのはそれがワープロで作成されている事だった。
『誰ですかこんなことをしたのは!?』由香里は初めて生徒たちの前で声を上げた。
『先生は犯人探しがしたいんじゃありません。人を傷つけるということがどれほど悲しいことなのか知ってほしいんです。人を傷つければ、その人も傷つくことになるんです。だから、こんなことはもう絶対にやめてください。先生からのお願いです。』
由香里はトーンを抑えて生徒たちを諭すように言った。静まり返った教室には、異様な雰囲気が漂っていた。
その日の放課後、由香里は教頭に呼び出された。
『例の話聞きましたよ。検閲はしていたんですよね?』教頭は静かにそう言った。
『はい。ボックスの回収は毎日していて、中身を全て確認してから生徒に配布しています。』由香里は回収した手紙の宛名とチェック結果を表にした資料を見せながら答えた。キラキラの手紙が始まったころに、届く手紙の枚数が偏らないように、全て管理していたのだ。
『とすると・・・これはボックスではなく直接生徒が机に忍ばせたということになりますよね。』教頭は白髪交じりの短髪を撫でながら、困った様子で資料を見つめていた。
『しばらくこの運用は中止したほうがよろしいでしょうか。』由香里は力なく教頭に告げると、『そうですね。事が落ち着くまではちょっと様子を見ましょうか』と教頭は指示した。由香里は指示に従い、次の日のホームルームで生徒たちにキラキラの手紙の中止を告知した。ボックスは撤去して、事態が収束するまでは、お互いに直接いいところを伝え合おうという話で落ち着いた。
しかし、またその次の日に加奈子の机には手紙が入っていた。内容を見た加奈子はその場で泣き崩れた。
『親父が巻き上げた金で暮らしている、クズの娘。お前なんかいなくなってしまえばいいんだ。』
さすがの教頭もこの内容を見て、加奈子を保健室登校にするよう指示した。すぐに保護者を学校に呼んで事情を説明し、全力で解明する事、加奈子を安全に保護することを約束した。『大変失礼ですが、何か他人から恨みを買われるような心当たりはありませんか?些細なことでもいいんです。娘さんを守るためにご協力いただけると・・・』教頭が申し訳なさそうに言うと『ありませんね。』と加奈子の父は答えた。
その一週間後、また加奈子の机には手紙が入れられていた。今回は、これまでと違っていた。手紙と共にカエルの死骸が机の中に入れられていたのだ。加奈子が登校すると、加奈子の絶叫が職員室まで響き、聞きつけた職員が何事かと駆け付けた。
手紙にはこう書かれていた。
『早く死ね。早く死ね。早く死ね。早く死ね。早く死ね。』
加奈子はその場で気絶して保健室へ運ばれた。教頭は校長に相談し、急遽休校にすることとし、学校を閉鎖した。職員室では例の一件が議題に上げられた緊急職員会議が開かれて、今後の対応方法が5時間に渡り議論された。
14時ごろ、議論が続く職員室の電話が鳴った。加奈子の母親からの電話だった。なんと、加奈子が自宅のマンションから飛び降りて自殺したというのだ。あまりにショッキングな内容に、電話を受けた教頭は腰を抜かして受話器を落とした。電話を替わった校長が事情を確認して、職員会議を中止し、校長、教頭、そして担任である由香里の3名で加奈子の自宅へ急行した。

現場へ向かうタクシーの中で校長は関係各所へ連絡を取り、教頭はワナワナ震えていた。由香里はうつむいて後部座席にへたれこんでいる様子だった。車窓から見えてきた加奈子の自宅マンションにはすでに救急車と警察車両が到着していて、辺りは大騒ぎになっていた。
警察に了解を取り、規制線の中へ入って加奈子の両親と会った。途端に加奈子の母親が鬼の形相で校長につかみかかった。
『なんでよ!なんで娘が死ななきゃならないのよ!あんたの管理責任じゃないの!?』ほとんど声にならないような絶叫で校長のスーツの襟元をつかみ、加奈子の母は涙ながらに訴えた。校長は成す術無く『申し訳ありません』と呟くしかできなかった。
落下現場になったと思われる駐輪場は、屋根が大きく折れ曲がっていて、その衝撃を物語っていた。また、ブルーシートは掛けられているが、飛び散った血痕でアスファルトが赤く染まっていた。加奈子の者と思われる靴は、駐輪場から20m以上も離れた場所に落ちていた。
警察に聞かされた話では、屋上に遺書らしき書置きがあり、恐らく加奈子が書いたものであろうということで、筆跡鑑定が進められているという。その書置きにはこう書いてあったとのことだ。
『誰かが私の事を要らないって言ってる。パパとママも私がいると幸せになれないみたい。天国からみんなを見守っているから。由香里先生の授業楽しかった。さよなら。』
やはり、直接的な原因は例の学校での手紙にあるようだ。また、両親の仲があまりうまくいっておらず、時折親権について口論している声を、幼い加奈子は自室のベッドで聞いていたようだ。あまりにも悲痛な内容に、それを見た誰もが絶句して涙ぐんだ。
ある一人を除いて・・・
加奈子の葬儀が終わると、学校は1か月間の閉鎖を余儀なくされた。加奈子の両親は娘の死をきっかけに離婚することとなり、あのマンションからも引っ越したそうだ。校長と教頭は教育委員会から降格を命じられ、年明けから別の学校へ転勤することが決まった。由香里は担任として状況改善に努めていたということが認められたが、自殺者を出してしまったことから自主退職する事にした。
誰かに見られている
由香里は退職した後、しばらくの間は就職せずに自宅で暮らしていた。そんなある日、また郵便受けのほうで音がした。手紙だ。
由香里は少し不気味だったが、玄関のドアを少し開けて誰もいないことを確認し、郵便受けの手紙を開いてみた。呆然と手紙を眺めていた由香里だったが、手紙は1通ではなかった。郵便受けに入っていた手紙を全てテーブルに持っていき、1枚ずつ読んでみた。由香里はそのすべてを読んだとき驚愕した。
由香里先生 生徒が困っているのに、やっぱり何もしなかったんだね。
由香里先生 知ってたの。パパと由香里先生のこと。
由香里先生 いつまでも隠し通せると思うなよ。全部ぶちまけてやるから。
由香里先生 過去の過ちは消せないってこと思い知らせてやる。
由香里先生 今度はお前の番だ。
まるで、死んだ加奈子が由香里に対しての恨みを綴ったかのような文章に、由香里は手紙を投げ捨てた。狭い6畳間に散らばった手紙を見つめながら、由香里はガタガタ震えていた。季節はもうすぐ雪が降りそうな時期だったが、それは紛れもなく恐怖による体の震えだった。
『誰?誰なのよ?加奈子ちゃんなの?そんなはずない。だって・・・彼女はもう死んでいるんだから!』

部屋の中で一人由香里がそう叫ぶと、また郵便受けに手紙が入れられる音がした。咄嗟に振り返って『誰なのよ!』と由香里が叫ぶと、それは手紙ではなくビデオテープだった。唐突な出来事に由香里は拍子抜けしたが、ビデオテープのラベルには『お前がしたこと』と書かれていた。
恐る恐るビデオデッキにテープを入れて再生しようとしたが、手が震えてなかなか再生ボタンが押せなかった。冷たくなったコーヒーを口に運んで一呼吸すると、由香里はビデオを再生した。
テレビに映ったのは、かつて由香里が教壇に立っていたあの2年生の教室だった。どうやら教室後方のロッカーの方から撮影されたような画角だった。しばらくすると、教室には由香里が現れた。太陽の方角と高さからして恐らく放課後だろう。生徒のいない教室に現れた由香里は、加奈子の机に何か隠した。
『え・・・まさか・・・』
次に映ったのも教室だった。同じように由香里が現れると、バケツに入れた何かと、反対の手には手紙を持っていた。バケツから取り出したのはカエルの死骸だった。
そう、加奈子に嫌がらせをしていたのは、担任だった由香里本人だったのだ。
次の瞬間、ビデオの画面が夜の繁華街を映していた。画面の揺れから考えるに誰かが手持ちで撮影しているらしい、しばらくすると一組の男女をカメラは追いかけていた。立ち止まってキスをした男女は、由香里と加奈子の父だった。
『誰が?いつの間に!?』
実は、飲み屋で知り合い、連絡を取るようになった男が加奈子の父親だった。5月のゴールデンウィーク過ぎに実施した父親参観でそのことを知った由香里は、お互いに弱みがある関係性のため、世間の目を盗んで密会することを加奈子の父に強要していた。しかし、会社役員でもある加奈子の父は、事態が公になることを恐れて、由香里に対して関係の解消を提案していた。それに、子供もいるということを由香里も知っているはずなので、誰も幸せにならないと説得していた。
それが許せなかった由香里は、2学期の個別面談が始まったタイミングで起きていた『悪口の手紙』を利用して、加奈子を死に追いやった。加奈子が居なければ険悪になっている妻とは離婚して自分と一緒になってくれるだろうと思っていた。それが叶ったと思った矢先、実は誰かにその事実を知られていたということがこのビデオで発覚したのだった。
『誰がこんなことを?いつから?これで何をしようとしているの?』
由香里は自分の犯した罪よりも、その罪を知っていることで、何を企んでいるのか、ビデオの送り主の真意が気になっていた。
突然ビデオから人の声が聞こえ始めた。狭い由香里の部屋では近所に憚られるような声だった。アダルトビデオのようなその声の主は、由香里と教頭だった。ビデオの中身は教頭室で事に及んでいる二人を盗撮した映像だった。実は、教頭は新任教師に手を出すことで密かに有名で、由香里とも肉体関係に及んでいた。そのため、学校内での由香里の評価は優遇されており、何かと教頭が手伝っていたのだ。
加奈子への嫌がらせ、加奈子の父との不倫、さらには教頭との関係。由香里は短い教師生活の中で、隠しておきたい秘密を抱えていた。しかし、それを全て知っている人物がいるらしい。この秘密を元に、送り主は何をするつもりなのか、そう考えると由香里は疑心暗鬼になった。
新たな人生
由香里に届く脅迫めいた手紙とビデオはその後も毎日続いた。由香里は自分でしたことだとは言え、誰に知られているのかということを考えると、アパートから出ることさえできなくなり、完全にノイローゼになっていた。
ある日、抜け殻のように自宅で外を眺めていると、玄関のチャイムが鳴った。
やっとの思い出立ち上がって玄関ののぞき窓から確認すると、そこに立っていたのは元同僚で先輩教諭の金森 恭子だった。
玄関のドアを開けると、『金森先生!』と由香里は恭子を迎え入れた。『どうされたんですか?』と尋ねると恭子は『近くを通ってね。萩原さんこの辺に住んでたよなって』恭子は手土産らしきドーナツを差し出して由香里にそう言った。
恭子を居間に通すと、由香里はもらったドーナツを皿に盛り付けてコーヒーを淹れた。『ミルクと砂糖はどうされますか?』一応先輩だったことを思い出して由香里は敬語で聞いた。恭子はいつもブラックでコーヒーを飲んでいることを知っていたが、頭が働かない状態の由香里はとりあえず聞いてみた。
『久しぶりね?痩せた?』という恭子に、苦笑いをしながら由香里はコーヒーカップを差し出した。『まぁ、あんなことがあったんだもん、仕方ないわよね。』と加奈子の一件を示唆して由香里を気遣う素振りを見せた恭子は、由香里の淹れたコーヒーを飲みながら軽く微笑んだ。
『学校は・・・その後どうですか?生徒たちはどうなりましたか?』社交辞令なのか本心だったのか自分でもよくわからないが、由香里はとりあえず当たり障りのない質問をしてみた。恭子はその後の学校の様子について教えてくれたが、2年生のクラスはまた新たにクラス替えがあり、担任は体育の教師が担当することになったという。新しい校長のやり方が少し窮屈だということを恭子は愚痴っぽく話した。『それにね・・・』と恭子は切りだし、
『あんたのせいでパパがいなくなっちゃた』と突然語気を強めて恭子は言った。
『どういうことですか?』と由香里は聞き返した。すると、恭子は立ち上がって仁王立ちしながら滔々と話し始めた。
『どういうことって、ビデオ見たんでしょ?パパとあんたがヤってるところ、バッチリ撮れてたでしょ?あんたが入ってくるまでパパは私だけのものだったのに、あんたが横取りしやがって!また私の人生の邪魔をするわけ?』恭子はあざ笑うかのような調子で捲し立てた。
『また・・・って、どういうことですか?』由香里は恐る恐る京子に尋ねた。
『あー、分からないか。新しい人生を楽しもうねって手紙返したじゃない、由香里。』
由香里は呼吸が止まりそうな気がした。以前、夏休みのプールの監視当番を交換した際に感じた違和感が、再度体中を駆け巡った。どこかで聞いたことがあるよな口振りだった気がしたあのセリフが、頭の中で何度も繰り返し響いたのだった。
『あなた、もしかして・・・』
『そうよ。あんたが自分だけを守ろうとして捨てられた、智花よ』

なんと、恭子は由香里の高校時代にいじめられて不登校になった『小林 智花』だった。高校時代の経験が辛く悲しいものだったので、大学へ入学した後に整形し、戸籍名を変更したというのだ。それほどまでに、智花の学生時代は心に傷を負い、無かった事にするほか方法が見つからなかったのだ。由香里と同じく教頭から言い寄られて関係を持っており、教頭の事を『パパ』と呼んでいた。
『あんたもさぁ、友達みたいな顔して笑ってたくせに、自分を守る段になったら急に知らんぷりだもんねー。あの時は本当に悲しかったねぇ。でもね、私が一番むかついたのは、それが無かった事かの様にあんたが手紙を出してきた時だった。こいつ、自分は悪くない、自分は善人だって事が言いたいんだなって思ったよ。だから、人生をかけて復讐してやろうと思った。都合のいいことに同じ職場にノコノコ現れてさー!アハハハハハハハ!!!』
狂気じみた恭子、いや、智花の喋り方は、声以外は全くの別人に思えた。由香里に対する智花の憎しみと、復讐に心を燃やす冷淡な悪魔に思えた。
『なんでそんなひどいことを!』由香里は後ずさりしながら智花に叫んだ。
『ひどいこと?え?どの口が言ってんのよ!あんたは私だけじゃなく、何の罪もない加奈子ちゃんを自分の欲望を叶えるために利用して殺したくせに!』
確かに由香里は加奈子を利用して殺した。それは完全に由香里のエゴだった。
『それは・・・、それは・・・』由香里には返す言葉がなかった。
『結局あんたは自分のために他人を犠牲にする糞みたいな女だってことだよ!性根はいくら時間が経っても変わらないんだよね!他人を傷つけたら必ず自分に返ってくるってことを思い知らせてやるよ!』
由香里は過呼吸になりながら、先ほど食べたドーナツを吐き出した。しかしそれでも呼吸が苦しく、由香里は床に倒れ込んで悶えた。薄れゆく意識の中で智花がこう言っているような気がした。
『そろそろ効いてきたのかもね。残念だったね。あんたの人生はこれで終わりだよ。地獄で後悔するんだね!ハハハハハハ!』
智花は、持ってきたドーナツに青酸カリを仕込んでいた。どおりでコーヒーにしか手をつけなかったはずだ。由香里は泡を吹きながら白目をむいて手足をバタバタとさせて、暫くすると動かなくなった。
由香里に一瞥を向けてコーヒーをひと啜りした智花は何事もなかったかのように立ち去った。雪がチラつく中、智花が開けっ放しにした玄関のドアの向こうには、アパートの花壇咲いた黄色いアイリスが揺れていた。

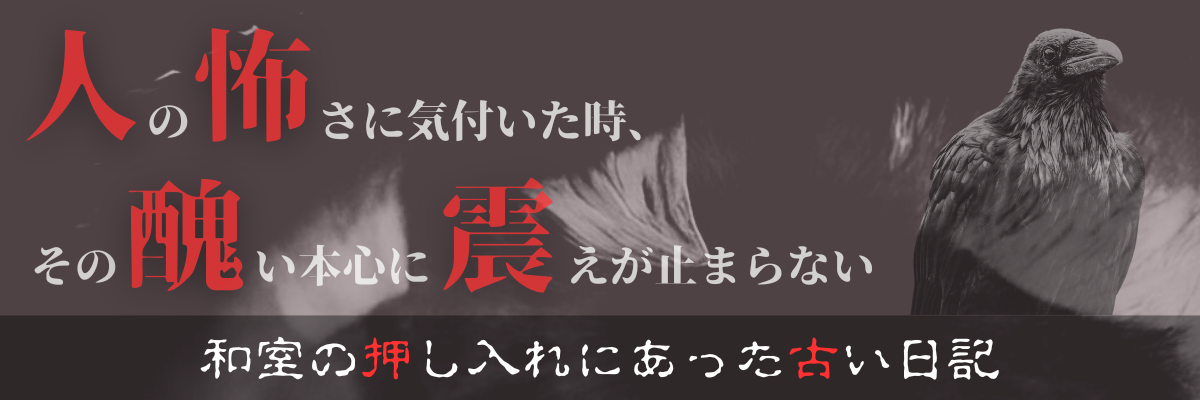




コメント