職を失い失意のうちに帰宅した航だったが、恵那の優しい一言に救われたような気持になった。いつか訪れるであろう定職獲得の日のために資格勉強に精を出そうとする航だったが、妙な変化に気付き始める。それは、恐怖の入り口に過ぎないことなど、知る由もなかった。
小さな祠
今日も航は職安へ自転車を走らせていた。夏本番を迎える季節に自転車を漕ぐのは一苦労だった。汗だくになりながらも、今日貰ってきた書類を確認しようと自宅アパートの駐輪場へ航は自転車を停めた。ふと、航は先日の妙な臭いの事が気になって、アパートの周りを調べてみることにしたのだ。
航が住むアパートはどこにでもあるようなアパートだったし、近くに養鶏場や牧場があったりするような場所ではなかった。当然ゴミ処理場などの『それらしいもの』があるわけでもなく、平坦な道が続く裏通りにポツンとあるようなアパートだった。
アパートの前の長く続く道に陽炎が見えた視界の端っこに、航はあるものを見つけた。アパートの各部屋のエアコンの室外機がまとまって設置されている場所だった。その更に脇のところに小さな祠のようなものがあることに気付いた。航は新卒入社に失敗してこのアパートに越してきたのでまだ半年ほどしか生活しておらず、今までこの祠の存在に気付いたことはなかった。
近寄ってよく見てみると、水道で使うバケツ位の大きさの簡素な祠だった。雨風にさらされて、紙垂(しで)は茶色く変色してしまっていたが、桐でできた祠は作り自体は立派なものだった。扉は開いており、なかから2つほど毛筆で書かれたお札が顔を覗かせていた。『何のための祠なんだ。それにこんなところに粗末に置いてあるなんて』航はそう呟くと、何となく嫌な感じがしてそれ以上は祠に近づくことはしなかった。
大家に祠の事について聞いてみようと思ったが、どうやら留守らしい。ここのアパートの大家は殆ど留守にしていて、必要な時にアパートに居た試しがない。不動産屋も大して当てにならないと思った航は、仕方なく自宅の玄関を開けて職安からもらってきた書類に目を通すことにした。
『それにしても妙だな。祠があるってことは何かを祀ったり鎮めたりするために置いたってことだよな。何が目的だったんだろう。それに、せっかくの祠なのにあんな粗末な場所に置くなんて、罰当たりもいいところだ。』書類に目を通しながら航は独り言のように呟いた。
次の日の朝、玄関口で恵那と出くわしたので、例の祠の事について尋ねてみた。
『あのエアコンの室外機のところにある祠って何のために置いてあるのかご存じですか?』
航はリュックを背負いながら、赤ん坊を抱いた花柄のワンピース姿の恵那に向かってそう言った。
『え?祠ですか?ちょっと、落ち着いてくださいよ。祠なんてないはずですよ?』
そんなことはない。自分は昨日ハッキリと薄汚れた小さな祠を見た筈だった。今回ばかりは恵那に反論すると、恵那を連れて室外機のところへ行ってみた。すると、何故か昨日はそこに置かれていた筈の祠が無くなっていた。『無くなった』のか『そもそも無かった』のか航には分からなかったが、恵那はいたずらっぽく笑いながら、『だから疲れすぎですよって忠告したじゃないですか。本当に、心配になりますよ。』と航に話しかけた。
そう言うと恵那は朝食の準備があるからと自宅へと向かい、アパートの怪談を静かな足取りで登っていった。何故だ。昨日は確かにあったはずだ。妙な違和感を感じた航は、これが『キツネにつままれた』という感覚なのかと思ったほどだ。いや、そんなはずはない。確かに昨日見た祠は実在したものだったはずだ。あれだけハッキリと認識できたのに、見間違えるはずはない。じゃあ、なんでーーー
航はモヤモヤした気持ちを抱えながらその日も職安へと自転車を走らせた。帰ってきたのは18時を回った頃だった。
恵那の鳴き声
職安から帰ると、航は夕飯の準備を始めた。その日は職安で大した話を聞けずに、もらってきた書類に目を通す気にもなれなかったからだ。夕食と言っても、帰りの道すがら立ち寄ったスーパーの半額シールが貼られた総菜と大根の葉っぱや豆腐を入れただけの質素な味噌汁が主体だった。航の計算では、一人暮らしの自分にとって毎日の食材を買ってきて作るよりも、安くなっている総菜で済ませたほうが出費は抑えられる計画だった。
夕食時にはテレビを付けないのが航の習慣だった。特に理由があるわけではないが、自分は何か気になるとそちらに集中してしまう癖があり、少ない生活費で食べる食事を大事にしようと思ったからだ。しかし、今回ばかりはテレビをつけておいた方が良かったかもしれないと航は後になって思った。それは、壁の向こう側から恵那のすすり泣くような声が聞こえ始めたからだ。
本当に微かな声で、殆ど溜息に近いような、『涙も枯れ果てた』という表現がぴったりの小さく弱弱しい声で恵那が泣いているような気がした。悪いと思いながらも、航は好奇心から壁に耳を付けてその様子を窺ってみることにした。すると、恵那の鳴き声と共に、あのカリカリという音も聞こえてきている気がした。
どういう事だろうと思った航はしばらく壁に頭を付けて恵那の泣き声とそのカリカリという不気味な音を聞いていたが、なんとなく奇妙なことに気付いてしまった。カリカリという音は以前と同じように正確に表現するなら『カリッ、カリカリ、カリ、カリ』という不規則な音に対して、恵那の泣き声は規則的に聞こえてくるのだ。だいたいは呼吸に合わせて緩急が付きそうなものだが、恵那のそれはまるで針が飛んでしまったレコードのように同じ音節を繰り返しているように思えた。
堪らなくなった航は立ち上がると、玄関を出て恵那の自宅の玄関扉をノックした。
『松嶋さん、ごめんください。』
航は先ほどの泣き声を聞いていたことを悟られないように、努めて普段と同じ声色でそう呼びかけた。しばらくすると玄関の扉が半分ほど開いて、恵那が顔を覗かせた。航は少し意外な印象を受けた。それは、先ほどまで泣いていた筈の恵那は、その顔に涙の後もなく、目も腫れているような様子は見られなかったからだ。無論、裸電球が一つしかない玄関先だったので暗くて見えなかっただけかもしれないが、恐る恐る航は恵那に尋ねてみた。
『あ、夜分にすみません。お宅の方から泣いているような声が聞こえたので・・・。』
『え?うちの子ですか?うちの子はずっと眠ってますよ?』
『いや、赤ちゃんじゃなくて・・・』
『え?私ですか?泣いてなんかいないですよ。泣いてたら玄関開けませんし。』
『あぁ、そうですか。何かあったのなら相談に乗ろうと思ったんですが、思い違いでしたかね。失礼しました。』
『いえいえ、心配していただいてありがとうございます。でも大丈夫ですよ。それよりも本当に疲れすぎですよ。』
恵那はあっけらかんとした表情で航に微笑みかけた。詫びの言葉を告げて恵那の自宅から後ずさりすると、また航は『キツネにつままれたような』感覚に陥った。
『確かに聞こえた筈なんだけどな。なんかおかしいな。でも、仮に泣いていたとして、それを他人に相談することもないのか。何でもないってのは社交辞令だったのかな。だとしたら、悪いことしちゃたかな。』
そんなことを呟きながら、航は自宅へと戻っていった。
それにしても、最近妙なことが起き過ぎてはいないか。あのカリカリという音、屍臭の様な臭い、消えた祠、そして恵那のすすり泣く声・・・。全てが自分の思い違いなのか。それとも何か関係があるのか。その時はどういうことか分からなかったが、後になってそれが全て線でつながれる日が来るとは、航は思ってもみなかった。
我慢の限界
しばらく職安でいい案件が見つからなかった航は、資格試験の勉強に時間を費やしていた。午前中は8時から12時まで、午後は14時から17時まで。気が乗らない時もあったが、職安へ出かける時と買い出しやそれ以外の用事がある時以外は、ほとんどの時間を資格勉強に費やしていた。
ある日、午後の資格勉強をしていると航の部屋の電話が鳴った。実家の母からの電話だった。就職活動はどうかとか、ちゃんとご飯は食べているかなど、航の近況を心配する内容の話だった。久々に聞いた母の声に航は少し懐かしく、どこか申し訳ない気持ちが込み上げてきて、早く定職に就かなければという気持ちが一層強くなった。
電話の最後に母が妙な事を口走った。
『じゃあ、体に気を付けてね。・・・それと、さっきから気になっていたんだけど、あんまり彼女を泣かせたらダメよ。仲良くやってちょうだい。』
『え、母さん、俺彼女なんて居ないよ?何を言ってるんだい?』
『いや、ずっと隣で泣いてるじゃない。隠したって駄目よ。あなたもいい大人なんだから彼女が居てもおかしくないけど、女を泣かせる男はロクなもんじゃないよ。しっかりしなさいね。じゃあね。』
そう言うと、母は電話を切った。航は寒気がして受話器を置く手が震えていた。当然自分の部屋の中には自分しかいないし、先日聞こえた恵那のすすり泣く声も今は聞こえていない。それにも拘わらず母は何を聞いていたというのだろうか。悪い冗談か?それにしては唐突過ぎて脈絡が分からないし、母は冗談を言うようなタイプの人間ではなかった。だとしたならば、一体どういう事なんだ。航は得体の知れない恐怖に包まれて資格勉強どころではなくなってしまった。
しばらくして落ち着きを取り戻した航は、参考書を開いて勉強を再開したが、先ほどの母の言葉が妙に気になった。どこからそんな声が聞こえたのか、そもそも、『誰の』声なのか。そう思っていると、またしても航の背筋は凍り付きそうになった。例の恵那のすすり泣く声が聞こえてきたのだ。それは、以前よりも大きな声で泣いているような、壁の向こう側というよりは自分の部屋の中で泣いているような大きさの声だった。
さらに、あの『カリカリッ』という不気味な物音も恵那のすすり泣きに合わせて聞こえてきた。その二つの音が航の周りをグルグルと回るように大きくなったり小さくなったりして、航は恐怖に包まれた。両手で耳をふさいでみてもその音と恵那のすすり泣きは聞こえているような気がして、航は部屋の中でうずくまった。
『何なんだこれは!どういう事なんだ!?何が起きてるんだ?』
航は心の中でそう叫んだ。すると、フッと音が止んだ。と同時に、あの屍臭の様な臭いが航の鼻を刺した。またかと思った航は殆ど手すりだけのベランダへと駆け寄って窓を開けて身を乗り出した。恵那の部屋の方が見た航はギョッとした。強烈な悪習と共に、恵那の部屋のベランダにはウジ虫が大量に蠢いているのが見えたからだ。さすがにもう限界だと思った航は急いで玄関へ飛び出して、ノックもせずに恵那の部屋の玄関扉を開け放って叫んだ。
『いい加減にしてくれよ!ゴミくらいちゃんと捨ててくれませんか?それに・・・』
航は次の言葉が出るかどうかという所で、目の前の光景に卒倒寸前だった。そこには、壁中にお札が貼られており、部屋の真ん中に正座した恵那が赤ん坊と思しき白骨化した遺体を抱いてすすり泣いていたのだ。部屋の中にはあの悪臭が充満しており、航は今にも吐きそうになった。恵那の体にはウジ虫が這いつくばり、赤ん坊と思しき白骨化した遺体の目玉の部分からウジ虫があふれ出ていた。
思わず玄関の扉をバタンと閉めた航は全ての事が繋がった。
恵那の抱いた赤ん坊はいつも静かに寝ていた。顔は見えなかったが、随分と大人しい赤ん坊だと思っていた。しかし、それはすでに死んでしばらく経った遺体だったのだ。だから泣き声なんて聞こえるはずが無かったのだ。あのカリカリという音は、白骨化した赤ん坊の頭蓋骨を撫でる恵那の爪の音で、すすり泣きは死んだ赤ん坊を抱いた恵那の声だったのだ。ウジ虫は遺体を放置しているから得も言われぬ悪臭と共に部屋から這い出てきたのだ。
考えるだけでもゾッとするような光景に眩暈を感じながらも、今朝方見かけた大家の姿に助けを求めようと、大家宅の玄関扉をノックした。
『すみません!すみません!大家さん、助けてください!』
大声で叫ぶ航に対してゆっくりと扉を開けた大家が『ああ、落合さん、どうしたんですかそんな血相を変えて』と尋ねた。
大家の話
『ちょっと落ち着いてくださいよ。何が起きたっていうんですか?』
大家はめんどくさそうに航に尋ねた。
『何が起きたのかはわかりませんが、隣の松嶋さんおかしくなっちゃってると思うんです。お子さんが死んでいるのにその屍を抱いて部屋の中でずっと泣いているんですよ?』
大家は航の話に少しギョッとした表情でこう続けた。
『松嶋さん・・・ああ、落合さんの隣の部屋の。』
『ええ、そうなんです。いつも赤ん坊を抱いているけど随分泣かないなと思っていたんですが、どうやらなくてなっているようなんです。きっとそのことが受け入れられずに、松嶋さんはおかしくなってしまったのではないかと。』
航は興奮のあまりところどころ詰まりながら大家にそう話したが、大家は意外な返答をしてきた。
『確かに松嶋さんはお子さんを亡くしたんですよ。でも妙ですね、それはもう3年も前の話ですよ。』
航は固まってしまった。3年前の出来事だと?自分は先ほどこの目で見てきたんだ。例のカリカリという音もすすり泣きの声もウジ虫もこれまで何度も目の当たりにしてきた。とうとうその実態をこの目で確かめたからこそ相談に来たのだ。大家がいつも自宅に居ればもっと早くに相談に来れた筈だったのだ。それが、今しがた見てきた光景を3年前の出来事と言われても航には信じられる筈が無かった。
大家の話によると、恵那はシングルマザーで行政の助けを借りながらこのアパートへ引っ越してきたらしい。生活は楽ではなかったが、両親の助けや行政の力を借りて、なんとか子供を育てながら必死に生活していたらしい。恵那はいつも笑顔を絶やさない女性だったという印象が強かったそうだ。
それが、お盆前のちょうど今くらいの時期に、ブレーカーの修理を頼まれて大家が恵那を訪ねた時、玄関先で作業している大家を、恵那はベビーカーに赤ん坊を乗せて日向ぼっこがてら話し相手をしていた。恵那がお茶を入れに行った僅かな時間の間に、何かの拍子で赤ん坊を乗せたベビーカーが玄関先の階段から落ちて、赤ん坊はそのまま亡くなってしまったというのだ。
落ちた衝撃で全身を強打しており、病院に運ばれたがすでに手遅れだったというのだ。悲しみに暮れた恵那は自宅に籠るようになり、異臭に気付いた近隣住民が部屋に入ると、部屋の真ん中で赤ん坊を抱くような格好で死んでいる、もう腐りかけた恵那の遺体があったそうだ。
不慮の事故で亡くなった赤ん坊の魂を鎮めるという事と、恵那の無念の供養にと例の祠を作ったという。エアコンの室外機が置いてある場所は、ちょうど恵那の部屋から一番近い場所だったからだ。しかし、それも3年前の話であり、恵那の一件があってからは事の異様さから入居は断っているとのことだった。
『じゃあ、俺が見たのは何だっていうんですか?』航は大家に詰め寄った。
『そこまで言うなら、一緒に見に行きましょうか。鍵だってしばらく開けてない部屋なんですから。』
大家の言葉が信じられなかったが、航は大家と共に恵那の部屋へと向かった。その途中で目を遣ると、例の薄汚れた祠は確かに依然見た時と同じ場所に雑然と置かれていた。大家が鍵束の中から選んで玄関のドアを開けると、航は信じられない光景を目にした。確かにそこは、ガランとして陰気な雰囲気をまとった空き室が鎮座しているだけだったのだ。
『ね?落合さんが言ってた話が嘘じゃないなって思ったのは、この部屋を貸出しなくなった理由の一つでもありましてね。高嶋さんの遺体が見つかった時、落合さんが言うようにお札が壁中に貼られていたんですよ。それで、そのお札を剥がそうとしたんだけど、どうしても跡が残ってしまって、他の人に貸し出しを出来る状態じゃなくなっちゃったんですよね。』
確かに言われてみればその空き室の壁には、所々古い髪の様な切れ端がこびりついたような跡があった。という事は、自分が今まで体験してきたことやさっき見た筈の恵那の姿は、この場所に住み着いた恵那の亡霊だったという事なのか。航は改めて背筋が凍るような妙な感覚に襲われた。
『あぁ、あとね、松嶋さんは彼氏がいたんですが、その彼氏が住んでいたのがあなたの住んでいた部屋なんです。彼氏は松嶋さんの亡くなった後、どこかへ引っ越ししてしまったんですが。松嶋さんの親がなかなか厳しいご両親だったみたいで、お付き合いしていたのに、定職に就かない彼氏なんて同棲するなって言われていたみたいなんですよね。』
航は、今まで恵那から掛けられた言葉の意味が何となく分かったような気がした。きっと、恵那は彼氏と似た境遇の航に対して、生前の姿で現れたんだろう。恵那が亡くなってから作った祠だったから、例の祠についても知らないと言っていたんだろうと、航は自分に言い聞かせた。でも、何故恵那は自分の前に現れたのか。それだけはどうしても分からなかった。
『それにしても、ベビーカーが落ちてしまった原因とかあったんですかね?そんなに狭い場所でもないのに。』
航が尋ねると、大家はゆっくりと口を開いてこう言った。
『松嶋さんは自分が目を離した責任を感じて自分のせいだって言ってたんですよね。警察が現場検証をしたんだけど、ちょうどその日は風が強かったから、風に煽られて動いてしまって、その弾みで落ちてしまったんだろうという結論になったんですよ。』
『それは松嶋さんも悔やんでも悔やみきれませんね。だからずっとここに気持ちが残っているのかもしれませんね。』
航はそう言って玄関のドアを閉めると、大家がボソッと呟いた。
『でもね、本当は違うんです。脚立から降りた拍子に私の足がベビーカーに当たってしまってね。そんなの言い出せないじゃない。でも、今でも彼女の亡霊に追われているんですよ。だから、あまりこの建物には居たくないんだよね。』
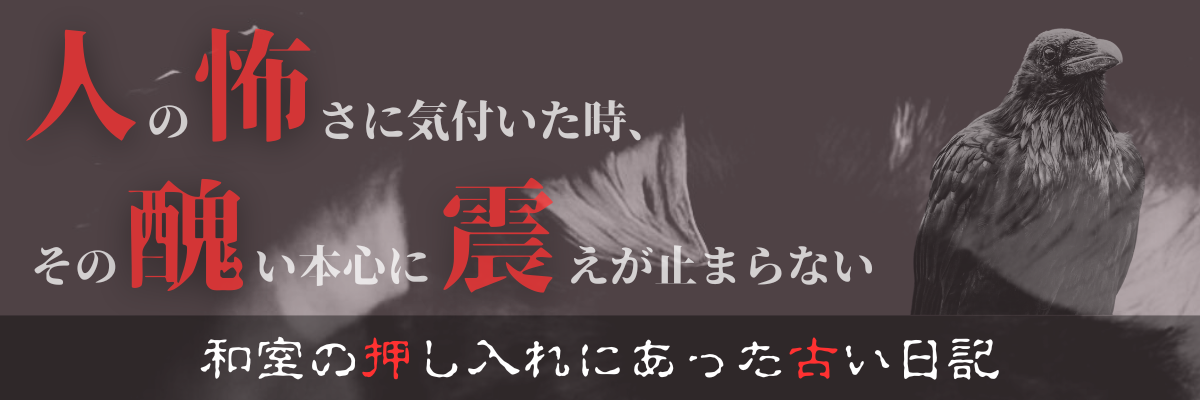




コメント