人の為に施しをするのは立派なことだが、心の余裕が無いとなかなか難しい。また、その善意を逆手にとって横行したのが『オレオレ詐欺』や『振り込め詐欺』だ。善人と悪人の境はどこにあるのか。面倒な事に巻き込まれるくらいなら、利己的に生きて干からびた心を潤す何かを探すべきか。
この話は、『人の為に』と思った行動が思わぬ事態に巻き込まれてしまった青年の話だ。
若夫婦の隣人
東京都板橋区の商店街で、ゴミ拾いのボランティアに汗を流しているのは、今年34歳になる有吉 守(ありよし まもる)だ。時代の変化と共に商店街が衰退し、それに伴ってゴミのポイ捨てや、利用マナーの悪化が小さな社会問題になっていた。守は、少しでも自分が育った町の為になればとボランティア活動には積極的に参加していた。
守がボランティア活動やチャリティーに積極的なのは理由があった。それは両親の影響だ。両親は守が20代の時に亡くなったが、守が幼いころから慈善活動を精力的に行い、両親の葬儀に参列した人から多くの感謝の言葉を掛けられた。そんな両親の残した想いを引き継ぐためにも、守は自分に出来る範囲でボランティア活動を続けていた。
守の自宅は両親から相続した一軒家だった。決して大きな家ではないが、一人暮らしの守にとっては十分であり、何よりも家賃がかからない分生活は楽だった。そんなことも相まって、ボランティア活動が続けられていた。
ある日、守が庭の手入れをしていると、隣の空き家に一組の若い夫婦が不動産屋に連れられて内見に来ていた。恐らく大学を卒業したくらいであろうその夫婦は、仲良く寄り添いながら、これから自分たちの新居になるかもしれない空き家に目を輝かせていた。守の目に留まったのは、妻のお腹が大きかったことだ。
『こんにちわ、少しお話伺ってもよろしいですか?』
旦那のほうが守に話しかけてきた。手を止めて、守は軽く会釈をすると、旦那は守に対して周囲の生活環境について質問してきた。どうやら二人は群馬と埼玉の出身らしく、都会での本格的な生活は初めてらしい。まもなく出産も控えているのでという事で、スーパーがどこにあるとか、駅までのバスは何を使うとか、他愛もない世間話をした。
『私は子供の頃から住んでますが、徒歩圏内で環境は整っているのできっと住みやすいと思いますよ。だからと言って、駅前にみたいにごみごみしていないので、きっとこれから生れてくる赤ちゃんにも良いと思います。』
守は頼まれてもないのに丁寧に近隣状況を説明し、夫妻にとってポジティブな点を説明した。一通り聞いて納得したのか、夫妻は空き家を購入するような話をしていた。守は一人暮らしの時期が長かったので、隣に歳の近い夫婦が住むことになるというのは悪い気はしなかった。
3日後、引っ越し業者が挨拶に来た。住宅街の道が狭く、しばらくの間車を停めるからという事だった。守は先日の夫婦の事だと勘づいたので笑顔で対応した。外に出てみると、やはりあの若夫婦の引っ越しの様で、守に気付いた夫婦が頭を下げてこちらに近づいてきた。
『先日はありがとうございました。お隣に引っ越してまいりました大森と申します。改めてご挨拶には伺いますが、これからよろしくお願いします。』
若者にしては随分丁寧だと思った守に、二人は簡単に自己紹介した。
旦那は大森 新平(おおもり しんぺい)、妻は大森 玲子(おおもり れいこ)。大学の同級生だった二人は長い間付き合っていたらしい。旦那の父親が不動産屋をしており、その伝手で今回の空き家を紹介された。一軒家ではあるが比較的家賃が安く、旦那の給料と両親からの多少の援助で生活できるという事、妻がまもなく出産予定の為、旦那の会社から近いこの土地であれば、何かあればすぐに帰って来れるというのが決め手になったらしい。
大森夫妻は、最近の若者には珍しく、律儀に近所の家々に挨拶回りをしていた。守が普通に生活しているだけでも何度かその姿を見かけたのだ。ある日守が仕事から帰ると、いつものように大森夫妻は近所へ挨拶回りをしている途中だった。ふと目が合った守が会釈をすると、奥さんの玲子が駆け寄って守にこんな話をした。
『こんばんわ。お仕事お疲れ様です。ちょっとお伺いしたいのですが、近所に神社はありますか?』
唐突な質問に守は面食らったが、歩くと10分くらいのところにある小さな神社を玲子に教えた。すぐに旦那の新平があとから駆け寄って『玲子、やめろよ。変に思われるだろ。あ、妻が変な事聞いてすみません。』と守に頭を下げた。『いやいや、お子さんも産まれるみたいだし、お参りかなんかですか?』守は何気なしに聞いてみた。すると、夫妻は少し奇妙な話を守るに話して聞かせた。
実は、夫妻がここへ越してくる前に奇妙な体験をしているという。何でも玲子が住んでいた借家で起きた話らしい。その奇妙な体験の後分かったとこで、どうやら新平は呪われているらしく、子供が生まれるとその子供を新平が殺してしまうという言い伝えになっているようだ。守は少し笑いながら話していたが、夫妻の真剣な話振りに口元を右手で隠した。
『僕はそんなことあり得ないって話しているんですが、妻が以前の借家の大家さんと仲が良くて。で、実はその大家さんが僕の祖母だったっていうことが後でわかりまして』
祖母だと知らずに住んでいた家で奇妙な体験をし、その大家から聞いた話が京都に伝わる伝承で、親が子供を殺してしまう呪いがかかっているとか。そして、今現在で言うとその対象になっているのが旦那の新平であるというのだ。そのため、神社やお寺でお払いがしたいというのが妻の玲子の言い分だった。
守はどう返事をしたらいいか分からず戸惑っていると、『夜分に変なことをお尋ねして申し訳ありませんでした。教えていただいてありがとうございます』と言って二人は自宅へと入っていった。
守はモヤモヤした気分にはなったが、夫妻が変わった夫婦だという印象が強くなった。守は自室に入ると、先日奮発して購入した55型の液晶テレビの電源を入れ、録画しておいたホラー映画を鑑賞しながら酒を飲んだ。
起こってしまった悲劇
それからしばらくというもの、大森夫妻とは会えば挨拶する程度で、それほど頻繁にやり取りするわけでもなく、所謂隣人としての関係が続いていた。それでも、人の良い守は夫妻が困っていることがあれば自分に声を掛けやすいようにと、愛想良く接していた。新平と玲子もそれを快く思っており、昔からこの土地に住んでいる人が多く高齢者の多い地域で、守の存在をありがたく思っていた。
新平と玲子の間に子供が生まれた。数日の間は親や親戚がたくさん集まって、大森家は賑わっていた。女の子らしく、名前は『恵美』と名付けた。微笑みを絶やさず、恵みを施す心の美しい人になってほしいという願いが込められているらしい。両親の愛を一身に受けて恵美は順調に成長し、6か月検診を終えたと先日玲子から聞かされていた。
守は未婚であり、当然子供を育てた経験が無かったので、出産祝いもベタにオムツをプレゼントしたが、ボランティア活動でたまにもらうレトルト食品などを大森夫妻に譲っていた。子育てに忙しく、食事を作ることも大変なことがあるだろうという、守なりの気遣いだった。夫妻はそれをたいそう喜んでおり、深く感謝していた。
そんなこともあり、大森夫妻とはたまに食事に行ったり、夫妻誘われて手料理をご馳走になったりと以前に比べると頻繁に交流を持つようになった。ある日の昼下がり、守が庭の草むしりをしていると、玲子が恵美を抱っこして庭で日向ぼっこをしている姿を見かけた。汗をかいている守に対して『麦茶でもいかがですか?』と玲子が話しかけてきたので、守は手を止めて大森家の庭へ入った。
冷えた麦茶は守の喉を潤した。それと共に守は、前から気になっていた事を玲子に聞いてみることにした。
『そういえば、以前にお話ししていた神社行かれましたか?』
『ええ、その節はありがとうございました。』玲子は恵美を抱きながら、守に対して軽く頭を下げながらそう言った。
『で、その後どうですか?』守は麦茶の入ったグラスを縁側に置きながらそう言った。
『そうですね・・・今のところは・・・』含みのある言い方で玲子がそう話すと、『あまり考え過ぎても良くないですよ。恵美ちゃんもこんなに元気ですし、旦那さんも例の話のような人には見えませんからね。』守は本心からそう言った。しかし、1週間後にその発言が後悔に変わるとは夢にも思わなかった。
守は早朝から駅前の掃除のボランティアに参加して、お昼過ぎに帰宅し昼食を済ませると、2階の寝室で昼寝をしていた。窓からは心地よい風が入ってきて、守の疲れた体を癒していた。夢見心地で横になっていた守は、耳に入ってきた声にベッドから飛び起きた。
『ギャーーーーーーーー!!!!!!』
女の悲鳴というか叫び声というか、なんとも形容しがたい声が聞こえた。それは大森夫妻の家の方からだった。夫妻の家は、住宅並びの一番端に位置しているので、恐らく自分の家にしか聞こえていないだろうが、間違いなく何かあったのではないかと守は思った。とりあえず玄関の姿見で寝癖が無いかだけ確認し、大森家の玄関を叩いた。
『大森さん?大丈夫ですか?何かありましたか?』
応答は無かったが、家の中からは玲子と思われる泣き声と、それを宥めるような、それでいて動揺しているような新平の声が聞こえている気がする。悪いとは思ったが、守は鍵のかかっていなかった玄関を入って中へ上がった。
『無断で入ってすみません。何かあったかと思って来てみました。どうされま・・・』
守は最後まで言い切らないうちに事態を悟った。守が観たのは、ベビーベットの横でぐったりとした恵美に覆いかぶさって泣き喚く玲子の姿と、動揺して腰を抜かした新平の姿だった。恵美は顔が内出血で腫れており、恐らく重篤な怪我をしていると思われた。守はすぐさま救急車を呼んだ。
5分ほどで救急車が到着して、恵美と夫妻は病院へ向かった。守もタクシーを捕まえて、夫妻が向かった中央病院へ急いだ。病院へ到着すると待合室には新平が項垂れており、恵美の名前を叫びながら髪を振り乱す玲子の姿があった。守に気付いた新平は向き直ると、頭を抱えながら守に対して自分の隣のソファーを促した。
ポツリポツリと新平が語った話によると、昼食を食べた夫妻は育児に家事に疲れており、居間でウトウトしてしまったという。玲子の悲鳴で目が覚めた新平は、声のする方を見てみると恵美が床に横たわって白目を剥いていたという。理由はわからないが、恵美はベビーベッドから落ちてしまったらしい。
新平から話を聞いていると、病院の奥から玲子の叫び声が聞こえた。声のする方へ目をやると、玲子が看護師に抱き抱えられながら手術室から出てきた。守は静かに悟って新平を見たが、玲子に駆け寄って暫くした後、声を上げて泣いた。
守はどう話して良いかわからなかった。
先日まで絵に描いたような幸せいっぱいの若夫婦が、今は世界一不幸な顔をしている様に見えた。先日麦茶をもらった時に見た恵美の顔が脳裏にチラついて、守はなんともやるせ無い気持ちになった。
変わっていく妻
恵美が亡くなってからと言うもの、大森夫妻は変わってしまった。特に、妻の玲子は別人の様に疲れた顔をしていた。ある日は一日中泣き喚いていたと思ったら、ある日は庭で恵美をそうしていた様に赤ん坊を抱いてあやす様な仕草をしながらケラケラと一人で笑っていたり。誰の目から見てもおかしくなってしまった。
人間というのは、耐えられない状況に追い込まれると、その状況から逃げるために現実を否定すると聞いた事があるが、まさに玲子は恵美の死が受け入れられず現実逃避をしている様に思えた。少しまともに話を始めたと思ったら、例の呪いの一件の話を持ち出して、あれは事故では無く呪いなんだと言い張った。そんな事が続いたからか、最初は心配して気にかけていた近所の人たちも、次第に距離を置く様になってしまった。
夏のジリジリとした日差しが和らいだ頃、守はいつもの様にボランティアから帰ると夕飯の支度をしていた。一人暮らしの守は、健康のためになるべく自炊を心がけていた。ご飯と味噌汁、おかずを二品テーブルに並べて、スーパーの特売品コーナーにあった刺身のラップを剥がし、あとは醤油差しを用意すればいいという時だった。
『ゴンッ、ゴンッ』
玄関で何か物音がしているのに気づいた。時刻は20時頃だったが、近隣には比較的高齢者が多く、もう外を出歩く人は居ないのがいつもの事だった。誰か来たのかと玄関に声を掛けても応答がない。守は、開けてしまった刺身にラップを被せて玄関まで足を運んだ。
『どちら様ですか?何か御用ですか?』
守が声をかけるが、玄関の向こうから聞こえるのは一定のリズムでドアに何かがぶつかる様な音だけが聞こえていた。ノックしている様な軽い音とは違う。何かもっと重いもの、もしくは大きなもので玄関のドアを叩いている様な感じの音だった。仕方ないので、守はサンダルを右足だけ履いて両手をドアに当てがい、ドアスコープを覗いてみた。途端に、声を上げて驚いた。
小さなスコープから見えたのは、真っ暗な玄関先で頭をドアに打ち付ける女の姿だった。正確に言えば『女の様な何か』が玄関のすぐ近くで頭をしきりに打ち付けている。ちょうどお辞儀をする様な間隔で何度も何度も玄関にゴツンゴツンとやっていたのだ。守が玄関ポーチの明かりをつけると、それが玲子だという事がわかった。
守は、こんな時間に玲子が何か用があるのか、そして何をしているのか聞いてみる必要があると感じて、内開きの玄関をそーっと開けた。玄関のドアが開くと、そこに立っていたのはやはり玲子だった。玲子は守が玄関を開けるとさっきの気味の悪いお辞儀の様な仕草を止めてこう話始めた。
『うちの子が・・・こちらに来てませんか・・・きっと、お宅にいるんじゃないかと・・・思って・・・』
『うちの子』というのは、ペットを飼っていなかった大森夫妻にとっては『恵美』を意味すると守は直感した。そして、居るはずもない恵美が自分の所へ来ている訳が無いという事を、どうやって伝えようか迷っていた。酷くやつれて幽霊の様な出立ちの玲子に、守は意を決して話し掛けようとしたが、玲子がまた意味のわからない事をポツリポツリと話始めた。
『一緒に見つけて欲しいんです・・・きっとどこかにいるはずだから・・・』
一定のトーンで、低く枯れた声でそう話す玲子の姿に、守は『とりあえず今日は遅いし、また明日お話伺いますから』と曖昧に答えた。すると玲子はゆっくりとその場で振り返って、守に背中を向けながら夜の闇の中に歩いて行った。困ったもんだなと守は思ったが、不意に、晩夏の夜にも拘らず、少し冷たい風が入ってくる様な気がして、静かに玄関のドアを閉めた。
リビングに戻って夕飯を食べようと腰を下ろした守だったが、乾いてしまった刺身を食べる気にならず、味噌汁とご飯を二口ほど食べた後、残りは冷蔵庫にしまった。
玲子が夜に訪ねて来た3日後、守の家の電話が鳴った。夕方のニュースを食い入る様に見ていた守は少しビクッとしながら立ち上がると、咳払いをして受話器を取った。電話の相手は玲子だった。『どうされましたか?』という守の問いかけに一切応じず、先日と同じ様に『一緒に見つけて欲しいんです・・・きっとどこかにいるはずだから・・・』と繰り返した。流石の守もどうしていいか分からず、『大森さんしっかりしてください!』と声を掛けると、電話はプツッと切れた。
怯えた顔の新平
玲子からの電話はあれから無かったが、とうとう庭で玲子を見かける事もなくなったので、守は少し心配だった。自分は結婚も子供も経験はないが、小さい頃に飼っていたハムスターが死んだ時には、心にポッカリと穴が空いてしまった様な虚無感を感じたものだ。それが、最初の子供で若い母親となれば、おかしくなってしまうのも無理はないと思った。しかしながら、あの玄関に頭を打ち付けている様子と、念仏の様に呟く玲子の様子は異様なものがあった。
暫くの間、仕事へ出かける時もボランティアへ向かう時も、大森夫妻を見かけることは無くなった。ある日の仕事帰りに守が自宅に向かって歩いていると、大森夫妻の家の前にしゃがみ込んで頭を抱えた新平の姿が見えた。自宅のすぐ目の前でしゃがんでいる新平の姿に違和感を覚えたが、守はゆっくり近づいて声を掛けた。
『大森さん、どうかされましたか?』
守に気づいた新平は、少しだけ頭を持ち上げて上目遣いに守を見遣った。その顔は、以前玄関のスコープから見た玲子の様に、ゲッソリと痩せて別人の様に疲れた顔をしていた。目は虚ろで焦点が定まっておらず、唇は小刻みに震えていた。一向に答えない新平を気遣って、守は膝を折り新平に話しかけた。『大森さん、大丈夫ですか?』守が改めて声を掛けると、新平は枯れた様な声でこう話した。
『あれから、妻もおかしくなっしまって。それからというもの・・・私も、もう耐えられないんです・・・。』
何かに怯えた様に小刻みに震えていた唇を小さく動かして新平は話した。すでにその震えは体全体にまで広がっていた。守は立ち上がって、『少しの間、ウチでゆっくりしてください。』と言って新平の肩に手を置いた。今は、新平と玲子それぞれが、自分の心の整理をすべきだと思ったからだ。とりあえず新平は自分の家に置いて、暫くしたら玲子の様子を見に行こうと思っていた。
家に上げた新平は尚もブルブル震えていたので、守はお茶を入れて新平に差し出した。普段、人の為になればとボランティア活動をしている自分が、これだけ疲労困憊した様子の新平を目の前に、掛ける言葉もない状況に守は唇を噛み締めた。『色々大変でしたよね。』と当たり障りない言葉をかけながら、和室を好きに使ってくれていいと新平に話した。
新平は会社も休んでいるらしく、あれから2日が経ったが、守の家から出ることはなかった。それどころか、あてがった和室の押し入れに向かって何やら念仏の様な言葉を言っているのを何度か見かけた。きっと恵美の写真が見えたから、仏壇代わりにしているのだろうと守はそっとしておくことにした。守が休みの日に、珍しく新平が縁側に腰掛けて外を眺めていた。守は声を掛けてみることにした。
『具合はどうですか?』
新平はほんの少し唇を動かした様な様子だったが、声は聞こえなかった。守は、玲子の様子が気になっていた為、新平に尋ねてみた。
ほとんど聞き取れない声だったので守の想像も多分に含まれるが、恵美が亡くなった後半狂乱になってしまった玲子は、家の中でも奇行が目立つ様になったという。また、例の呪いのせいだと言って自分に食ってかかる事もあり、流石に精神的に参ってしまったとか。自分も娘を失った悲しみを抱えながら、自暴自棄になった妻を支えていく事に限界を感じていたらしい。次第に変わっていく妻を見ていると、苦しさよりも恐怖が強くなり、頭を抱えて自宅の外に出たのが先日の出来事の様だ。
新平の唇が動かなくなったのを確認して、守は玲子の様子を見てくると新平に告げた。ところが、新平はそれを頑なに止めようとして守の腕を掴んでこう言った。
『今は、自分と一緒にいてください!一人になったら、もう、どうにかなってしまいそうで・・・』
新平のあまりの表情と今まで聞いたことのない声の大きさに守は戸惑いながらも『わかりましたから、落ち着いてください。』と新平を諭した。すぐ隣の家なので、タイミングを見て玲子の様子を見にいく事もできたが、その間に新平に何かあったら、それはそれで厄介だ。新平と玲子に対する板挟みの中で、守は今後どうしたら良いのか分からなくなりそうだった。その夜は、窓の外で蟋蟀(こおろぎ)が鳴いていた。
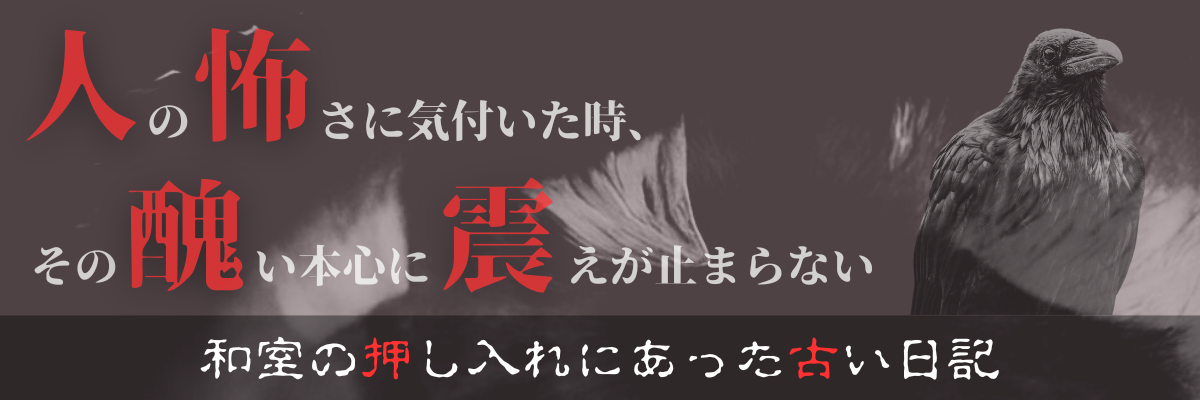





コメント