時代の波にのまれて生きるために藻掻いていた青年は、隣人の笑顔が心の支えだった。ふとした瞬間に声を掛けられることが、自分が生きている証明にとなり、社会の狭間に失いかけた自我を取り戻させていた。
しかし、気になり始めた隣人の生活音や違和感が青年を恐怖のどん底へ落とすこととなる。これは、そんなお話。
ロストジェネレーション
時は2000年代に入ったころ、『ハッピーマンデー』が導入され、月曜日の祝日が多くなった頃の話だ。携帯電話にインターネット機能が搭載されてコミュニケーションの幅が広がりつつある中、都内を中心に路上喫煙禁止条例が制定され始めた。新たな時代の幕開けに社会も人も変化しようとした時代だった。世界に目を向けると、『アメリカ同時多発テロ』が発生し、まるで怪獣映画のワンシーンのような現実とは思えない光景が全世界に発信された。
時代の変化には歪みや淘汰がつきものであり、携帯電話の普及は人々のコミュニケーションを変化させたが、詐欺被害の拡大にもつながり大きな社会問題となったのは周知の事実だ。また、バブル崩壊後の日本経済は幾度となく経済危機を迎えており、所謂『就職氷河期』と呼ばれる時代でもあったのがこの時代を象徴する出来事だろう。
定職に就けず、日雇いやアルバイトで何とか生活を維持して、親や親戚に顔向けできない若者が増え、職安には連日長蛇の列が出来た。若者たちが選んだ選択ではない。時代がそう流れたのだ。多くの若者がこの激流に流されて、後に『引きこもり』や『5080問題』へと関連していくこととなる。
『はい、次の方どうぞ』
あちこちで職を求める長蛇の列が出来る中、ようやく自分の番を迎えた青年が居た。落合 航(おちあい わたる)という名前だった。前の順番だった男性がまだ相談カウンターに居座っていたため航は少し戸惑いながらもカウンターが空くのを待っていた。係員に促されようやく男性はおもむろに腰を上げ、航に鋭い眼光で睨みつけながらカウンターを後にした。
『あ、落合さんですね。先週の結果出ましたよ』
流れ作業で書類を受け取ったカウンターの女性は、航に目も合わせずにそう告げた。航は大学を卒業して就職試験を受けたが、時代の波にのまれて定職に就けずにいた。先週紹介された工場派遣の仕事に応募して面接結果を聞きに来たのだ。車の免許を持たない航は、自転車で通勤が出来る範囲で職を探していたため、それがネックでなかなか仕事先が見つからず、バイトと職安を行き来していた。
『とりあえず来週から来てくださいとのことですので、この書類に目を通しておいてください。明後日先方から電話が来て、詳しい話があると思います。よろしくお願いします。』
カウンターの女性はなおも目を合わせずに書類の束を航に差し出して、終了時刻になった役所のように『以上です』と航に告げた。書類を受け取った航は、これだけの話ならここに来る必要もなかったのではないかと思いながらも、今後のために深々と頭を下げてその場を後にした。
航は自転車に乗ると、7月の晴天の中汗を流しながら自宅へと急いだ。とりあえず仕事が決まってよかったとは思ったが、工場勤務という事は肉体労働が待っているわけで、運動靴とか軍手とか必要なものを揃える必要があり、多少の出費が嵩むことが気がかりだった。
航の自宅は2階建てのアパートで1階と2階にそれぞれ3世帯が住めるアパートだった。家賃は33,000円と安いが、ボロアパートという訳ではなかった。航には家賃が安い理由は分からなかったが、親からの仕送りも含めてギリギリの生活で、食事は毎日1食しか食べない日々が続いていた。先日まで勤めていた印刷会社の仕事は、空腹によって集中力が途切れ致命的なミスをしてしまった。そのせいでクビを言い渡され、日雇いの仕事や短期のアルバイトで食い繋いでいたのだ。
そんな航にも一つだけ生きる糧があった。それは、2階の中央に位置する航の部屋の左隣に住んでいる若いシングルマザーの存在だ。航のアパートは1階の端の部屋に大家が住んでおり、航とシングルマザー以外は住民が居なかった。いつも赤ん坊を連れて玄関先から見える景色を眺めていることが多かったが、ちょうど航が自宅から出かける時間に重なることが多かった。
その都度『いってらっしゃい』とか『ご苦労様です』と声を掛けてくれることが、苦しい生活の中で航に生きる活力を与えていた。松島 恵那(まつしま えな)という名前で容姿も航の好みだったという事をひた隠しにしていた。
玄関のドアを開けると、航は四畳半の部屋に腰を下ろして職安で受け取った書類に目を通した。日勤と夜勤の二交代で2勤1休というスケジュールだった。1か月に1度だけ第3日曜は休みになるようだ。給料は手取りで17万円。なかなかの薄給だったが、毎日の生活にも困っていた航にとっては選択肢はなかった。2日後、職安で言われた通り勤務先の工場から電話があり、作業服は支給されるためそれ以外のものは準備するよう告げられた。
人生計画
何とか二交代のきつい仕事にも慣れてきたころ、航は仕事から帰る途中で近所の書店に立ち寄った。雑然と並べられた本棚を目を凝らして航が探していたのは、『宅建資格』の参考書だった。
航は就職こそ失敗したが、勉強は出来ないわけではなく、自分なりに今の生活を変えるために色々と考えを巡らせていた。宅建資格を取得しようと思ったのは、不動産業界に潜り込めればある程度安定するだろうという事と、資格を持っていれば食い逸れることはないだろうと踏んでいたからだ。
資格の参考書の棚である本が目に入った。それは福祉関連の参考書だった。航は大学時代に、福祉関連の仕事に就こうと思っていた。具体的に言えば、老人ホームや保育所、幼稚園などの仕事に就くはずだった。そのためにたくさんの勉強をして自分なりに努力をしていた。
しかしながら、資格試験に合格できなかった事、資格が無くても出来る仕事は就職倍率が高く、航はその競争に漏れてしまった。福祉関連以外は殆ど興味が無かったので、他の業界にシフトすることが出来ず無職になってしまった。航はその福祉関連の参考書を手に取って、以前自分が勉強した内容に目を通していた。
航が福祉関連を目指したのは理由があった。
中学の頃に仲の良かった友達の兄が言語障害を持っていた。友達の家に遊びに行くと、兄も一緒に遊んでいて仲が良かったが、その友達の兄が学校でのいじめを苦に自殺したのだ。障害で苦しんでいた友達の兄の無念を考えると航は胸を締め付けられる思いだった。
それからというもの、航は福祉関連の仕事を志すようになった。過去の記憶と自分の人生計画に浸っていると、壁に貼られた『立ち読み禁止』のポスターが目に入った航は、周りを気にしながら本を閉じて、宅建の参考書を手にレジへと向かった。
仕事の合間を縫って宅建の勉強をするのは簡単なことではなかったが、航は今の生活から抜け出すには資格取得が一番の近道だと信じて疑わなかった。休みの日には4時間、仕事がある日でも1時間は勉強を欠かさずに行っていた。それもこれも全てはは今の生活から抜け出したい一心だった。
しかし、そんな航のやる気が裏目に出た出来事があった。工場で作業中に大事な部品を落として壊してしまったのだ。上長に叱責され酷く落ち込んだ航は平謝りしたが、責任感が足りないと指摘され、即日解雇を命じられてしまった。
当時は就職難という事もあり、求人業界は買い手市場だった為、起業は何かにつけてクビ切りを行っていた。航のミスもそれほど大したことでもなかったが、人員削減が目的だった。
『またか』と深くため息をついて肩を落とした航は、明日から無職になる現実と、もう使わないであろう軍手や手ぬぐいを抱えながら、自転車を押して自宅へと歩いて行った。さすがにこれ程までにうまくいかないと、自転車に乗る気力さえなかった。
帰る道すがら、向こう側から自転車に乗った男性が走ってきた。航は端っこに避けてやり過ごそうとしたが、すれ違う際に男性は『邪魔だよ!』と吐き捨てて走り去った。
『俺だって好きでこんな所歩いてるわけじゃないよ。』
航は誰に言うでもなく独り言を呟いた。まだ時間は16時ごろでオレンジ色の西日が航の影をアスファルトに長く長く映していた。
自宅のアパートに到着すると駐輪場に自転車を停めて、溜息をつきながら荷物を抱えて歩き出した。ふと目線を上げると、恵那がいつものように玄関先で遠くの町並みを見つめながら赤ん坊を抱いている姿が目に入った。恵那は出産した後とは思えないほど細く、綺麗な女性だった。セミロングの髪にハッキリとした二重で、色白の肌にはえくぼが印象的だった。
『お疲れ様です。どうされたんですか?何となく元気がないようですけど。』
『いやぁ・・・実は仕事をクビになっちゃいましてね・・・』
『あら、そうだったんですか。今日はゆっくり休んで明日からまた頑張ればいいじゃないですか。そんなに落ち込まないでくださいね。』
優しい恵那の言葉が航の心に響いた。第三者目線で考えれば恵那の言葉は無責任にも取れたが、憔悴しきった航には、恵那の優しい一言が今日起きた悲劇を一瞬にして振り払ってくれるかのように思えたのだ。恵那の腕には赤ん坊がスヤスヤと眠っていた。
『そう言えば、赤ちゃんいつも大人しくていい子ですね。』
航は恵那に語り掛けた。しばらく隣に住んでいるが、赤ん坊の夜泣きを聞いたことが無かった。玄関先で恵那を見かける時にも赤ん坊はいつも大人しく寝ていたので、福祉関連の勉強をしていた航にとっては珍しい子供だなと思っていたのだ。
『ええ、うちの子泣かないんですよ。ずっと寝てるので助かってます。』
満面の笑みで赤ん坊に頬ずりする恵那は、西日を背に受けてまるで聖母マリアの様に航には感じられた。
玄関の扉を閉めると、職を失った航は、日雇いで出来る仕事を探そうと朝刊に入っていた広告を隅から隅まで調べてみた。大学を卒業したばかりの航は体力には自信があったため、日雇いならとりあえずすぐに仕事が出来ると思っていた。その時広告に書いてあったのは、工場の警備員やショッピングモールの誘導スタッフ、工事現場の棒振りの仕事などが目についた。
恐らく申し込めば断られることはないだろうが、いづれも単発の仕事が多く、長くても3日間だけの仕事というのがほとんどだった。仕方ないと思いながらも、また時間を見つけて職安へ行く必要があるなと航は感じていた。広告をテーブルの上に乗せて、狭い部屋の中へ寝ころんで天井を見上げた。なぜ自分がこんな状況になってしまったのか。航は大学時代の事を思い出していた。
大学時代にもバイトはしていたが、授業とバイトとそれなりに楽しんでいた。友達とは将来について語り合ったこともあった。終電を逃せば友達の家に寝泊まりすることもしばしばあった。
それが今はどうだろう。『社会人』という自然と意識に入り込んでくるレッテルが、今の自分を蔑んだ存在にしているように思った。就職試験だって怠けていたわけじゃない。仕事もクビになってしまったが、手を抜いていたわけじゃない。きっと、何かタイミングが悪かったんだ。航はそう思うしかなかった。
ふと、玄関先で聖母マリアに見えた恵那から掛けられた言葉が頭の中でリフレインした。
『明日から頑張ればいいじゃないですか。』
『そうだ。今日はもう休もう。少し体を休めて、気が向いたら資格の勉強でもすればいい。立ち止まっているわけじゃないんだ。自分の将来の為に、出来ることを精いっぱいやっている中で、失敗しない人間なんかいないんだ。今俺に出来ることは、明日から頑張る事なんだ。』
狭い四畳半の部屋の中で寝ころんだ航は、自分に問いかけるように独り言を呟きながら、いつしか眠ってしまっていた。
資格勉強
ザーッと言う夕立の音で航は目が覚めた。開けっぱなしの窓からは少し雨が吹き込んで、テーブルに置いたままの求人広告が濡れていた。航は寝ぼけた目を擦りながら立ち上がると、夏の雨の匂いが吹き込んでくる窓を急いで閉めた。
ふと時計を見ると、自宅へ帰ってから間も無く2時間が経とうとしていた。随分寝てしまったと思った航は、夕飯の準備をする前に少し資格の参考書を開いて勉強しようと思った。食事をしてからだと眠くなるし、思ったよりも寝起きで頭が冴えている気がしたからだ。
テーブルに参考書を広げて大学ノートに板書をしながら、前回の勉強の復習をした。宅建の資格試験は3つの難関が存在した。それは『出題範囲が広い事』『事例式の出題形式』『高水準の合格ライン』だ。特に一つ目と二つ目は勉強する上では対策が難しく、合格率は15%前後と言われていた。
航はこの点に注意しながら勉強していたが、『都市計画法』と『税法』の部分がなかなか頭に入らなかった。非常に難易度の高い科目ではあるが、だからこそ航は自分の人生を変えるために、必死になって勉強していたのだった。
その日はいつにも増して参考書の内容が頭に入らなかった。内容が難しいわけでもなく、頭が冴えていると思ったのにも関わらずだ。と言うのも、隣の恵那の部屋から何やら物音が聞こえ始めたからだ。何の音か最初はわからなかったが、次第に航は勉強の手を止め、その音のする方向へ自分の意識を集中させた。
『カリカリッ、カリッ、カリッ。カリカリ』
何かを引っ掻くような、それとも齧るような、ネズミでもいるのではないかと思うような軽い不規則な音が恵那の部屋の方から聞こえてきた。ネズミではない事はよく分かっていた。何故なら、大家が大の動物嫌いで、特にネズミが嫌いらしく、アパートの周りに大量の殺鼠剤を撒いていたからだ。
だとしたら、この音の正体は何だろう。航は気になって気になって仕方がなくなってしまった。今すぐ恵那の部屋に訪ねて行っても良かったが、もう19時になろうかと言う時間だったので、不謹慎だと思われたくなかった。
耳を澄ましていると、違う音が聞こえてきた。それは赤ん坊の泣き声のようにも聞こえた。ただ、『オギャー』というよくある赤ん坊の泣き声とは違って、一定のリズムで規則正しく聞こえてくるのだ。
『隣の赤ん坊は普段泣かないし、今までもこんな感じで泣く声は聞こえてこなかったな。』航は独り言のように呟きながら、尚もその音の正体を探ろうと、とうとう耳を壁にくっつけてみた。その瞬間、航は少し妙な感覚を覚えて身を竦ませた。
先程まで聞こえていたカリカリと言う音も、赤ん坊のような泣き声もピタリと聞こえなくなったからだ。『どう言う事だ?』と思った航は壁から耳を離してみた。すると、先ほどと同じようにカリカリと壁を引っ掻くような音と、赤ん坊の泣き声のような声は微かに聞こえているのだった。
航は気味が悪くなって、壁から離れると、小さな部屋の中で一層小さなテレビの電源を入れて、ゴールデンタイムのお笑い番組の音で部屋の中をいっぱいにした。
翌朝、航は昨日の奇妙な音の件はすっかり忘れて、職安に出かける準備をしていた。職安はほとんど役所のようなところだったので、8時45分から受付をしていた。それに間に合うように、8時半には到着出来るよう自宅を出ようとしたのだ。
昨日のような夕立に降られたら困ると思った航は、窓を閉めて戸締まりを確認した。リュックに水筒と昨日の晩御飯の残りで作った弁当を入れると、玄関のドアを開けて鍵を閉めた。ふと目をやると、恵那が玄関先に赤ん坊を抱いて立っていた。
あの奇妙な音の件を思い出した航は、恵那に話しかけてみることにした。『あ、おはようございます。ちょっと変なことを伺いますが…』航は申し訳なさそうに声をかけた。すると、恵那はいつものにこやかな表情をしたまま、次のように答えた。
『昨日の夜ですか?いや、そんな音が出るようなことはしてませんけど。ウチの子も、ご存知の通りずっと寝ているので泣いたりはしてないですし、何かの聞き間違いではないですかね?』突っぱねる恵那に、音の詳細を恵那に話して聞かせた。
『あら、きっと勉強の頑張りすぎじゃないですか?少しお休みになったらいかがですか?』
優しく微笑みながら恵那にそう言われた航は言い返すことができず、自分の思い違いかもしれないと話して一礼をすると、駐輪場に向かい職安へと自転車を走らせた。
拭えない異変
恵那と立ち話をしていた航は、予定していた時刻よりも遅れて職安へと到着した。職安の駐輪場から入口の方を見ると、すでに入口の外まで受付の列がはみ出していた。
『こりゃ参ったな』と思った航は、近くの喫茶店で時間を潰すことにした。朝イチの順番待ちに遅れてしまうと、それ以降はほとんどいつ行っても待たされるし、待ってる間はどこにも行けず立ちっぱなしであることを最近の職安が良いで心得ていたからだ。
喫茶店に入った航は、290円の一番安いアイスコーヒーを注文して、リュックに入れておいた資格の参考書を取り出してノートと見比べながら読んでいた。秋口のホオズキのような色をした店内の明かりは、本を読むには少し暗く、すぐに航は参考書とノートをリュックへしまった。
咽せ返るような煙草の匂いと独特の湿った空気が、特にやることのない航を微睡の中へ吸い込みそうになったが、瞼が重くなるたびにアイスコーヒーへ手を伸ばして、10時を過ぎるまで航は何とか耐え切った。
会計を済ませて外へ出ると、電信柱にアブラゼミが勢いよく鳴いていた。もうそんな季節かと航は思った。仕事を探し始めてからもう半年が経つ。今度こそ継続して勤められる仕事を探さなければと航は思った。
喫茶店を出た後すぐに職安へ向かったが、受付を済ませて窓口へ通されたのは11時20分を回った頃だった。資格の参考書を持ってきていた航にとっては時間を有効活用することができたが、いつにも増して職安は定職を求める人でごった返していた。
受付で聞かされた話では、夏場になると力仕事をしていた人が辞める割合が増えることと、ボーナスをもらって辞める人が増えるため、8月のお盆の時期までは大変な混雑が続くと言うのだ。逆に言えば、職のポストは空きが出るので狙い目であると言うことも言えるのではないかと、航は分析した。
先日紹介された会社をクビになったので、窓口の係員からは散々嫌味を言われたが、航はとりあえず新しい職場の面接を設定してもらえることになった。継続して資格の勉強をしており努力をしていると言う点と、何よりも大学を卒業したばかりであると言う年齢が航の強みとして認められていた結果だった。
書類をもらって自宅へ到着したのは、もう15時になろうかと言う時間だった。昨日帰宅した時間と同じだったが、昨日と違ったのは、恐らく今日は夕立はないだろうと思える天気だったことだ。だとすれば、締めっきりにしてきた自宅の中は、強烈な暑さになっているのではないかと航は考えた。
玄関を開けて一番に窓を開け、荷物を小さな部屋の隅にまとめておいた。職安でもらった書類をテーブルに置いて、冷蔵庫から麦茶を出してコップに注いだ。長い時間職安にいたので一息入れようと、生暖かい風が入ってくる窓のところへ立って、外を見つめながら麦茶を一口飲んだ。
途端に、航は麦茶を吐き出しそうな感覚に襲われた。
それは麦茶のせいではない。何故ならば、窓から何とも言えない悪臭が漂ってきたからだ。生ゴミのような、何かが腐った匂いだ。小さい頃に金魚を飼っていた。夏場に旅行に出て帰ってきたら死んでいた。その時に嗅いだような屍臭を帯びたような匂いだった。
ほとんど手すりだけのベランダに身を乗り出して匂いの元を探そうとすると、どうやら恵那の部屋のベランダの方から匂ってくるような気がした。昨晩の音といい、この匂いといい、何が起きているのだろうか。まさか、あのにこやかな聖母マリアはゴミ捨てが出来ないダメ女なのか。
定職についたら食事の一つでも誘って、交際でも申し込もうと思っていた恵那が、そんな人だとは航には到底思えなかった。しかし、この匂いは間違いなく恵那の部屋の方から匂ってくるようだった。
窓を閉めれば我慢できなくもないと思った航だったが、窓を締め切りにしてみた部屋はあまりにも高温で一晩過ごせそうになく、仕方なくあの匂いを覚悟して再度窓を開け放った。すると、さっきまで充満していた屍臭のような匂いは少しも残らず消え去っていた。
昨晩の音と、今の匂い。
何が起きているんだと航は不思議に思った。恵那のいう通り自分は疲れ過ぎていて、ありもしない音や匂いに敏感になっているんだろうか。もしかしたら、疲れからくる何かの病気なのだろうか。そんなふうに思えて仕方なかった。
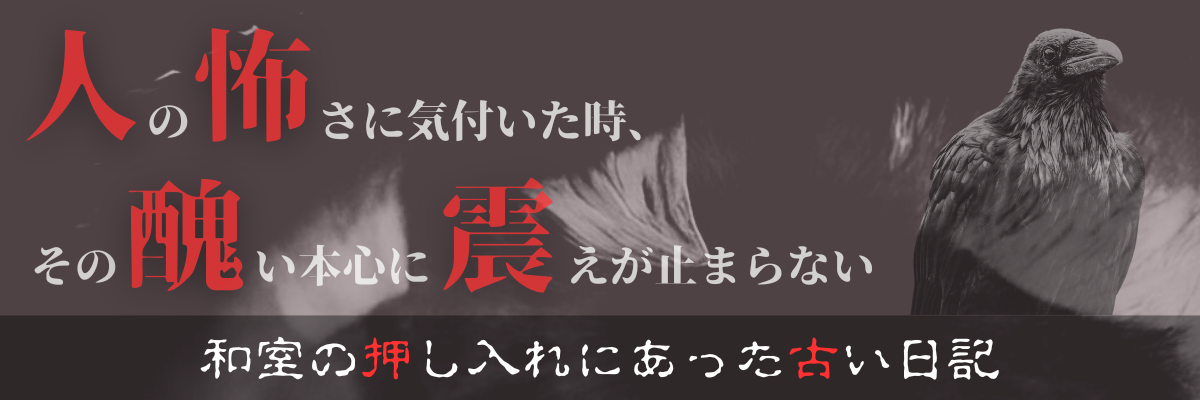




コメント