『いい大学を出て、いい会社に入れば将来安泰』そんな終身雇用神話がまことしやかに囁かれていたころの話。ある一人の女性が新卒入社した会社で体験した信じられないような話。自分ではない誰かが自分に対して危害を加えようとしている時、どのようにして対応したら良いのか。それが生身の人間であれば話し合うことが出来るが、そうでない場合は。
絵に描いたブラック企業
青く晴れた空に桜色のアーチがかかる頃、新潟県の市民会館ではある会社の入社式が行われていた。緊張した面持ちで参加する新入社員達には、入場口で株式会社双葉印刷の社章が配られた。入社式と言っても簡単な会社概要の説明と社長のありがたいお話というお決まりの内容で、先日まで学生生活で浮かれていた若者たちにとっては退屈そのものだった。
まぶたの重さと戦う若者の中でグレーのスーツに身を包み、茶髪の髪を黒髪に染めたばかりの千間 亜衣(せんま あい)は入社式だと言うのに浮かない顔をしていた。その理由は、この双葉印刷の評判だった。亜衣は学生時代に相当遊んでおり、いざ就職活動という段階ではことごとく希望先に断られ続けた。最後の最後で地元の小さな印刷会社であるこの会社の面接に合格し、渋々就職を選んだのだ。
双葉印刷の評判と言えば、安月給に寸志程度のボーナス、長時間労働でパワハラが横行するなど絵に描いたようなブラック企業で有名だった。しかし、先代の社長が一代で築き上げた地元のネットワークを活用し、車で1時間ほどの範囲内の会社ではほとんど双葉印刷で仕事を請け負っており、会社業績としては順調だった。ただ、先代が亡くなり息子が後を継いだころから受注先が減り、現在の体質悪化に繋がっていた。
入社式は終日の日程で進行し、昼食は近所の仕出し弁当が配られた。好き嫌いの多い亜衣は煮物が好きではなかったが、寝坊したせいで朝食を食べ損ねたので、いつもは食べない『がんもどき』を仕方なく口に運んだ。午後は配属先別の説明会があると聞いていたので、さすがに何も食べないで乗り切ることは無理だなと思っていたからだ。
亜衣の配属先は営業部だった。当然特別な資格を持っているわけでもないので、この配属には納得せざるを得なかったが、評判の悪い会社で営業部とくれば、それなりの覚悟が必要だという事は明白だった。同じ営業部に配属となった新入社員は自分を含めて5名居たが、いづれも浮かない顔をした『落ちこぼれ』感が否めなかった。
『皆さんにお願いしたいのは、新規のお客様の獲得業務と、既存顧客先へのルート営業です。』
説明担当らしき女性社員がホワイトボードに書かれた業務内容を指さしながら説明した。ブラック企業には似つかわしくない若い女性で、キラキラとした笑顔で亜衣を含めた5人に向けて説明した。恐らくこの人と会うのは今日が最後で、実際の上司は別の男性なんだろうと考えていた亜衣は、とりあえず説明されている事を手に持った大学ノートにメモした。女性の説明が終わると、別の男性が口を開いた。
『いいですか、営業部ですから甘えは一切捨ててください。』
開口一番厳しい口調で話し始めたのは、営業部長の八木 圭一郎(やぎ けいいちろう)だった。八木は営業部とは何たるか、会社の中で前衛部隊であり、自分たちが会社の利益を支えているんだという事を、自分の武勇伝と共に熱を込めて語った。話の最後には、やる気がないのであれば社章を置いて今すぐ別の採用面接を探しても構わないとまで言い放った。当然席を立つ人間は居なかったが、亜衣は心の中で八木の禿げ上がった頭に社章を投げつけて、カラオケに足を向ける自分を想像していた。
全てのカリキュラムが終了したのは19時を回った頃だった。一番最後に給料の振込先の指定をする書類や、労働契約書などを手渡され、ようやく亜衣は解放された。会社から自宅まで車で15分と比較的近かったが、今日来ている市民会館から自宅までは1時間ほどかかる。今日一日を振り返ってみて、通勤が楽な事が唯一の利点だなと鼻で笑いながら、亜衣は自分の車で実家までの道のりをあくびをしながら運転して帰った。
八木 圭一郎という男
20時を過ぎたころに自宅へと帰ってきた亜衣を両親は夕食を食べずに待ってくれていた。昔からヤンチャだった亜衣の就職を誰よりも喜んでくれたのは他でもない両親だ。母は亜衣が好きなクラムチャウダーを作り、父はいつもの晩酌をせずに居間でテレビを観ていた。亜衣が帰ってくると、両親が顔を見合わせながら、どちらともなく今日の入社式の様子を亜衣に尋ねた。
『うん、まぁ、なんとかやっていけそう。明日も朝早くから研修あるみたいだし。』
亜衣は就職を期に両親には心配や迷惑をかけまいと心に決めていた。だから、今日感じた会社の『ヤバい雰囲気』は言葉にせずに当たり障りなく答えた。当然両親も双葉印刷の話は知っているはずではあるが、とりあえず定職に就けたことを喜んでいてくれたからだ。その後は、ご近所さんの噂話や父の若かったころの話など、『いつもの話』が続いたが、亜衣は明日の研修に向けて22時には床についた。
『亜衣、そろそろ起きなさい。遅刻するわよ。』
次の日の朝、母がイチゴジャムを塗ったトーストとコーヒーを用意してくれていた。亜衣は今まで朝食を抜くことが多かったが、昨日の空腹を思い出し、これからは絶対に朝食を食べてから出社しようと決めていた。父が買ってくれたビジネスバッグには、昨日のうちに準備したノートや筆記用具、ハンカチに化粧ポーチを入れて準備万端だ。
朝の道路は亜衣の予想よりも混んでいた。ただ、自宅から15分の道のりに予定の30分前に出発しているのでそれほど問題は無かった。歩道には学生の集団登校の姿が見え、あれほど校則に縛られる生活が嫌だったにも拘らず亜衣は学生時代が恋しくなったとともに、昨日の営業部長の話を思い出していた。
『いいですか、営業部ですから甘えは一切捨ててください。』
入社初日からあんな事を話すのだから、実際の業務についてはそれなりに覚悟しているつもりだったが、亜衣の予想をはるかに上回る実態が待っていたのだ。
社屋に入ると、昨日の『説明係』の女性が会社の中の案内をしてくれた。待ち合わせ時間を伝えられていたので亜衣を含めた新入社員5人は、揃ってその女性の後をついて回った。一通り説明を終えると、女性はある部屋に5人を案内した後、『それでは』と冷たく言い放ちドアの向こうに消えていった。棒立ちになっている5人がそわそわし始めると、先ほど女性が消えていったドアから八木が入ってきた。
八木の後から3人の社員が入ってきたが、いづれも営業部の先輩だと説明を受けた。今日は朝礼のやり方と具体的な業務の流れについて研修をするという。まずは朝礼のやり方だったが、社訓と、営業部心得、今日の目標を『最大限の大声で』唱和するというのが朝礼のやり方の様だ。新入社員は声が小さいので先輩社員のやり方を見て学ぶようにと八木は5人に言った。
先輩社員の一人が、『では、始めます』と一言言ったと思ったら、そこにいた3人が一斉に社訓と営業部心得を絶叫し始めた。新入社員5人が呆気に取られていると、第一発目の八木の指示が飛んできた。
『おい!お前ら!メモも取らないのは何事だ!社訓を覚えているってことか?だったら一人づつ言ってみろ!』
3人の絶叫をかき消すくらいの大声で八木が怒鳴ると、新入社員は完全に委縮した。先輩社員は『初めての事、分からない事は必ずメモを取ってください』と淡白なの口調で5人に告げた。しばらくの沈黙が続くと、『返事も出来んのか!!』と八木がまた怒鳴った。5人はオロオロしながらも返事をして、なんとか朝礼のやり方を教わった。
亜衣は馬鹿馬鹿しいと思っていたのが顔に出たのか、八木から注意をされると『わかりました』と返事をした。咄嗟に八木が『目上に対しては”かしこまりました”だろ!』と亜衣に対してだけ詰め寄った。亜衣は精いっぱいの声で『かしこまりました』と答えたが、八木は一瞥をくれて気に入らない様子だった。
朝礼が終わった後は、5人に対して3人の先輩が手分けしてチームを組み、1日の業務について細かく教えてくれた。亜衣は自分一人に対して先輩が一人ついてくれたことにラッキーだと思った。マンツーマンで教えてもらえることで、早く仕事を覚えられると思ったからだ。昼食の際にこの先輩と話をしたが、社内でも八木の横暴振りは一目置かれているらしい。
『男女関係なく自分の気に食わないことがあるとすぐに怒鳴るし、相手が逃げられない状況にあればあるほど、その状況を利用して詰問をするという癖があるんだ。』
そう教えてくれた先輩の話によると、以前、部下に対して手を上げたことで減給処分を食らっており今は暴力は無いものの、その分言葉での圧力が強く、辞めてしまう社員も少なくないと先輩社員は教えてくれた。
『え、ちょっと聞いて良いですか?なんで先輩はこの仕事を続けているんですか?』
亜衣は周りを気にしながらもストレートに質問をぶつけた。先輩が言うには、営業部の特徴として目標達成した場合にインセンティブがあるため、基本給は安いが、自分の頑張り次第で給料が増えることがある事、この会社以上にキツイところは無いと思うので、仮に辞めることになってもどこでもやっていける自信が付いたこと、あと2年で八木が定年の為、それまでが一つの区切りだと思っているという事を教えてくれた。
八木が定年間近であるという事は、亜衣にとっても共感できる部分だった。仮にあの感じが毎日続いたとしてもいずれ慣れるだろう。慣れてしまえば最長でも2年続ければ、間違いなく八木は居なくなる。そうすれば、それまで耐えた分、どんな上司になってもやっていけるのではないか。亜衣は食堂で注文した天ぷら蕎麦を食べながらそんな風に思っていた。
拭えない違和感
入社して1か月が経った頃、八木の圧力にも慣れて先輩社員について営業に回るようになった亜衣は、それなりにうまく立ち回っていた。サービス残業や八木の叱責は相変わらず酷かったが、先輩社員に恵まれて、なるべく社内に居なくてもいいようにスケジュールを組んでくれたからだ。無論、社内に居れば『デスクに向かって座っていれば数字が取れるのか!』と八木が激昂するため、殆どの営業は必要最低限しか会社にいる事は無かった。
梅雨の季節が始まりアジサイが咲き始めたころ、亜衣はなかなか営業成績が上がらず苦慮していた。営業エリアの会社は殆ど自社サービスを導入しているため、受注量の増加やサービスグレードの変更などが主な営業内容になるが、先輩社員と同行が終わり一人で営業するようになると、やはりサービス知識の面で不足していることがあり、なかなか実績に結び付けられずにいた。
亜衣が一番嫌だったのは、営業成績が上がらない事よりも、それによって毎日八木に詰められることだった。当然亜衣だけではなく、他の新入社員も同じような状況ではあったが、初日から目を付けられていたのか、八木は亜衣に対してのあたりが強かった。ほかの社員の前で罵倒することはもちろん、亜衣だけを居残りさせて延々と説教することもあった。
ある日に至っては、『お前みたいなカスはいつでも辞めてもらっていい!』と亜衣に書類を投げつけたことがあった。さすがにそれに対して亜衣も反論したが、さらに激昂した八木をほかの先輩社員が押さえつけるような場面さえあった。
いくらヤンチャしていたとは言え、人格や存在を否定されれば亜衣でも傷ついた。その度に先輩社員が声を掛けてくれることだけが救いだったが、亜衣は自分のせいで先輩社員が八木に目を付けられてしまうのではという事を恐れて、なるべく先輩に頼らないようにしていた。新入社員同士で飲みに行っても、なるべく愚痴は吐かずに前向きに話をするよう努めた。
『あなた最近痩せたわよ。それに何となくボーっとしていることも増えた気がするし。仕事無理しすぎなんじゃない?』
仕事から帰った亜衣に母が尋ねた。どちらかというと活発な方だった亜衣が、最近は疲れ切っている様子に両親は気を病んでいたのだ。亜衣もそれに気づいていたので、慣れないことをしているのだから多少は仕方ない、自分は大丈夫だと答えた。
ただ、八木の説教とはほかに、亜衣には気がかりが一つだけあった。それは、自分のロッカーに入れたはずのペンやハンカチが、知らない間に無くなっている事が度々あった。それだけなら自分がどこかに置いたのだろうと考えることもできるが、ある時にはロッカーに入れてあるはずの財布から金がなくなっていることがあった。給料が安い会社だからそういうこともあるのかと亜衣は波風を立てることを恐れ、なるべく財布には必要最低限の現金しか入れないようにしていた。
ある日八木に呼び出され、先日の営業先の商談状況を報告していると、八木のペン立ての中に自分のペンがあることに気付いた。どこにでもあるようなペンなので紛れてしまってもわからないが、先っぽにテープを巻いて名前を書いていたので、自分のものであるとすぐにわかった。一通り報告が終わった後に八木にペンを返してほしいと話すと、また八木の逆鱗に触れこんなことを言われた。
『お前が自分で失くしたんだろ!俺が泥棒だとでも言いたいのか!なんて女だ!』
とてつもない剣幕で捲し立てる八木に、自分が失くしたものを拾っていただきありがとうございますとその場を収め、足早に自分のデスクへ戻った。亜衣は、自分が失くしたものではないという事を確信していた。なぜなら、仕事用のペンは別に購入しているため、入社式で配られた名前入りのペンは一度も使っていなかったからだ。どういう理由なのか分からないが、一連の私物や現金がなくなるのは、八木の仕業なのではないかと、薄々亜衣は考えるようになった。
例の先輩社員にペンの事を相談した。
『あの、私のペンが無くなったと思っていたら、部長のペン立てにあったんです。まさか部長って社員の私物を盗んだりとかするんですかね。』
すると先輩社員は、今までそんなことは聞いたことないし、さすがの八木もそこまでする人ではないと言った。逆に、自分の不注意で失くしたことを人のせいにするのは良くないと注意を受けてしまった。それからというもの、八木の叱責や私物の紛失など嫌なことが重なり続けるものの、先輩社員にも相談がし辛くなってしまい、次第に亜衣は自分の中だけでこの悩みを留めておくようになった。
冷たい手触り
それからというもの、度々自分の持ち物が無くなったり、仕事でも自分がやった覚えのないことで指摘を受けたりすることが多くなってきた。それと共に八木からの高圧的な叱責も重なり、亜衣は次第に神経をすり減らしていった。亜衣としては先日の一件があるため、持ち物の件や仕事での身に覚えのない事象については、間違いなく八木の嫌がらせだと確信していた。
しかしながら、様々なことが重なって仕事のミスが増え数字も伸びない亜衣に対して周囲の目も冷たく、次第に社内で孤立していった亜衣の味方をしてくれる人が居る訳もなく、亜衣の社会人生活は日を追うごとに窮屈なものに変わっていった。当然サービス残業等のブラック体質も変わるわけもなく、亜衣は心身ともに疲れ切っていた。
会社の総務部へ相談に行ったこともあった。これまで自分の身の回りで起きている事、八木からの過度な叱責などをどうにか改善できないモノだろうかと話してみたが、またしても持ち物が無くなるのは自分の管理能力の問題であり、それを八木の事と結びつけるのは考えが甘いと一蹴されてしまった。当然八木の叱責や詰問に対しては話が及ばず、亜衣は肩を落として総務部のドアを出た。
入社して初めての長期連休があった。長期と言っても土日を挟んだ4日間のお盆休みだったが、それでも毎日サービス残業の亜衣にとってはまたとないリフレッシュタイミングだった。朝はゆっくり寝ていられるし、急いでトーストを頬張る必要もない。亜衣は両親と共に買い物に行ったり外食をしたりしながら、久々の心の休息に穏やかな時間を過ごしていた。しかし、突然事件は起こった。
ある朝起きてみると、普段は8時になれば餌が欲しいと鳴き出す飼い犬が妙に静かなことに気付いた。名前は『マロン』といい、亜衣が中学生の時に両親に買ってもらった。一人っ子だった亜衣はマロンを自分の兄弟のように可愛がっており、学生時代に遊び歩いている時もマロンの世話だけは欠かさず行っていた。そんな亜衣なので、何かが違うと気づくのは当然の話だった。
玄関から出てサンダルを履くと、引き戸をガラガラっと開けてマロンを呼んでみたが応答がない。いつもなら鎖のリードをシャンシャン鳴らして吠えるはずだった。嫌な予感がした。恐る恐るマロンの小屋に足を運んで覗いてみると、そこにはぐったりと横たわったマロンの姿があり、亜衣は悲鳴を上げた。亜衣の悲鳴を聞きつけた両親が何事かと家の外に飛び出してきた。
『マロン!!!』
亜衣はすぐさまマロンを抱きかかえるも、冷たくなったマロンの体はすでに固くなっていた。いつもだったら自分の顔をペロペロと舐めてくるマロンが、今はまるで木彫りの彫刻のように動かない事と、想像もしていなかった事実に亜衣は涙を流して母に抱きついた。よく見ると、マロンの顔には何かで殴られたような、どこかにぶつけたような傷があり、小屋の外にも血が付いているのが分かった。亜衣は咄嗟に八木の顔を思い浮かべ怒りに震えた。
両親にも会社で起きていることを話して、きっと今回のマロンの事も八木の嫌がらせに違いないと話をするが、両親は証拠もないしそんなことはないと言ったきり黙ってしまった。しばらくの沈黙が流れた後、亜衣は両親に対して会社を辞める決意を話した。八木の度重なる叱責とサービス残業、持ち物の紛失、さらにはかけがえのないマロンを失った亜衣は、それが八木の仕業であると思っている以上、もう会社に居続ける意味もないと決断したのだ。
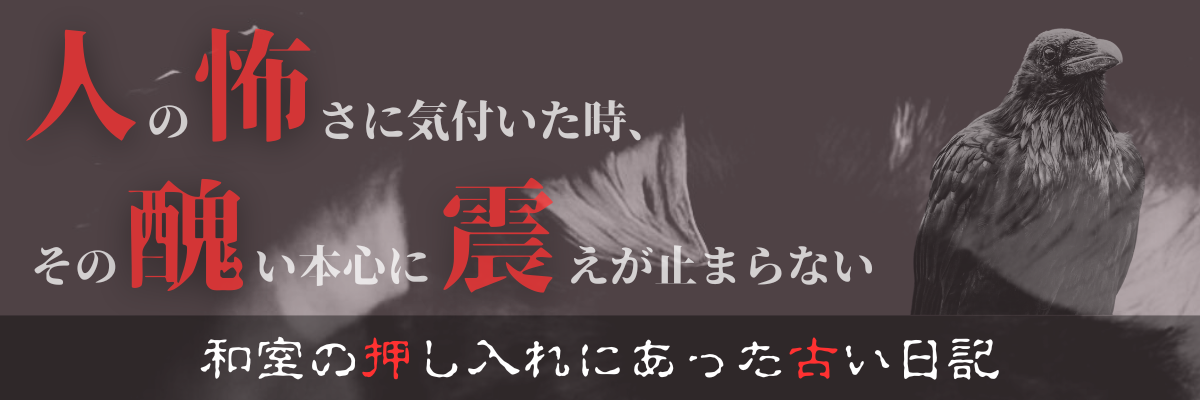




コメント