北海道目梨(めなし)郡にある羅臼湖(らうすこ)は、海岸線からの標高差が大きいため平地が少なく、知床峠までの道のりは、徒歩で辿り着くには難所が多い場所だ。木々から枯れ葉が落ちる季節になれば、辺りは一面の雪景色となり、動植物の生活に大きな影響を及ぼす。
この話は、そんな羅臼湖にほど近い小さな集落で噂される、ある洞窟に纏わる話だ。
閉ざされた集落
日本が戦争から復興の途中にあった1930年代、地方では、所謂小さな集落が点在していた。いくつかの世帯が身を寄せ合って生活をしているその集落では、外界との関りが皆無で、ほとんどの場合、その集落の数十人だけの生活が、そこに生まれた人たちの全てだった。

食物や衣服など、生活に必要なものはお互いに分け合って生活をしており、自然と合理的な役割分担が形成されていた。
そのような限定的なコミュニティでは、しばしば独特の風習や特異な習わしがあったりするもので、言い伝えなどについても、その集落独自の文化や考え方が変化して生まれたものが多かった。
北海道の知床峠に近い羅臼村(旧植別村)近くでも山間の地域には小さな集落が存在し、独自の生活と独自の文化を持っていた。古くは江戸幕府によって仮直轄地とされた地域でもあり、もっと古くは『クナシリ・ナメシの戦い』があった場所であることから、『独自文化』という観点では歴史の多い場所でもある。
与一が住んでいた集落もその一つだった。物心ついたころには薪割りを教えられ、クマよけの鈴は隣の家のおじさんが作ってくれたものだ。冬になると豪雪地帯となるため、住まいの移動を余儀なくされた。冬場は天然の屋根がある山肌の崖の近くに集落ごと移動するのだ。与一はそれが普通の事と思っており、特に疑問を抱かずに育った。
与一の家族は、もうすぐ80歳になる祖母と与一の母、自分の3人家族だった。祖父は昔クマに襲われ、父は与一が2歳の時に忽然と姿を消した。山が近く、野生動物の狩りをすることもあるため、行方不明になるのはそれほど珍しくもない話だったが、与一の父は『鈴落ちの洞窟』に消えていったと与一は教えられた。
鈴落ちの洞窟というのは、冬になると移動する崖の近くにある小さな洞窟で、天然の湧水があることから、集落の人間は神聖な場所として祀ってきた。しかし、その場所は曰く付きの場所でもあり、子供には近づいてはいけないと広く周知されていた。
鈴落ちの洞窟に纏わる曰くは次のような内容だった。

昔からその洞窟には神様と魔物が同居していた。普段は、雪の多い過酷な環境で暮らす自分たちのために、神様が湧き水や野生動物を分け与えてくださっている。しかし、欲を張った人間が独り占めしようと洞窟へ入った時、魔物がその人間を地獄へ連れ去ってしまうという。
魔物は鈴の音が嫌いなので、人間が身に付けた鈴を引きちぎって放り投げるため、行方不明者が出た際には、雪の中に鈴だけが残されている。このことから、その洞窟は『鈴落ちの洞窟』と呼ばれるようになった。
与一は、共同生活における強欲さを禁ずる大人たちの躾だと思っていた。しかし、与一が成長するにつれ、いろんな人に鈴落ちの洞窟の話を聞くと、どうやらそうではないらしい。
ここ15年ほど、悪天候が続いて作物が取れない時期が度々あった。その度に、集落を代表した男どもが鈴落ちの洞窟へ赴いて神様にお祈りをしようと出かけていた。しかし、そのうちの数人が戻ることなく、雪解けを待って洞窟へ行くと、その男のつけていた鈴が転がっているという怪事件が起きていた。
与一の祖母は80歳という当時としては異例の高齢者だったため、集落の歴史についてよく昔話をしてくれた。
『この土地はなぁ、昔っから貧しくて、食べるものにも困ることもあった。猪や兎なんかも、大雪の中じゃなかなか見つからないから、粟の煮汁で飢えを凌いだこともあったなぁ。』
祖母は木彫りのような手を擦りながら、囲炉裏の炎を見つめてそう言った。
『食べるものを争って殺し合いが起きたこともあった。それもこれもこの土地の運命(さだめ)じゃてのぅ。それでも洞窟の神様に祈って何とか生きてきたんじゃ。』
『じいちゃんも鈴落ちの洞窟に行ったの?』与一はほとんど閉じている祖母の目を見て言った。
『いやぁ、どうじゃろうな。それはよくわからんが、じいさんの食事は美味かったなぁ。』祖母が懐かし気に語る様子を見て、『どんな食事だったの?』と聞くと、『さぁて、大昔の話だから覚えてないが、一度しか食べなかったがな。』と祖母は答えた。
祖母は今で言うところの痴呆症が進んでいたので、与一は話半分で聞いていた。祖母からは結局鈴落ちの洞窟について詳しいことは聞けなかった。ただ、集落の大人に話を聞くと、少なくともこの10年ほどで、20人近くの男があの鈴落ちの洞窟に出かけて、命を落としているとのことだ。正確に言えば、死んだかどうだか分からないが、あの洞窟に行って帰らなかったのは確からしい。
洞窟の噂
与一も15歳を過ぎると、すでに体は大きくなっており、集落の中でも大人扱いされるような立場になっていた。力も強く、長老である祖母を持っているため、小さな集落ではそれが自然なことに思えた。
年を重ねるにつれて、与一は父が消えたとされる『鈴落ちの洞窟』について興味が湧いてきた。正確に言えば、もしかしたら自分が犠牲になるかもしれないという薄っすらとした恐怖もあってのことだ。
幼馴染の弥生とは、家も隣で仲が良かった。弥生の家は与一と同じように父が居らず、これもまた、鈴落ちの洞窟に消えていったと言われていた。ただ、弥生の父の弟、つまり叔父は、冬場の狩りの最中に一度だけ鈴落ちの洞窟で奇妙な体験をしたことがあるという数少ない人物だった。
賀次郎(がじろう)という名前の弥生の叔父は、父とは違って昔から体が弱く痩せていた。今も、ほかの男たちに比べて体が小さく力も弱いため、どちらかというと女衆に交じって田植えや機織り(はたおり)をしていることが多かった。
賀次郎は体が小さい割に、ハキハキと喋る男だった。
『俺が17になる年だった。兄さんはもう二十歳を超えてたから、父さんたちに交じって冬になるまでは猪を追いかけてたんだ。俺は走ることが出来なかったから、母さんと家で薪割りを手伝ってたんだ。兄さんが戻ってくるのが遅かったから、母さんに言われて山の方へ見に行った時なんだ。』
賀次郎は薄い衣服の襟元を、両手で引き寄せて身を縮めた。
『ちょうどあの鈴落ちの洞窟の入り口のところから、鬼火が見えたんだよ』
『鬼火?』与一は大きな疑問を投げかけた。
『ああ、鬼火だよ。死んだ人が魂だけになって現れるとか、神様が怒っているんだとか聞いたことがあるが、とりあえず俺が見たのは、洞窟の奥の方で橙色をした鬼火だったんだ。』
賀次郎はしっかりとした口調で与一に語り掛けた。鬼火というのは、地方の言い伝えにはよくある話で、ほとんどが山火事を見たり、山で焚火をしている姿を遠くから見ている場合がほとんどだ。しかし、賀次郎の場合は洞窟の中で鬼火が見えたという点が特異な点だった。洞窟の中は鍾乳洞に近い湿った場所になっているため、火が出るような要素がなかったのだ。
『それとな』賀次郎は身を乗り出して話をつづけた。
『洞窟の近くに行って初めて鬼火が見えたんだが、山を登っている最中に奇妙な音が聞こえたな。低くて大きな音だったが、ドーーン、ドーーンっていう音が辺り一面に響いているような音がしていた。どこから聞こえたのか分からなかったがな。』賀次郎が言い終わると、与一の背中に祖母の声が聞こえた。
『そんな話はデタラメだ!神様を粗末にしたらいかん!』
ゆっくりとした口調ではあるが、諫めるような祖母の口調に賀次郎は口を閉じた。与一の祖母は年寄りだということもあって、神様の存在を集落の人間に強く説いていた。だからこそ、与一にもあの洞窟には近づいたらいけない、命を取られたらどうするんだと何度も言い聞かせていた。
祖母がそう言って家に戻ると、与一は弥生と顔を見合わせた。
祖母が居なくなったと同時に、賀次郎が二人に手招きする仕草をしながら、小さな声でこう続けた。
『実はな、これは俺の親父、つまり弥生のじいちゃんになるが、そのまた父ちゃんから聞いた話だ。あそこの洞窟は昔から墓の代わりに使われていたらしいんだ。この辺の地域は雪が降ったら場所が分からなくなることがあるだろ?死んだ人を普通に埋めちまうと、雪が降って天国への道が閉じられちまうし、死んだ人間の家族もどこに埋めたか分からなくなっちまう。だから、目印としてちょうどいいあの洞窟に死んだ人を放り込んでたっていう噂もあるって話だ。』

囲炉裏の揺らめきに照らされた賀次郎の体は、壁に小さく細い影を映し出していて、まるで死神のように見えた。賀次郎の話の真偽は分からないものの、与一と弥生にとって、何かある曰く付きの場所であるということだけは確かな事実と言って間違いなかった。
新たな犠牲者
その年の冬になると、与一たちは山間の崖の近くに住居を移し、厳しい寒さに耐えながら肩身を寄せ合って暮らしていた。冬は気温が下がり水が凍ってしまうため、例の洞窟の近くにある湧き水を利用する必要があった。当然昼間に行かないと、持って帰る間に水は凍ってしまう。
その年の冬はいつにも増して作物が不作だったことから食糧難に陥っていた。ある日、集落の男が山へ兎狩りに出かけて暫く帰ってこないという事件が起きた。集落の人々はまさかと思い不吉な予感と寒さに震えていた。
与一は自分が様子を見てくると申し出た。祖母や母には止められたが、その制止を振り切ってクマよけの鈴と小さなランタン、万が一の時のナイフを手に、与一は山道を歩きだした。
まだ昼間だというのに山道には雪が積もっていた。太陽は出ているが、山肌のくぼみにできた道には日が当たらないからだ。時折吹き抜ける風が木々を揺らして轟々と音を立てた。与一はゆっくりと、そして確実に、あの鈴落ちの洞窟へと歩みを進めていった。
しばらくすると、与一の目には雪の上にかすかに残った足跡が見えた。動物のものと人間のものは足跡が違うので、与一にはそれが人間のもの、すなわち行方不明になっている男のもであろうと確信があった。やはりあの男も鈴落ちの洞窟へ向かったのだ。
足跡を辿っていくと、遠くに黒い洞窟が見えた。
鈴落ちの洞窟だ。
山道はその先も続いているが、洞窟がある場所は中腹に位置しており、山の中でも一層暗く、異様な雰囲気を放っていた。賀次郎の話が本当だとするならば、この先にたくさんの死体が埋められている、与一はそう考えるとこのまま進むことを少し躊躇した。
洞窟の入り口まで来ると、与一は手に持ったランタンで洞窟の中を照らしてみた。足元は少し明るくなったが、それでも真っ暗な洞窟は先へと続いていた。ずいぶんと長い洞窟になっているようで、集落の人たちが近づかないのも頷けた。この中へ入ったら、もう帰って来れないかも知れないと与一は思った。
そんな雰囲気も、与一の好奇心をくすぐるには十分すぎた。与一は恐る恐る洞窟の中へと歩みを進めていった。
少し洞窟を進むと、与一は不思議な感覚を覚えた。確かに暗く湿った感じがして不気味ではあるが、洞窟の中は風がないため、ほんの少し暖かい気さえした。自分の足音と、どこからともなく聞こえる水が滴る音だけが洞窟の中には響いていた。
どれくらい歩いたか定かではないが、洞窟は大きく右に折れた道になっていて所々狭く、与一でもすり抜けていくのがやっとだった。
さらに歩いていくと、少し広くなった部屋のようになった場所へ着いた。そこには石を積み上げて作ったような祭壇のようなものがあり、恐らくこれが集落の人が言う神様を祀った場所なのだろう。とは言え、その場所の大きさは便所よりも少し大きいくらいで、たくさんの人が一度に集まるような場所ではなかった。
賀次郎の話にあった墓の代わりというのが本当だとすれば、この場所に多くの人が埋められているはずだ。ただ、与一はそれに少し違和感を覚えた。仮に墓場の代わりに使われていたとして、人を埋めるなら穴を掘る必要がある。穴を掘ったら、その土をどこかへ運ばなければいけない。ただ、自分が通ってきた道には、狭く通りにくい場所が多かったので、なかなか骨の折れる作業になるのではないか。
そう思って与一は今にも消えそうなランタンで周りを照らしてみた。すると、始めは気づかなかったが、その部屋のような形をした祭壇の脇に先へ通じる道がまだあることに気付いた。真っ暗な中、祭壇に目を取られていると気づかないような位置にあった。
その道を与一はゆっくりゆっくりと歩いて行った。足音はまだ響いている。どうやらこの先の道は長く続いているようだ。ふいに、与一は歩みを止め、耳を澄まして持ってきたナイフに手をかけた。これから自分が進んでいこうとする先に、低い唸り声のような音が聞こえたからだ。
壁をつたいながらさらに進むと、先ほどの祭壇と同じような、小さな部屋のようになった場所を見つけた。ランタンで照らそうとしたとき、与一は何かを踏んでいることに気が付いた。足元を照らすと、それは例の男の鈴だった。
『ま、まさか・・・』
嫌な予感がした与一は恐る恐るその鈴の先をランタンで照らすと、そこにはあの男がミイラのような顔で横たわっていた。思わず後ずさりした与一だったが、ふとおかしなことに気付いた。その男の死体をよくよく見てみると、左腕と右脚がなかった。まるで斧で分断されたかのような状態だった。与一が気になったのは、その分断された腕と脚が見当たらなかったことだ。
男の死体に気を取られて気付かなかったが、まだ先へ続いている洞窟はかすかに明るくなっているような気がした。光を頼りに進んでいくと、どうやら出口になっているらしかった。
『そうか、俺が入ってきた場所とこの場所がトンネルのようになっているんだ』与一はそう思った。先ほど聞こえた低いうなり声だと思ったのはここから聞こえた外の風の音だったようだ。外へ出た与一は愕然とした。

そこは鬱蒼と繁った森の中へ通じていて、とてもじゃないが引き返すしかないという事と、その山の中に、人骨とみられる骨が自分の背丈よりも高く積まれていた。これが賀次郎の言っていた墓なのか、そんなことを思いながら、与一はとりあえず来た道を引き返して家族の待つ家へと急いだ。
深まる疑惑
与一が帰ると、集落一帯は例の洞窟の話で持ちきりだった。与一は見てきたことをそのまま祖母と母に話し、それが人伝に集落全体へと伝わるまでそれほど時間はかからなかった。
特に、犠牲になった男の家族には、母からいち早く伝えられた。娘は涙を流し、男の妻は怒り狂っていた。しかし、その様子がどうもおかしかった。
『何故自分の夫が犠牲にならなければいけないのか?うちの順番じゃないはずだ』と言うようなことを喚き散らしていた。与一は『順番』と言う言葉が妙に引っかかって母に尋ねたが、母は、しばらく鈴落ちの洞窟には近づかないほうがいいと言って詳しく話そうとはしなかった。
犠牲になった男の娘は千鶴子と言った。与一や弥生と同じくらいの歳だが、少し千鶴子の方が若かった。千鶴子の祖父も鈴落ちの洞窟で命を落としており、以前からその噂については疑問を持っていたと言うのだ。また、千鶴子が気になっていたのは、自分たちが知っている限りで、犠牲になっているのはいづれも男性であると言う点だった。
確かに言われてみれば、与一の父、弥生の父、そして今回千鶴子の父と、子供を持つ親の世代の男性が犠牲になっているのだ。これが犠牲者の共通点なのか?しかし、賀次郎にも子供はおり、体は弱いが洞窟に行ったこともあることや、過去には与一のような結婚前の青年も犠牲になっているらしいことから、この推測は的外れに思えた。
千鶴子は、女性の犠牲者がいないと言うことと、自分たちが知っている中で、犠牲になった男衆の共通点が分かれば、何か見えてくるものがあるのではないかと考えた。そのことについて与一と弥生に話をすると、二人もその考えに同調した。
ただ、大人達にこの事を話すと、はぐらかされるか叱られるかするだけだったので、自分達だけで秘密裏に探っていく必要があった。
こうして、共に父をあの鈴落ちの洞窟で奪われた3人は、洞窟に潜む謎と、集落に隠された秘密について調べてみることにした。
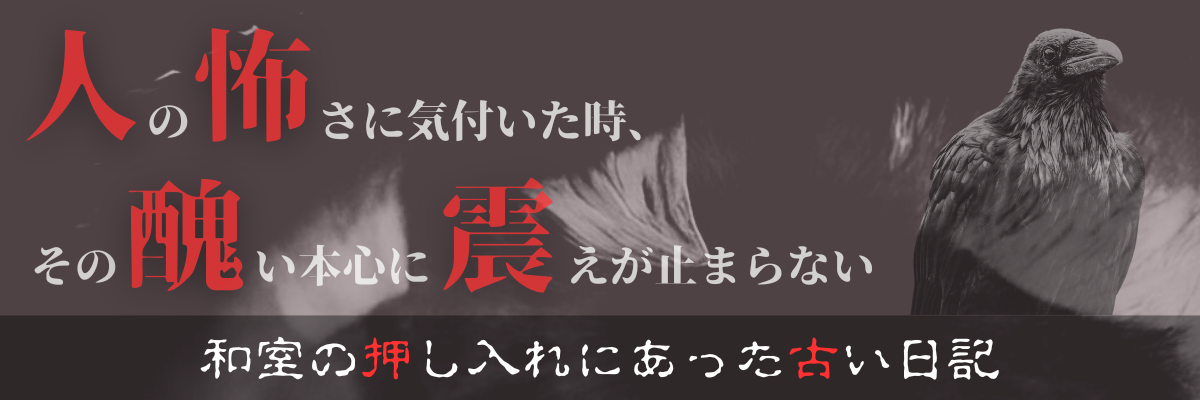




コメント